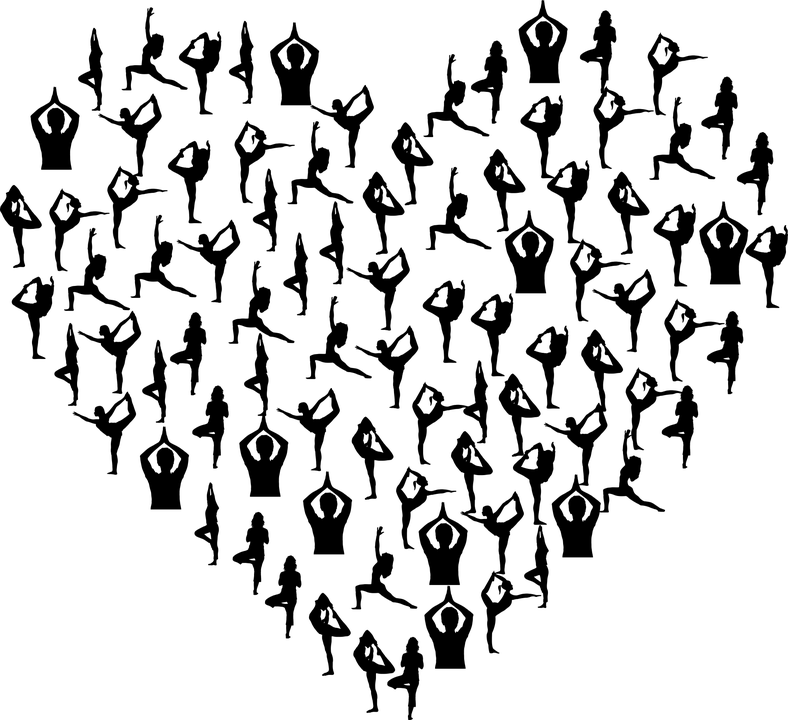共感性恐怖とは
共感性恐怖を感じる母から子へ
共感性恐怖とは、他者の恐怖を自分も感じてしまう、特に母から子へといったケースが多いでしょう。
親に対する子どもの適切な愛着を妨害する要因は、親の愛情不足という場合も稀にはあるでしょう。
しかし、それ以上に、愛情はあっても共感性が乏しいために、安定した愛着が形成できず期待された役割を生きる自分を育ててしまうことが多いのです。
急速に発展してきた脳神経科学や発達心理学、とりわけ誕生前後の発達を扱う周産期心理学は、母子間の微妙な交渉を明らかにしています。
たとえば、脳神経科学は、人間の脳にはオシレーターと呼ばれる他者からの刺激に合わせて自分の脳内神経の働きを同調させる機能が備わっていることを明らかにしています。
こうした機能に支えられてか、赤ん坊と母親との間には心身の多様な共感性恐怖や同調性が存在するのです。
母親と赤ちゃんとの良好な交流がなされている状態では、心が通じ合っているという母親の主観的な心理的体験だけでなく、呼吸や感情、動作など、生理的にも身体的にも同調作用や共感性恐怖が生じています。
母親は自分で意識していなくても、特別な感受性をもって赤ちゃんに反応しており、視線、表情、声、動作などで赤ちゃんと相互に影響し合っています。
たとえば、赤ちゃんが声を出すとか、ばたばたする、泣くなど、なにか行動すれば、赤ちゃんが母親の表情を見やすい位置まで近づいてあげて、同じ視線の高さになるように腰をかがめ、まなざしを赤ちゃんに向けて、言葉をかけます。
このとき、赤ちゃんの様子に応じて、声の高さ、発音の明確さ、話すテンポなどを変えます。
この言葉に赤ちゃんが反応するのを待ち、次の発声や行動を調節します。
赤ちゃんも母親を見つめたり、視線をそらしたり、笑顔を見せたり、身体を動かすなどして、母親の反応をコントロールしています。
このようにして、母親は赤ちゃんに共感し、共鳴しながら、安心を与えたり、楽しさを与えたり、快感を与えたりしているのです。
こうした親の姿こそ、無条件の愛の実像といえるものですが、この共感的なやりとりのなかで、愛されているという根底的な確信が子どもに作られていくのです。
赤ちゃんへの母親のこうした共感的対処や共感性恐怖は、母親が赤ちゃんの衝動や感情に服従していることではありません。
注意深い観察研究によれば、母親は非常に忍耐強く赤ちゃんに接しており、想像以上に早い時期から赤ちゃんに要求的だということです。
母親は、ビデオの超スロー再生でないと分からないような微妙な視線や表情、間などで赤ちゃんに要求を伝えており、赤ちゃんもまた、それに調整的に反応しているというのです。
このように母親は赤ちゃんに共感し、赤ちゃんの感情や諸欲求を受け入れつつ、その延長線上に赤ちゃんを導いてあげているのです。
養育者のこうした共感性を伴った導きができないと、子どもに期待された役割を生きる自分の育成を強制することになってしまうのです。
共感性に乏しい養育
親が十分な共感性を発揮できない理由として、いろいろなケースが考えられます。
自分のことで精一杯
その一つは、親が、自分や家族のことで重大な問題を抱えているなどで精神的な余裕がなく、子どもに対して十分な配慮を払えない場合です。
親が子育てを面倒だと感じるのは、子どもの本来的な衝動や欲求、願望に根ざす行動に粘り強く対処しなければならないときです。
たとえば、子どもが聞き分けなく甘えようとするとか、欲しいとねだってだだをこねるといった行動への対処です。
余裕のない親は、こうした子どもの行動に対して、不快感情をもって拒絶するか、怒りや叱責、脅し、あるいは無視で応えがちです。
こうした対応を頻繁に体験すれば、子どもは自分の欲求や願望、衝動を抑え、欲求満足の快感をあきらめるようになります。
アルコール依存症の親を持つ子どもなど、親が問題を抱えている家庭で育った子どもがアダルト・チルドレンになることはよく知られていますが、アダルト・チルドレンとは、親が自分のことで精一杯で、子どもが期待された役割を生きる自分を発達させざるを得なかった姿に他なりません。
性格的な共感性の乏しさ
共感性には個人差があります。
非常に共感性豊かな親もいれば、共感性に乏しい親もいます。
期待された役割を生きる人の身体感覚には、歪みや鈍感さがあることが少なくありませんが、これは共感性に乏しい親の養育に起因していることがあります。
赤ん坊や幼児は、最初から自分の身体感覚を適切に意味づけることができません。
空腹や腸の変調は、いずれも腹部の不快感として体験されます。
この不快感のために泣くと、養育者が「お腹がすいたのね」とか「お腹が痛いのね」などと、意味づけをしてくれ、適切な対応をしてくれます。
こうしたことが重なって、身体感覚とそれが意味するものとが結びついていくのです。
ところが、共感性の乏しい親は適切に解釈できず、身体感覚とは異なる意味づけをしてしまうとか、親の都合で意図的に意味づけを歪めてしまったりします。
たとえば、子どもが寒さを感じていないのに、風邪を引かせることを恐れて、「寒い、寒い」と言って厚着させてしまいます。
栄養をバランス良くとらせようとする意図のもとに、自分でもおいしいと思わないものを「おいしい、おいしい」と意味づけたりします。
こうした親の意味づけが優先されるので、幼い子どもは自分の感覚を信頼できず、感覚を歪めたり、鈍麻させたりしてしまうことになります。
思考や行動に柔軟性が乏しく、物事に執拗にこだわる強迫的性格の親は、子どもに共感性を欠いた対応をしがちです。
それが共感性恐怖をもたらします。
共感性恐怖の例1.
「母は何事も徹底しないと気が済まない性格でした。
それを子どもにも要求するのです。
洋服をたたんでも、折り目がずれていると、やり直しをさせられました。
宿題などでちょっと乱れた字を書くと、全部消してやり直しです。
それで、表面だけはきちんとやる、という癖がつきました。
目に見えないところはいいかげんにやっているので、それで、精神的におかしくならないでいるっていう感じです。」(二十代 女性)
共感能力を測定した研究によれば、一般に男性は女性よりも共感能力が劣っています。
男性は女性のような細やかさで子どもの内面に対応しようとしません。
このことは、動物でも見られるそうです。
たとえば、セキセイインコの卵は、孵化する時期がそれぞれ異なるのですが、このために、母鳥は後から生まれた弱い子に先に餌をやるという注意深さを発揮します。
ところが父鳥はそんなことには無頓着で、手近かの子に勝手にやってしまいます。
父親の養育への関与の必要性を強く主張する人もいますが、父親が養育に関与したために好ましくない影響がもたらされた事例が少なからずあります。
共感性恐怖の例2.
「父は法学の教授で、小さい頃、私の勉強を見てくれていました。
でも、私の理解が遅いので、二人ともイライラして気分を害して終わることが多かったのです。
『なんで出来ないんだ』と、しょっちゅう頭をたたかれました。
げんこつで思い切り殴られて、鼻血が止まらなくなったこともありました。
父は、私の顔を見ると、決まって『がんばっているか?』と声をかけてきます。
励ましてはくれるのですが、褒めてくれることのない父でした。
だから、父がいるところでは、自分に何か落ち度があるんじゃないかと不安になって、今でも緊張してしまいます。
自分は無能だって感じてしまいます。」(女子大生)
子どもの内面を読み取る能力はあっても、感情表現において抑制的な親は、子どもの期待された役割を生きる自分を育ててしまうことがあります。
乳児と母親とのやりとりを分析したスターンという研究者は、情動調律という概念を提唱しています。
乳児と母親との間には感情を中心にした無数のやりとりがありますが、その際に母親は乳児の感情を読み取って、感情を適度なレベルに調整するとか、感情を開放する方向へと導いてあげるなど、乳児の内面に対応した働きかけをしているというのです。
これにより共感の交流がなされ、子どもは養育者に対して愛着を形成し、安心感をもつのです。
そして、このとき、養育者が子どもの感情や意図を適切に読み取っているだけでは不十分であって、「あなたの気持ちを分かっているわよ。あなたの気持ちを受け止めているわよ」というメッセージを返してあげることが決定的に大事だというのです。
ですから、共感していることをうまく伝えられない養育者に対しては、赤ちゃんは安定した愛着を形成できず、期待された役割を生きる自分を発達させてしまい共感性恐怖の発生の元となるのです。
また、こうした家庭では、知的雰囲気や建前が優先して、生身の本音の感情交流がなされません。
共感性恐怖の例3.
「両親とも教員で成熟した大人でした。
私をいつでも高いところから冷静に見守っているという接し方でした。
愛されていたことは疑いないのです。
でも、愛されているという実感は持てませんでした。
むしろ信頼されていることに応えなければ、という無言の圧迫感の方が強かったように思います。」(男子大学生)
親自身が自分の感性や感情を信頼して育つことを教えられていないと、子育てが自然な感情の交流ではなく、「考えること」「頭ですること」になってしまいます。
そして、こうした人は、しばしば完璧な親になろうとします。
外目にもそのように見られることが少なくありません。
関連記事
共感性恐怖は愛情不足から生まれる
共感性恐怖は欲求不満の表れである
感情抑制的な家庭では、幼いころから言葉でのやりとりが優先されがちです。
言葉とは感情の代理物であり、共感性恐怖といった衝動的行動の代理物です。
たとえば、乳幼児は不快さという感覚に、泣いて反応します。
欲求不満のときには、だだをこねたり、泣くという行動で表現します。
言葉を獲得すると、この直接的行動は、「痛いよ」とか「お腹がすいたよ」などの愛情不足の共感性恐怖は言葉に置き換えられていきます。
感情抑制的な家庭では、こうした言葉の置き換えの傾向が強く、それがいき過ぎてしまうことがあるのです。
羞恥心の恐怖
また、感情抑制的な親は、身体的接触をも抑制する傾向があります。
このために、子どもは言葉としての愛情表現を受けても、身体的に豊富な受容体験を持てません。
それで、無条件に愛されているという感覚に疑惑が伴い共感性恐怖を発生させます。
この疑惑を振り切るためにも、子どもは自分と身体とを切り離すということにもなるのです。
さらにいえば、こうした家庭では、身体自体を恥ずべきもの、汚いものと意味づけする傾向が強くなります。
子どもは、一時期、おしっこやうんちに興味を持ちます。
男女の性器の違いに興味を持ちます。
性器をもてあそんだり、自慰をすることもあります。
こうした子どもの関心や行動を過度に辱めたり、禁止すると、自分の身体そのものが恥ずべきもの、気持ちの良いことは否定されるべきものと子どもが受け取ってしまいます。
その結果、楽しむこと、気持ちの良いこと、楽であること、こうしたことが罪責感と結びつくことになります。