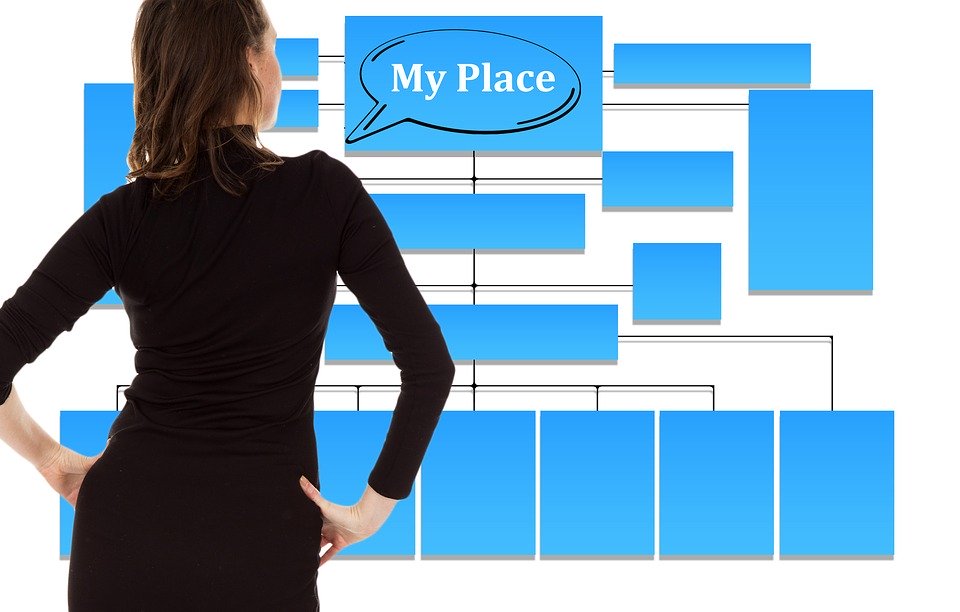対人不安とは
対人不安とは楽な自分で他人と接しないことから生まれる
現実に友達付き合いがあまりない場合も、友達とはうまく付き合っているという場合も、誰もが心の中では対人関係に不安を抱えているものである。
たとえば、話すことに関して不安がある。
よく知らない人や、それほど親しくない人と会う際には、「うまく喋れるかな」「何を話せばよいのだろう」「場違いなことを言ってしまわないかな」などといった不安が頭をもたげてくるため、会う前から緊張する。
相手から好意的に見てもらえるかどうかが不安だという心理もある。
誰だって相手から否定的に見られたくないし、好意的に見てもらいたい。
でも、絶対的な自信がある人などいない。
そこで、「好意をもってもらえるかな」「嫌われないかな」「うっとうしがられたら嫌だな」などといった不安に駆られ、相手の言葉や態度に非常に敏感になる。
相手からわかってもらえるかどうかが不安だという心理もある。
何か言おうとするたびに、「共感してもらえるかな」「変なヤツと思われないかな」「退かれたらきずつくなあ」などといった不安を感じるため、気になることもなかなか率直に言いにくい。
このような対人関係の場で生じる不安を「対人不安」という。
心理学者バスによれば、対人不安とは、人前に出たときに感じる不快感であり、つぎのような心理傾向を指す。
- 初めての場に慣れるのに時間がかかる
- 人に見られていると仕事に集中できない
- とても照れ屋である
- 人前で話すときは不安になる
- 大勢の人の中では気を遣って疲れる
ほとんどの項目があてはまるという人が多いのではないか。
日本人の多くがこのような心理傾向をもつと考えられる。
心理学者シュレンカーとリアリィは、対人不安とは、現実の、あるいは想像上の対人的場面において、他者から評価されたり、評価されることを予想することによって生じる不安であるという。
この定義は、バスの定義と比べて、対人不安が生じる心理メカニズムにまで踏み込むものと言える。
つまり、人からどのように評価されるかをきにするあまり不安が高まる、それが対人不安だというのだ。
対人不安が強いと、対人場面を恐れ、回避しようとする。
不安なために、人のちょっとした言動にもネガティブな意味を読み取り、傷つきやすい。
対人関係を回避しようとするため、率直なかかわりができず、いざというときに助けになる絆ができにくいということもある。
学生も、子育てしている母親たちも、企業でも、対人不安の反応が多い。
そして、自分自身について、つぎのように語る。
「誰かから話しかけられたらどうしようという気持ちが強くて、学校ではいつも緊張している」
「進学したり、クラス替えしたりするたびに、うまくやっていけるか不安が強かったけど、未だに慣れないし、就職して新たな人間関係の中でちゃんとやっていけるか不安」
「断られるのが怖くて、友達を自分から誘えない」
「高校でも大学生になっても、グループができると、その中でしかつきあわない傾向があり、みんな対人不安が強いように思う」
「相手からどう思われるかがとても気になり、自分をさらけ出すことができない」
「相手から好意をもってもらえるか不安で、嫌われないかといつも脅えている」
「相手によく思われたい気持ちが強くて、無理して合わせたり、つまらないと思われないように必死になって喋ったりしている」
「相手のノリが悪いと、やっぱり自分の話はつまらないんだと思い、落ち込んでしまい、ますます気まずい感じになる」
「こんなこと言ったら嫌われ、仲間外れにされるのではと思って、何を話したらいいか悩むことがある」
「自分に自信がないから、思うように言いたいことを言えなくて、ストレスが溜まる」
「不安のあまり汗をかいたり、イライラしたりして、自分の嫌な面が出てしまう」
自分は誰とでもうまくやっていけるタイプだと思っていたけど、対人不安の話を聞くと、たしかに自分にもそういう面があるし、これまで意識したことはなかったけれど、けっこう無理して気疲れしていることに気付いた、という声もある。
このように多くの人が対人不安を抱えているようだが、「嫌われたくない」という思いの強い人が非常に多いことがわかる。
「こんなことを言ったら嫌われるのでは」といった思いが強すぎるため、言いたいことも言えず、嫌なことも嫌と言えない。
嫌われるかもしれないといった不安、いわば「見捨てられ不安」が強い。
友達と一緒でも心から楽しめない
そんなふうに気を遣うために友達と一緒にいても心から楽しむことができない。
初対面の相手と話すときに気を遣って疲れるのはわかるが、友達と話していても疲れる自分はおかしいのではないか。
そんな悩みを抱えている学生もいる。
「友達といると、ふつうは楽しいんですよね。でも、僕は楽しいっていうより疲れる。僕の言ったことや態度で友達を不快にさせていないか、いちいち考えながら発言したり行動したりしているから、疲れちゃうんです。だから、家に帰ると疲れが出て、しばらく動けなくなります。なぜ自分は友達と話すのにこんなにも神経をすり減らすのか。こんなに気を遣っているのに、なぜ親しい友達ができないのか。やっぱり僕はどこかおかしいんじゃないか。最近そんな思いが強くて、友達付き合いがぎくしゃくしてきて、どうしたらいいかわからなくなって・・・」
このように悩みを訴える学生は、このままでは苦しくてしようがないから、なんとかしてそんな自分を変えたいという。
でも、考えてみれば、相手の反応に一喜一憂したり、相手の反応が気になって気が休まらなかったりするのは、多かれ少なかれ誰もが経験することであって、とくに異常なわけではない。
友達付き合いを楽しんでいる人でも、相手の反応は気になるものだ。
友達が傷つかないように言葉を選ぶ。
友達の反応を見て、気分を害していそうだったら、フォローする言葉を添えるようにする。
友達がつまらなそうな様子だったら、話題を変える。
沈黙が続くと気まずいので、何か話さなければといったプレッシャーがかかる。
そうしたことは、人付き合いをする上で欠かせない配慮であって、けっしておかしなことではない。
問題なのは、それが行き過ぎて友達付き合いを楽しめないことだ。
気をつかいすぎて、何を話したらよいかわからなくなってしまう。
神経をすり減らすため、人付き合いを避けるようになってしまう。
そんなことにならないようにするには、対人不安とはどういうものなのか、どうしたら少しでも軽減できるのかを知ることが大切だ。
場違いな自分を出してしまう不安
対人不安が強い人にありがちなのは、二人っきりならまだよいのだが、相手が複数いる場が苦手というものだ。
大勢の場では気疲れして、楽しいはずの飲み会でさえも全然楽しめなかったりする。
だが、これも度が過ぎなければとくに問題ではなく、だれもが抱える心理と言える。
なぜなら、僕たちは相手に合わせる習性を身につけているからだ。
相手が傷つくような話題は避けたい。
できるだけ相手の期待を裏切りたくない。
そんな思いを抱えて人付き合いをしている。
相手によって感受性も違えば、価値観も違う。
それによって、どんな話題がコンプレックスに触れるかも、どんな話題を好むかも違ってくる。
そのため、相手が複数の場合は、それぞれの人物の反応を注視しながら自分の言動を調整していかなければならないため、非常に神経をつかうのだ。
そういった意味での気遣いは誰もがしている。
ただし、対人不安の強いタイプは、相手の反応を気にしつつも、それをうまく読み取る自信がない。
そのため場違いな自分を出し、気まずい感じになってしまう。
そんな経験をしているために、相手が複数いる場では非常に気疲れするのだろう。
相手によって違う自分が出ているから自分は多重人格なのではないか。
自分は裏表のある人間なのではないかと思うと自己嫌悪に陥る。
そんな悩みを抱えている学生もいる。
まじめで誠実であるがゆえに、自分が一貫しない人間、不誠実で調子のよい人間のように思えてしまうのだ。
だが、それはべつに気に病むようなことではない。
相手によって違う自分が出ているのは、ごく自然なことなのだ。
心理学の草創期に、定番となる心理学の教科書を執筆したジェームズは、人は自分を知っている人の数だけ社会的自己をもつが、同じ集団に属する人たちからは似たようなイメージをもたれているだろうから、人は属する集団の数だけ社会的自己をもつと言っている。
社会的自己とは、わかりやすく言えば、他者からもたれるイメージのことである。
ジェームズの指摘するように、僕たちは所属する集団によって、同じ人物でありながら多少なりとも異なるイメージをもたれているものである。
それは、集団によって雰囲気が異なり、出しやすい自分が微妙に違っているからだ。
家族といるときの自分と学校で友達といるときの自分が違うというのは、だれもが経験するところのはずだ。
先生の前での自分と友達の前での自分が違うというのも、ごくふつうのことだろう。
好きな異性を前にしたときの自分は、何でも話せる同性の親友の前での自分とはかなり違うのではないだろうか。
そこで「自己概念の場面依存性」という考え方がある。
自己概念というのは、自分のイメージのようなものだ。
自分のあり方は、だれと一緒の場面かによって違ってくる。
つまり、自己概念は場面に依存している。
ゆえに、自分の様子が場面によって異なるのは当然のことなのだ。
場面によって自分の出し方を変えるというのは、言い換えれば、場面にふさわしい自分を出すということである。
それができないと個々の場面に適応していけない。
だからこそ、場違いな自分を出しはしないかと気になるのだ。
いつも同じ自分でいればよいというのなら、だれも自分の出し方で気をつかったりはしない。
自己開示の抑制要因
自分の経験したことや思っていることを率直に話すことを自己開示という。
友達にもなかなか率直に心を開けない若者が増えている昨今、ここに自己開示の抑制要因についての調査研究がある。
結果、自己開示を抑制する心理的要因として、つぎの三つが抽出された。
- 現在の関係のバランスを崩すことへの不安
- 深い相互理解に対する否定的感情
- 相手の反応に対する不安
1.現在の関係のバランスを崩すことへの不安というのは、重たい話を持ち出して今の楽しい雰囲気を壊すことへの不安や、お互いに深入りして傷つけたり傷つけられたりすることへの恐れの心理を反映するものである。
2.深い相互理解に対する否定的感情というのは、友達同士であっても感受性や価値観が違うものだし、自分の思いや考えを人に話してもどうせわかってもらえないだろうというように、人と理解し合うことへの悲観的な心理を反映するものである。
3.相手の反応に対する不安というのは、そんなことを考えるなんて変なヤツだと思われないか、つまらないことを深刻に考えるんだなあと思われたら嫌だ、などといった心理を反映するものである。
このような思いがあるために、率直に心を開きにくいわけだ。
実際、150名ほどの大学生に、日頃よく話す友達に自分の思っていることを率直に話しているかどうか尋ねた調査がある。
ほとんどの学生が率直に話すのは難しいと答えているが、その理由として、以上の三つのいずれかをあげている。
典型的な反応として、つぎのようなものがみられた。
「相手の反応が気になり、プライベートなこととか、自分の内面については話せない。自分の意見にも自信がなくて、相手に呆れられてしまうのではと思ったりして、なかなか意見も言えない」
「友達に本音を言おうとしても、それを理解してくれなかったときのことを考えると、なかなか話す気持ちになれません。
本音を言うには勇気がいります」
「みんなはどう考えているんだろうと周りを気にして、自分の考えを言うのはすごく勇気がいる」
「相手がどう思うかを自分は気にし過ぎだと思うけど、どうしても気にしてしまう。自分の思うことを素直に言える人が羨ましい。よっぽど自信がある人でないと、言えないと思う」
「仲間外れにされる恐怖というか、みんなが自分と違う考えや感じ方をしていたらどうしようといった思いがあって、自分の思っていることをはっきり言いにくい」
「私は、自分の思ったことを率直に友達に言うというのはできません。やっぱり嫌われるのが怖いから」
「意見が違うと、せっかくの関係が悪化してしまうのではないかと考えてしまい、自分の意見があってもなかなか言えない」
「自分の意見を言える人はごく少数だと思う。自分もその場の雰囲気に合わせた発言をしたり、相手が喜びそうな意見を言ったりする」
「こんなことを言ったら相手が気分を害するのではとか、感受性が違ってたら相手が話しにくくなるかもしれないなどと思い、何を話したらよいかをかなり吟味する」
このように、今の関係を崩すことを恐れたり、相手の反応を気にしたりするあまり、自分の意見や思うことを率直に話せないといった心理が、多くの若者に共有されていることがわかる。
そうした現状に対して物足りない思いがある。
自分だけでなく、友達もさしさわりのない話をするだけの関係を物足りなく思っており、もっと率直にいろいろ話せるようになりたいと思っているかもしれない。
そう思ったりもするのだが、自分の側から一歩を踏み出す勇気がない。
そこには、前述の三つのうち、1.の「現在の関係のバランスを崩すことへの不安」と3.「相手の反応に対する不安」が潜んでいるのである。
■関連記事
内向型人間の楽になる人付き合い
自分に自信がない人が自信をつけるポイント
他人の目を気にする対人不安像
人から見られる自己像への不安
対人不安の心理メカニズムを検討したシュレンカーとリアリィは、「自分が人からどのように見られるか」という不安の核にあるとみて、対人不安の生起メカニズムについての仮説を提起している。
そこでは、先にも紹介したように、対人不安は、現実の、あるいは想像上の対人場面において、他者から評価されたり、評価されることを予想したりすることによって生じる不安、というように定義されている。
かみ砕いて言えば、現実の対人場面において、他者からどのように評価されているかを想像することによって生じる不安、あるいはこれから人前に出るというときに、他者からどのように評価されるだろうかと想像することによって生じる不安が対人不安である、ということになる。
そして、対人不安を自己呈示に関連付けた生起モデルを提唱している。
自己呈示というのは、他者に対して特定の印象を与えるために、自分の情報を調整して相手に示すことである。
「こう見られたい」という自己イメージにふさわしい自分の見せ方をすることであり、いわば一種の印象操作だ。
その対人不安生起モデルは、好ましい自己像を示そうという自己呈示欲求が強いほど、また自己呈示がうまくいく主観的確率が低いほど、対人不安は強くなる、というものである。
そのモデルに従えば、人からよく見られたいという思いが強く、かつ人からよく見られる自信がない人ほど、対人不安が強いということになる。
ゆえに、対人不安の強い人は、人の目に映る自分の姿が自分が望むようなものになっていない、あるいはならないのではないかといった不安が強い。
これを自己呈示に絡めると、対人不安の強い人というのは、人からよく見られたいという思いは強いのに、効果的に自己呈示ができない人、いわば人の目に映る自分の姿を自分にとって望ましい方向にもっていく自信が乏しい人ということになる。
そこにあるのが評価懸念だ。
友達としょっちゅうつるんでいても、不安で仕方がない。
どう思われるかを気にするばかりで気が休まらない。
相手からどう評価されるかが気になる。
否定的に評価されないか不安になる。
それが評価懸念だ。
対人不安が強いと、評価懸念が強く意識される。
そのため、相手が何気なく口にした言葉やちょっとした態度の変化にも否定的な意味を読み取って、落ち込んだり狼狽したりする。
相手の視線を否定的に解釈してしまうのだ。
たとえば、相手はとくに何とも思っていないのに、相手から変に思われているのではないか、相手を傷つけてしまったのではないかなどと気になる。
相手がべつに機嫌を損ねたわけでもないのに、機嫌を損ねたと思い込む。
相手の何気ない言葉に勝手に怒りを感じ取ったり、何気ない態度に無視されたとか冷たくされたなどと思い込んだりする。
ときに嫌われているとかバカにされているといった被害妄想的な心理に陥ることもある。
そこに働いているのが「敵意帰属バイアス」だ。
「敵意帰属バイアス」とは、他者の言動を敵意に帰属させる認知の歪みのことである。
あの人があんなことを言うのは、あるいはあんな態度を取るのは、敵意をもっているからだ、こちらのことを嫌っているからだとみなす認知傾向の歪みのことだ。
他の人なら素通りするような他者の言動にも、いちいち感情的に反応する。
嫌われたに違いない、きっと呆れているなどと思い込んで落ち込む。
バカにしている、嘲笑っているんだなどと思い込んで腹を立てる。
たとえば、友達から何か言われたとき、そこに勝手に敵意を感じ取り、「こっちのことをバカにしてるんだ」などと否定的に解釈する。
友達の何気ない言葉や態度に敵意を感じ、「仲間外れにしようとしてる」「こっちのことを嫌っている」などと悪意に満ちたものと解釈する。
そこにあるのが、何でも悪意に解釈する認知の歪みである敵意帰属バイアスだ。
それがあるために、相手には何の悪意もないのに誤解して、勝手に落ち込んだり腹を立てたりする。
とくに、自分に自信がなく、見下され不安を抱えている場合は、「バカにされるのではないか」「軽く見られるのではないか」「嫌われるのではないか」といった不安が強いため、人のちょっとした言動にも「バカにしてる」「軽んじてる」「嫌われている」などと敵意帰属バイアスを示し、ますます自信をなくし、人付き合いに消極的になってしまう。
周囲の反応をモニターしつつ自分の出し方を調整する
対人不安の強い人は、自己モニタリングがうまく機能していない。
心理学者のスナイダーは、自分自身の感情表出行動や自己呈示を観察し、それをコントロールする性質には個人差があることを指摘し、そうした個人差を説明する要因として、自己モニタリングという概念を提起した。
スナイダーによれば、自己モニタリングとは、自分の感情表出行動や自己呈示を観察し調整することを指す。
言い換えれば、自己モニタリングとは、印象管理の一種で、その時々の対人場面において、どのような振る舞い方が適切かを察知し、自分の言動を調整することである。
自分が他人の目にどのように映っているかを気にする、つまり自分の言動に対する周囲の反応をモニターするのは、自分の言動をその場にふさわしいもの、相手との関係性にふさわしいものに調整していくために必要なことであり、適応のために欠かせない心の機能である。
自己モニタリング傾向の強い人は、自分がどのように見られるかについての関心が強く、自分の行動の適切さに対する関心も強くなる。
そのため、自分の言動に対する相手の反応をたえずモニターし、相手のちょっとした感情の動きに敏感に反応して自分の行動を調整しようとする。
自己モニタリング傾向が適度にあることは社会適応につながるが、強すぎると気疲れして、ストレスを溜め込むことにもなりかねない。
逆に、自己モニタリング傾向の弱い人は、人からどう見られるかとか自分の言動がその場にふさわしいかどうかにはあまり関心がない。
そのため、自分の行動をモニターする傾向が弱く、自分の思うままに発言したり行動したりする。
これまでに見てきたように、対人不安の強い人は、相手の反応を人一倍気にする。
それは、自己モニタリングが強く働いていることを意味する。
その意味では、人からどう見られるかを気にする対人不安は、それが度を超さなければ、適応的な心理メカニズムとみなすこともできる。
ただし、何ごとにも程度の問題がある。
対人不安が強すぎると、自己モニタリングが強くなりすぎて、非常に窮屈なことになる。
人の目に自分がどのように映るかが気になるために、たえずモニター画面に自分の姿や周囲の人の様子を映し出してチェックせずにはいられない。
いわば監視カメラをたえず意識しすぎるため、自分が何か言ったりしたりするたびに、自分の言葉や行動が適切だったかどうかが気になり、周囲の反応ばかり窺うようになって、ぎこちなくなり疲れてしまう。
それによって対人不安がさらに強まる。
対人不安が強いから自分の言動が不適切なのではないかと気になり、自己モニタリングが強まる。
ここに強すぎる自己モニタリングと対人不安の相互作用による悪循環が生じる。
それに対して、対人不安がまったくなければ、相手の反応などまったく気にならない。
気楽に人とかかわれる。
ただし、場にふさわしくない言動をとっても平気であり、相手を不快にさせても傷つけても気にしないということになりかねない。
相手が不愉快になっても傷ついても気にならず、周囲から怪訝な目で見られても気づかない鈍感なタイプは、対人不安がなく、本人は気楽であっても、けっして適応的とは言えない。
このように対人不安と強く関係している自己モニタリング傾向は、他者の言動の意味を解釈する能力(解読能力)と自分の言動を調整する能力(自己コントロール能力)の二つの側面からとらえることができる。
つまり、自己モニタリングには、他者の反応をみながら自分の言動が適切かどうかを判断する能力と、適切な言動を取るために自分の言動を場にふさわしい方向へと調整する能力の二つの側面がある。
心理学者のレノックスとウォルフは、この二側面に対応させて、他者の表出行動への感受性と自己呈示の修正能力という二つの因子からなる自己モニタリング尺度を作成している。
それらがどのような心理傾向を指すのかがわかるように、いくつかの測定項目を例示してみよう(レノックスとウォルフの尺度項目より一部抜粋)
<「他者の表出行動への感受性」因子の主な測定項目>
- 相手の目を見ることで、自分が不適切なことを言ってしまったことにたいてい気付くことができる
- 他者の感情や意図を読み取ることに関して、私の直観はよくあたる
- だれかが嘘をついたときは、その人の様子からすぐに見抜くことができる
- 話している相手のちょっとした表情の変化にも敏感である
<「自己呈示の修正能力」因子の主な測定項目>
- その場でどうすることが求められているのかがわかれば、それに合わせて行動を調整するのは容易いことだ
- どんな状況に置かれても、そこで要求されている条件に合わせて行動することができる
- いろいろな人たちやいろいろな状況にうまく合わせて行動を変えるのは苦手である(逆転項目=あてはまらない場合に自己呈示の修正能力が高いことになる)
- 相手にどんな印象を与えたいかに応じて、付き合い方をうまく調整することができる
対人不安の強い人は、相手の反応をたえず気にしている割には、これらの能力が低いため、自己モニタリングがうまく機能せず、場違いな自分を出してしまったりする。
「調子に乗り過ぎた」「ちょっと言い過ぎた」「ノリが悪かったかも」などと反省し、自己嫌悪に陥る。
それによって、ますます相手の反応が気になってしまうのである。
自己モニタリングがわりとうまく機能しており、人の気持ちを敏感に察知して自分の言動を調整できるため、人間関係はうまくいっているという人も、相手の気持ちの変化に注意を集中するのに疲れ、じつは人付き合いに消耗していたりする。
さらには、対面のつきあいと違ってSNSが苦手だという人が多い。
それは、相手の表情も声色もわからず、相手の反応が読めないからだ。
そのため、持ち前の自己モニタリング能力を発揮できず、自分の言動をどう調整したらよいかが判断できない。
それで、メッセージを送信した後は、相手の意向に沿った反応ができたか、こちらの意図が正確に伝わっているかが心配でならず、相手の反応が返ってくるまで気が気でない。
SNSによるトラブルが多いのは、自己モニタリングがうまく機能しにくいメディアだという事情があるのだろう。
視線恐怖も人への配慮のあらわれ
対人不安はだれもがかかえる心理傾向だが、もうちょっと病的なものに対人恐怖がある。
対人恐怖とは、対人場面できわめて強い不安や緊張が生じ、行動がぎこちなくなり、人から変に思われるのではないかと恐れるあまり、対人関係を避けようとする神経症のことである。
インド哲学者中村元は、日本人に対人恐怖症が多いのは、個人に対して人間関係が優越していることに由来するものだろうというが、まさに対人恐怖こそ日本人の心理傾向をよく映し出すものと言える。
それは、人間関係に大いに規定され、「人の目」を強く意識する特性と密接に結びついている。
精神医学者木村敏によれば、対人恐怖という名称自体が日本人による数少ない独創のひとつであり、これに相当する西洋語は元来存在しなかったようだ。
このことは、まさしく対人恐怖という症状が日本人の心理傾向を反映するものである証拠と言える。
相手に見られている自分の姿について、病むほどに悩むというところに、「人の目」に強く規定されている日本人の心理的特徴が如実にあらわれている。
対人恐怖の中でも、視線恐怖は日本人特有の神経症であり、海外ではほとんど論じられないと言われる。
視線恐怖とは、対人関係に支障をきたすほどに視線が気になって仕方がないという症状に苦しめられる病理をさす。
人の視線が気になり、視線を合わせなければと思うのに、どうしても相手の目を見ることがができずに悩むというのが、視線恐怖の典型である。
相手の目をまともに見ることができないため、挙動不審に思われるのではないかと気になり、人付き合いが苦痛になる。
自分の視線が気になって仕方がないといった形の症状もある。
たとえば、人と話しているときに突然自分の目つきが悪いのではないかなどと気になってきて、ぎこちなくなってしまうため、人と会うのが苦痛になる。
こうした症状が出ることがあるくらいに、日本人にとって「人の目」というのは重要な意味をもっている。
人からどう思われるかが気になって仕方がないからこそ、このような症状に悩まされるのであって、人からどう思われてもいいと思っていたら、「人の目」など気にならないし、視線恐怖に悩まされることもない。
そうしてみると、多少なりとも視線恐怖気味になるのも悪いことではないと言えるのではないだろうか。
それは相手のことに配慮する心をもっていることの証拠でもあるのだ。
人の気持ちなどどうでもいいと思えば、「人の目」など気にせずに自分勝手に振る舞える。
「人の目」=「相手の思い」を気にすることで利己的な思いにブレーキがかかるのである。
■関連記事
他人の目が気になる人は他人との接し方を変える
役割期待のずれはイライラの原因
会話の対人不安
相手との関係性によって決まってくる言葉遣い
ここでは対人不安とは何かを探ってきたが、「それ、自分にもある」と思った人が多いのではないか。
じつは、対人不安は日本人の多くが抱える心理と言える。
このことは日本語の特徴にも深くかかわっている。
日本語では、相手との関係性によって言葉遣いが決まってくる。
逆に言えば、相手との関係性がはっきりしないとどんな言葉遣いをしたらよいかがわからない。
そうした言語を日常的に用いることで、相手の様子を窺い、相手の気持ちを気遣うようになっていく。
英語の「I」は、一般に「私」と訳される。
英語を初めて習うとき、そのように習い、誰もが「I」は「私」のことであるのは当然と思い、疑うことはない。
だが、心理学的にみると、「I」と「私」はまったく違った心の性質を表していると言わざるを得ない。
その違いは、「I」と「私」という言葉の使われ方に端的にあらわれている。
英語の「I」というのは、どんな文脈に置かれても「I」である。
友達と飲んで騒いでいるときも「I」、家族団欒の場でも「I」、職場でも「I」、得意先の人を前にしても「I」である。
どんな場面でも、「I」は「I」であり、姿形を変えることはない。
それに対して、日本語の「私」は、文脈によってその姿形を変えるのが常である。
友達と飲んで騒いでいる時は「オレ」になり、家族団欒の場では「お父さん」になり、職場でも同僚と話すときは「僕」となり、上司と話すときには「私」であり、得意先と話すときには「私」だったり「ウチ」や「小社」だったりと、文脈によって変幻自在に姿形を変える。
だれの前であろうと「I」は「I」なのだとでも言うかのような英語の「I」の断固たる姿。
それに対して、相手がだれであるかによって姿形を変えていく日本語の「私」の揺らぎやすさ、相手との関係性がはっきりしないと形が定まらない不安定さ。
それは見事に好対照をなしている。
まるでどんな場面でも自分の意見や要求を堂々と主張する欧米人と、たえず相手の出方を窺いつつ相手に合わせて自分の出方を決めようとする日本人の姿を見るようだ。
こうした対人場面における心のあり方の違いが、言葉遣いに端的にあらわれている。
このような心のあり方の違いと言葉の用いられ方の違いの対応に目を向けると、私たちの心のあり方が言語によってつくられていることがよくわかる。
「I」と「You」もうっかり日本語に訳すと何だか不自然な感じになる。
たとえば、日本語では、「君は僕のことをどう思ってる?」というよりも、「僕のことどう思っている?」の方が自然だろう。
「私はあなたが好きよ」というよりも、「好きよ」の方が自然だろう。
「I」も「You」もいらない言語表現は、まさに主客が溶け合う心をもつ日本流と言ってよい。
「私はおかしいと思う」と言うと、何だか相手と切り離されているような感じになるため、「何だかおかしいね」と共感を誘うような言い方をする。
「私はこんな風に考えるけど、あなたはどう?」などとは言わずに「こんなふうに考えていいのかな」と言うのも、「私はこの景色に感動した」などと言わずに「こんなふうに考えていいのかな」と言うのも、「私はこの景色に感動した」などと言わずに「感動的な景色だね」と言うのも、相手と自分を明確に切り離さない感受性によるものと言える。
たえず相手の視点を意識し、相手の思いや考えを想像し、共有できそうな思いや考えを主語なしでつぶやく文化では、自称詞も対称詞もいらず、主客溶け合った心理状態に漂うようにして対話が進む。
相手を気遣う心理は日本語使用と深く結びついている
このような言語使用をする日本人は、個の意識が希薄だと言われる。
それが短所のように受け止められがちだが、けっして悪いことではない。
個の意識が希薄だからこそ、相手と自分が切り離されておらず、お互いに共感でき、察し合うことができる。
「あの人だったらどう感じるだろう」と想像する習慣が身についているため、共感能力が高いのである。
個の意識に凝り固まっていたら、そのように他者の視点に想像力を働かせるのが難しいはずだ。
その証拠として、精神医学者の土居健郎が、アメリカに研修に行った際に、アメリカの精神科医の共感性の鈍さに驚いた経験について述べている箇所を見てみよう。
「(前略)私はその間アメリカの精神科医が実際にどのように患者に接しているかをあらためて観察する機会を与えられた。(中略)その結果アメリカの精神科医は概して、患者がどうにもならずもがいている状態に対して恐ろしく鈍感であると思うようになった。
いいかえれば、彼らは患者の隠れた甘えを容易に感知しないのである。(中略)
普通人ならともかく、精神や感情の専門医を標榜する精神科医でも、しかも精神分析的教育を受けたものでさえも、患者の最も深いところにある受身的愛情希求である甘えを容易には感知しないということは、私にとってちょっとした驚きであった。
文化的条件づけがいかに強固なものであるかということを私はあらためて思い知らされたのである。」(土居健郎『甘えの構造』)
また、心理学の立場から日本語論を展開している芳賀綏は、面白い例を用いて、日本人の気遣いをあらわす言語表現の微妙なニュアンスを描写している。
「バスの中で、旅行者らしい中年女性と土地の人らしい青年が並んで掛けていた。
考え事でもしていたのか、女性は乗り過ごしそうになり、気づくやあわてて降りようとした。
その背中へ、後に残った青年がちょっとためらいながら声をかけた。
「アノ、これ、違うんですか?」
女性は席にカバンを一つ置き忘れて降りようとしたのだった。
―青年の発話に、相手の呼称も、代名詞も、出現していないのがおもしろい。
「小母さん!」とも「あなた!」とも呼べず、「アノ、」となった。
そして「小母さんのカバン」でも「あなたのカバン」でも落ち着かない。
「これ」ですますことにした。
英語ならyour bagと言うのに何の迷いもあるはずがない(後略)」(芳賀綏『日本語の社会心理』人間の科学社)
芳賀は、年齢・性別・親疎など、いくつもの条件を考え合わせたあげく、使う語句を決定しかねると、こんな結果になり、どの語句を選んでも照れ臭さが絡んで口に出せないという心理の微妙さこそ、日本人の対人行動を描くのに欠かせないとしている。
まさに、そこに日本語とそれを用いる日本人の心の微妙な繊細さがある。
この青年の気持ちは日本人ならよくわかるはずだ。
丁寧語とはいえ年長者に「あなた」と呼びかけるのは失礼に当たる。
もちろん「君」とか「お前」などと言おうものなら、あまりに場違いで失礼なことになる。
このような相手に対しては、よく考えてみると適切な代名詞がない。
そこで、「小母さん」が頭に浮かぶが、もしかしたら気分を害するかもしれない。
そうかといって「お姉さん」では嫌味になるだろう。
そうなると、適切な呼びかけの言葉が思い浮かばず「アノ」となり、適切な所有格が見つからず「これ」で済まさざるを得ない。
このような言語使用をめぐる心の中の葛藤は、外国人からすればまったく理解不能に違いない。
こうした例からわかるように、ちょっと声を掛けるにも言葉遣いを巡ってあれこれ悩まなければならないほど、私たち日本人は常に相手がどう受け止めるか、相手の気持ちを思いやりながら行動しているのである。
言語学者鈴木孝夫は、相手が誰であっても「you」で済んでしまう英語について、徹底した自己中心主義であると指摘している。
相手が誰であるかは無視される。
二人称代名詞で呼ばれる相手は、自己にとっての相手に過ぎず、相手に即した相手その人ではない。
自分の目の前にいる他者から、その一切の個別性を奪って、それが自己に対立する相手であるという、自己本位の契機だけを抽象したものが、西洋の二人称代名詞であるというのである。
相手との関係性に考慮し、相手の気持ちまで思いやらないと言葉づかいも決められない日本語と、相手がだれであれ一定の言葉遣いで済ませられる欧米の言語。
そこには、その言語を用いる人の心が見事に映し出されている。
日本語を用いることによって自己形成をしてきた僕たち日本人は、たえず相手の気持ちを気遣いながら接するように習慣づけられており、それが対人不安の心理を生んでいるのである。
ゆえに、対人不安を抱えているからといってなにも悩む必要はない。
それは日本人なら誰もが抱える心理であり、けっして異常なわけではない。
日本語圏で生きる限り、むしろ適応的な心理と言ってよいのだ。
■関連記事
言葉は怖い、言葉の力を活用する