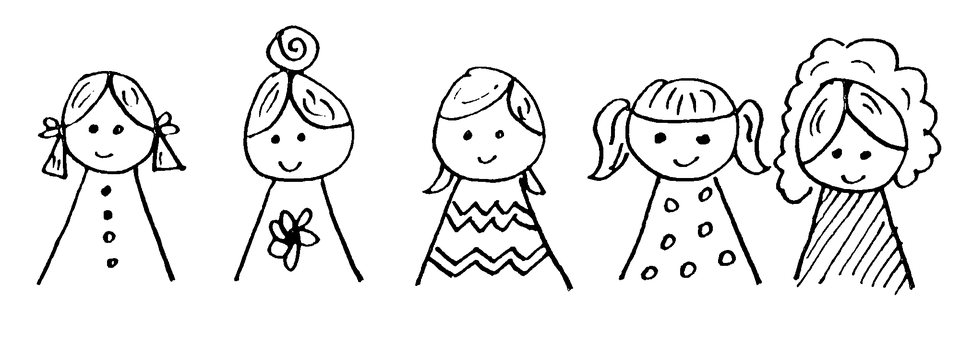部下を叱る本来の目的を忘れない
ある女性記者から聞いた話。
その記者はフリーで活動していて、雑誌の仕事で、著名な作家のインタビュー記事を書くことになった。
インタビューには、出版社の担当編集者も同行した。
編集者は、記者より20歳も年下だった。
インタビュー当日、編集者は録音機を持ってこなかった。
記者が持っていたので問題は起きなかったが、やはり担当として編集者が責任を持って録音すべきである。
それを先輩から教えてもらっていないのだろう。
まだ若い編集者のことを思って、記者は帰り道でアドバイスした。
「今日、どうして録音機を持ってこなかったの?」
すると、その編集者はちょっと不本意そうな顔をして黙り込んでしまった。
たぶん「余計なお節介だ」と思ったのではないか。
関連記事
- 辛い人間関係も自分の行動次第
- 人間関係の心地良い距離感
- 人間関係がめんどくさい人の心理と対処法
- 人間関係の戦場という職場を生き抜く
- 人間関係の苦しみを緩める方法
- いい加減な自分を認めると人間関係が楽になる
アドバイスをするのは、その人のことを気にかけているからだ。
「どうなっても知ったことではない」と思っていたら、人は何もいわない。
記者は編集者を気にかけたからこそいったのだが、それは相手に伝わらなかった。
なぜだろうか。
おそらく、その記者が選んだ言葉がまずかったのだ。
教えてやるという態度では人は教わらない。
こんなこと知らないのかじゃ、ダメなのだ。
アドバイスは説教くさくならないよう、「ちょっとしたヒント」程度に与えるのがいい。
距離感は遠めにしておいて、さりげなくヒントを投げる。
「今日は、あなた自身は録音しなくてよかったの?」
このくらい軽く振れば、編集者も「はっ」と気づいたかもしれない。
しかし、「どうして持ってこなかったの?」と詰問され、自分の落ち度を責められているように感じてしまったのではないか。
もちろん、録音機を持ってこなかった編集者は悪い。
だが人は、素直な気持ちでいなければアドバイスは聞かないものだ。
アドバイスをしようと思ったときは、その相手が素直な気持ちで耳を傾けられる状況が必要なのだ。
上司が部下を叱るときも、同様のことがいえる。
叱る目的は、部下のまずい行動を改めてもらうことであり、謝罪させることではない。
関連記事
- 人間関係での感情を考えるという扱い方
- 感情を放置せず、ケアをすれば人間関係は楽になる
- 人間関係での自信のつけかた
- 人間関係の疲れをとる三つの苦しさへのアプローチ
- 人間関係の感情の取り扱い
- 人間関係の疲れをとる5つの方法
表面上、どれほど反省した様子を見せてもらっても意味はない。
大事なのは「これではいけない」と本人に気づいてもらうことだ。
かつて、野球の野村克也監督は「教えるのではなく、相手に気づかせること。これが大切なのだ」といった。
本人が気づいてはじめて自分で納得するのである。
また、部下に素直に耳を傾けてもらう方法に「後褒め」がある。
「こんなミスしちゃダメじゃないか。キミらしくないね」
「これじゃ使えないな。キミならもっと面白いものができるはずだよ」
このように最初に厳しいことをいって、後から褒めるのだ。
人は最後にいわれた言葉が深く印象に残るから、叱られても頑なにはならない。
もちろん、徹底的に叱らなければならない場面もある。
だが、そんな気が重いことをするのも、部下に期待していればこそだ。
そうであれば、叱った最後に「期待しているぞ」と付け加えればいい。
イギリスの政治家チェスターフィールドはいった。
「忠告というものはめったに歓迎されない。しかも、最も忠告を必要としている人ほど、忠告を敬遠する」
この人間心理を理解していないと、効果的な叱り方はなかなかできない。褒めるより、叱る方がはるかに難しいのである。
関連記事
- 原始人メカニズムのネットまでの人間関係
- 人間関係の心地よい距離感
- 大人の人間関係でいい人でなくても大丈夫
- インターネットの人間関係
- 自分の軸をしっかり持てば良好な人間関係を築ける
- 職場での心地よい人間関係を保つ
部下は上手に褒めてモチベーションを高める
最近、課長に抜擢された30代前半の男性会社員は、上司からあまり褒められたことがなかった。
それは、彼が無能なのではなく、上司が非常に厳しい人だったからで、上司は彼をできる男と認めており、そのおかげで昇進できたのだ。
しかし、課長として部下を育てる立場になって彼はハタと困ってしまった。
自分が褒められて育っていないので、部下の褒め方がわからない。
あるとき、1人の部下がプロジェクトの進行報告書を提出してきた。
現状を丁寧に分析し、ポイントもわかりやすく説明している。
「うまくまとまっているな。これは助かる」
そう思ったが、何もいわなかった。
「今度、飲みにでも誘って褒めてやろう」くらいに思っていた。
ところが、数日して、その部下が尋ねてきた。
「先日、提出した報告書はいかがでしたでしょうか?」
その顔を見て、彼は「しまった」と思った。
関連記事
頑張って作成した報告書がよかったのか悪かったのか、どちらにしてもすぐに返事をもらえなかったことに、彼はがっかりしたようだった。
「褒めてもらえないこと」イコール「関心を持たれていないこと」だと思ってしまう。
そうした小さな失望感の積み重ねが、上司と部下の間にいつしか大きな距離を生むことにもなる。
「この企画書、よくできてるね」
「さっきの電話対応、なかなか上手だったよ」
「契約数が増えているね、その調子」
こんな簡単な一言を投げてあげるだけで、部下のモチベーションは大きく上がるのだが、それができない上司が少なくない。
褒めることを、大袈裟にとらえすぎているのかもしれない。
マネジメントに関する本を読むと、たいてい「叱るより褒めろ」と書かれている。
一つのことを叱るのであれば、その倍くらい、褒める気でなければいけないという。
たしかに、そうかもしれない。
褒められて嬉しくない人などいない。
部下を褒めて「その気にさせる」のは、上司の力量でもある。
しかし、褒めすぎるのも考えものではないか。
「褒めなければ」と、やたらと褒め言葉を連発すれば、やがてその効力を失ってくる。
どんなご馳走も、満腹状態では美味しく感じられないのと同じだ。
関連記事
- 争わない心理的距離で人間関係はうまくいく
- 「縦」ではなく「横」の人間関係を構築しよう
- 人間関係が怖いから気を楽にする心理
- 人間関係がしんどいから解放される心理
- 人間関係が辛い人が気が楽になる心理
- 人間関係がうまくいかない人がうまくなる心理
アメリカの行動心理学者リチャード・ファースンは、次の5つの理由から「褒める」ことへ疑問を呈している。
1.褒めると脅迫として受け取られる可能性がある
たしかに、褒められた部下は「だから、それを続けろよ」といわれていると受け取るかもしれない。
真面目な部下にとっては、かえってプレッシャーとなってしまうだろう。
2.相手の本当の価値を認めるより、自分の地位を相手の上に置くことになる
部下のいい働きをきちんと見ることをせず、「上にいる自分が部下を褒めてやっている」というスタンスに立ってしまえば、その上司は大きな勘違いをすることになる。
3.創造性を制限する
褒められたことで、相手が「自分はこれでいいんだ」と思い込んだら、そこで成長は止まる。
4.苦言も一緒にいいかねない
人間はつい余計なことを言いがちだ。小言をプラスしてしまえば、褒めたことまで帳消しになってしまう。
5.ほかの人と当人の人間的距離を広げてしまう
よくあることだが、特定の誰かを褒めることで、周囲にやっかみの感情が生まれる。
こうした感情は、露骨に表現されることはないだけに、難しい問題をはらむ。
このようにリチャード・ファースンが指摘するマイナス面を考慮せず、褒めることを、まるで「万能」のように扱うのは間違いだ。
上手に褒めれば、それは優れた武器になるが、下手をすると「やらないほうがよかった」という結果を招く。
褒めるときには、直接ではなく間接的に人を介するのもいい方法だ。
「〇〇課長から聞いたが、キミはずいぶん頑張っているそうじゃないか」
直属の上司がそういっていたといわれた部下は、直接褒められるよりもかえって嬉しく思うのだ。
第三者を経る距離感である。
いろいろな距離感の取り方で、適切に褒める。
これができたら、相当、有能な上司といえるだろう。
関連記事
- 人間関係がめんどくさい人を楽にする心理
- 人間関係に疲れた人へ送る処方箋
- 人間関係に無理しない方法
- 「人間関係が苦手」な人に贈るアドバイス
- 人間関係のストレス解消法
- 誠意と道理のない附随的な人間関係を捨てる
職場の人間関係は情にひかれると失敗する
中堅損保会社で営業職についている三十代の男性社員には、どう接していいか迷っている二人の先輩がいる。
一人は、入社したときから親切にしてくれた優しい先輩だ。
優しいのだが、仕事ができるとはいいがたい。
年度末に張り出される売り上げグラフでは、後輩の自分よりも成績が悪いのが明らかにされてしまう。
そんなときは、どう声をかけていいのかわからない。
もう一人の先輩は、やり手で有名だ。
強引に仕事を押しつけられることもある。
あまり好きなタイプではないが、きっと出世するだろうからにらまれたくもない。
さて、どうしたらいいか。
この会社に限らず、組織においてはさまざまな人間関係が存在する。
派閥もあればライバルもいる。
「敵の敵は味方」というおかしなことも起きる。
その中を、近づいたり離れたりしながら上手に泳いでいかなければならない。
仕事なのだから、そんなことに煩わされず業績を上げることだけに集中すればいいはずだが、現実にはそうはいかない。
人間関係で失敗したら、業績も上げにくくなるのが組織である。
ここは、ドライに考えるのがいちばんいい。
会社に在籍する限り、そこで自分が最も仕事がしやすく、最も評価されるところを目指すしかない。
優しいけれど仕事ができない先輩とは、とくに距離を置くこともないが、いま以上に縮めることもない。
挨拶や連絡事項をしっかり行なっていればそれでいい。
好きなタイプではないやり手の先輩とは、いずれ距離を近づける必要が出てくるかもしれない。
会社は競争社会であり、競争に勝つためには上層部から評価されている人のそばにいたほうが何かと有利だ。
とはいえ、その距離は会社での距離であって、プライベートまで近づくわけではないのだから、ことさら嫌がることはない。
「綱渡りより世渡り」という言葉がある。
世の中の人たちとうまくやっていくことは、綱渡りよりも難しいという意味だ。
しかし、本当にそこまで苦しむ必要があるのだろうか。
会社の人間関係で悩んでいる人は、ウエットにとらえすぎている。
関連記事
あくまで「会社の中のこと」だと割り切って、もっとドライに構えたほうがいい。
そもそも、「好き」も「嫌い」も人間の感情だ。
ウエットでいるから感情が顔を出す。
ドライを心がけていれば、サラリーマンを苦しめている問題の多くが解決するはずだ。
いまの若者はウエットで優しい人が多い。
たとえば、友人に不幸があれば自分のことのように心を痛める。
それは、もちろん悪いことではない。
ところが組織においては、優しさはときとして罪悪になる。
「自分の功績のために」と部下をこき使う、優しさのかけらもない上司がいる。
しかし結果的に、こき使われた部下は仕事ができるようになる。
一方で、「俺がフォローするから無理しないでいいよ」という優しい上司がいる。
この上司についた部下は、あとで苦しむことになるかもしれない。
以前、冨山和彦氏が書いた『結果を出すリーダーはみな非情である』という本が売れた。
その中に「リーダーに不可欠の条件はそんなに多くないが、外せないのは『合理的思考』力である」という一文がある。
ビジネスでは、非合理なウエットさは意味がない。
優しかろうと冷たかろうと、好きだろうと嫌いだろうと関係はない。
仕事そのものにその感情は必要ないのだ。
会社にいる目的は何か。
その目的を果たすために、どう動けばいいか。
ドライに考えていれば、いつも正しい距離が保てるはずである。