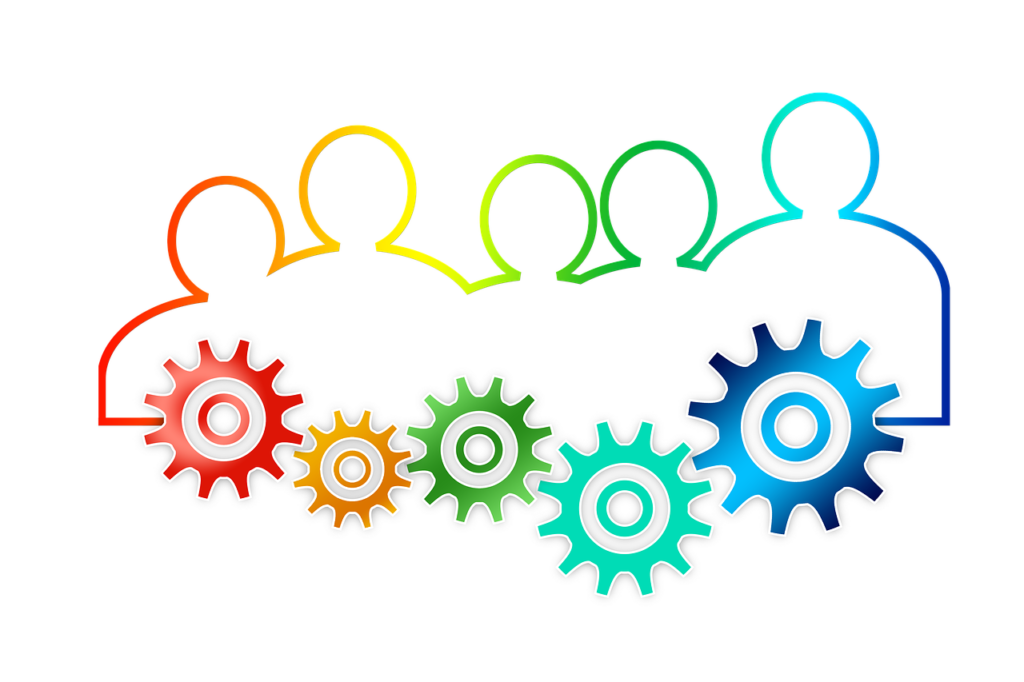親が子に接するなかで、意識的、無意識的に子どもの心深くに埋め込んでしまうものに、禁止令があります。
禁止令とは「××してはいけない」というかたちの呪文で、あなたの意識と行動を縛り付け、後に述べる人生脚本の基礎となり、また人生脚本を現実化させる作用を果たすものです。
存在してはいけない
「自分なんかいない方がいいんだ」というような投げやりな心理をもたらす禁止令です。
若くしてバイクで激突死したり、自殺する人などにその典型が見られます。
この禁止令は、「おまえさえいなければ・・・」という情緒的雰囲気のなかで育てられることにより、形成されます。
吉川英治は『忘れ残りの記』のなかで書いています。
父親の暴力に家を飛び出して行った母親に付いて行くと、「おまえたちさえ産んでいなければ」と言って母親が泣くのが、いかにつらかったかを。
親から離され、親戚や祖母などに預けられて育てられる子どもにも、この禁止令がつくられる場合があります。
男(女)であってはならない
この禁止令は、自分が男(ないし女)であることが親に対して申し訳ないような気持ちを持つ人がいます。
「おまえが男だったら」とか「今度こそ男と思ったのに」などと聞かされて育つと、こうした禁止令が形成されます。
あるいは、父親を嫌っている母親に育てられた男の子が、自分を男として受け入れられなくなる、などという例もあります。
この禁止令があると、同性の仲間よりも異性の仲間と一緒にいるときの方が居心地が良いと感じたりします。
また、異性との自然な性的関係が結べないこともあります。
子どものように楽しんではいけない
この禁止令が内在化した人は、楽しむことが罪悪であるかのように感じられます。
このために、なにをしても夢中になれず、どこか気がかりな感じになります。
集団のなかにいてもとけ込めず、孤独感を感じます。
過度に自己抑制的になり、いつも追い立てられ、せかせかと動き回り、場合によっては他の人に献身することによって救われるかのような気持ちを持つこともあります。
この禁止令は、禁欲的な親や感情抑制的な親によって形成されます。
また、無心に遊んでいる子どもに「宿題は済んだの?」などと、親が水を差す行動をとることにより形成されます。
家族の困難のために、小さいときから大人の役割の一端を担うことを強制されて育ったために形成された例もあります。
さらに、親戚の家や、父方の実家など、甘えが許されない環境により形成されることもありますし、逆に過保護で友達との自由な遊びが制限されて育ったような場合にも形成されます。
川端康成は両親の結核のため、生後一歳ごろから親戚の家にあずけられ、二歳で孤児となってからは祖母の異常な過保護のもとで育てられました。
体が弱いということで、他の子どもと遊ぶことさえ禁じられました。
七歳で祖母を失ってからは、十四歳まで盲目の祖父の面倒をみることになります。
こうした境遇で育った彼は、この禁止令からの解放を強い憧景として繰り返し作品に描いています。
<私はかつて子ども心というものを持ったことがないような気がいたします。
ですから子どもと遊ぶことは、私のひそかな天国であります。
けれども子どもと遊んでいるところを人に見つけられると、なにか物を盗んでいるところを人に見つけられたように恥じ入るのであります。>(『父母への手紙』。前出『川端康成<作家の自伝15>』より)
成長してはいけない
この禁止令に縛られた心理状態は、一つは、自分が成長して自立していくことが、親への反逆のように感じられる場合です。
もう一つの現れ方は、大人になることが恐いという、いわゆるピーターパン・シンドロームです。
思春期から青年期には、一般に親の権威から離れて、仲間集団に忠誠を尽くすようになります。
ところが、この禁止令にとらわれた人は自分の力への自信がつくられないために、親の権威への服従が持続してしまうのです。
この禁止令の強い人は、子どもの時には親の権威にしたがっているので良い子どもであり、親子関係は大変順調です。
自立が課題となる時期になって初めて問題が出現します。
したがって、思春期以降に問題が生じるのです。
この禁止令は、自分の性的成熟を否定する心理傾向として現れることもあります。
たとえば、女性の場合、化粧することに罪悪感を持ってしまったり、装飾品を身につけることに抵抗感を持ってしまうなどです。
自分の身体の成熟を否定しようとすることもあります。
ある種の拒食症に、この心理が見られます。
食べることを拒否することにより、成熟した女性の肉体になることを拒否する心理です。
ここには、自分が成熟することを拒否すると同時に、成熟した女性である母親を拒否するという心理も同居しています。
この禁止令はまた、恋愛や結婚を妨害することがあります。
恋愛や結婚は、親以外の存在に愛情を向けることです。
このために、親への裏切りのように感じられてしまうのです。
留年する学生にも、しばしばこの禁止令が認められます。
彼らはこの禁止令にとらわれてきたために、社会に出てやっていく自信が育っていないのです。
動物を見れば分かるように、親の役目とは、子どもの自立能力を育て、巣(家)から送り出してやることです。
ところが、親は自立能力を育てることを妨げてしまうことがあるのです。
自立よりもむしろ、親は無意識に服従を歓迎してしまう心理を持っているのです。
「言うことをきくこと」「素直であること」「強情を張らないこと」などを求めるのは、子どもに自立ではなく服従を求めていることです。
実際親の未熟な心は、子ども無力さを歓迎してしまう危険があるのです。
それは、弱い者から依存されることが、親の自己存在感を満足させてくれるからです。
次のお話のストーリーを思い出してみてください。
「三匹の子豚」「狼と七匹の子羊」「シンデレラ」-いずれも、一番下の子が好ましく描かれています。
旧約聖書のカインとアベルの物語もそうでした。
シェークスピアの「リア王」でも、いちばん下の娘がいちばん親思いに描かれています。
末っ子はいちばん年が小さいので、いちばん最後まで親に依存する子どもです。
いちばん下の子が好ましく描かれるこの一貫した傾向は、意識せずに親の心理を反映してしまったのです。
じっさい子どもは、本能的に親の子の心理を見抜いています。
だから、大部分の子どもや青年は、家ではより幼い自分を演じているのです。
能力を実際以下に見せることで自我を守る術は、とくに女性では少なくない人に身についています。
自分の頼りなさを強調して男性の援助を引き出し、相手の存在価値を高めてあげることで相手に気に入られ、安全を得ようとする行動がこれにあたります。
この禁止令にとらわれると、社会で出会ういろいろな問題を自分で解決し、困難を乗り越えていく力と自信がつきません。
このために、青年期になって困難を感じたり、破綻することになるのです。
成功してはいけない
人が成功を求めるのは当たり前のことのように思われます。
しかし、成功をおそれる心理を持ってしまう人もいるのです。
こうした人は、じっさいに成功しそうになると不安が強くなり、成功から逃げ出してしまいます。
杉田峰康氏によれば、入学試験で受験番号を書き忘れる行為などにも、この心理が隠されていることがあるそうです。
ある学生は、「『あなたは大事なところで失敗するから注意しなけりゃダメよ』と幼稚園のときに園長先生に言われた言葉が、なにかした拍子に思い出されて、いまでも委縮してしまう」と語っていました。
また別な学生は、自分だけで完全にやり遂げてしまうと、母親が自分を援助できなくて不満げである様子を子ども心に感じとっていたために、「なにかすると、どこか一点だけは失敗をつくってしまう」と語っていました。
この禁止令にとらわれると、たとえ社会的に見てどんなに成功しても、親を裏切ったという無意識の感覚のために、常に罪責感に悩まされることになります。
あるいは、地位のある人が破廉恥な行為で失脚してしまうなど、成功を帳消しにしてしまうような行動を、じっさいに引き起こしてしまうことがあります。
この禁止令は、優れた親から「ふがいない子ども」として見られることで形成されることもあります。
しかし、この禁止令がもっとも強く形成されるのは、親が子どもに凌駕されることでメンツを失うことをおそれる場合です。
また、大変で気の良い中学生がいました。
本人は普通に進学して大学まで進みたい希望を持っていました。
家も裕福で、学費に困るというような状況ではありませんでした。
ところが親は、自分が卒業した商業高校へ行かせ、高卒で就職させたのです。
実行してはいけない
なにも自分でする気にならない、自分で決めて自分で行動するということができない、行動しても不全感にとらわれる―こうした場合に、この禁止令が働いています。
グールディングらは、恐怖心の強い親によってつくられると述べています。
こうした親は過保護になって、しじゅう「危ないから」と禁止するからです。
また、少し大きくなっても、「よく考えてからしなさい」と、実質的にすすんで行動することをおさえてしまうからです。
杉田峰康氏によれば、親が「しない」でなく「できない」を多用するとき、この禁止令ができます。
たとえば「忙しくて××できないんだよ」などと親がしじゅう言う場合です。
また、さらに、幼児期から完全を求める親の養育が関係すると考えています。
子どもはなにをやっても、大人の目から見たら不完全にしかできません。
この不出来の部分にしか目がいかない親がいます。
「これではだめでしょ。こうでしょ」とか、「ほら、ここが抜けてる」など。
こうされると、子どもは自分を守るために、「なにもしない」ということで身をまもろうとするようになるのです。
重要な人物になってはいけない
みなが認める力があるのにリーダー的役割を担わない人、リーダー的な役に付くと必要以上に不安になってしまう人―こうした人は、この禁止令に束縛されている人です。
縁の下の力持ちの約に徹したり、場合によっては使いっ走りにされてしまうこともあります。
人から注目を浴びることを避けたり、恐いと感じたりする心理もこれによります。
この禁止令は、「子どもは黙っていなさい」とか、親の小間使いを強制されて育つなど、軽んじられて育つことによって形成されます。
また、「おまえはろくな者じゃないな」「ダメな奴」などと、おとしめられて育つことによっても形成されます。
さらに、うだつのあがらない父親とか、おどおどとした母親との同一化により、形成される場合もあります。
みんなの仲間入りをしてはいけない
人のなかにいることに困難を感じる人は、多かれ少なかれこの禁止令にとらわれています。
この禁止令にとらわれた人は、なにか口実を設けて集団に入ることを拒否したりします。
そして、しばしば集団のなかにいる他の人を見下しながら、同時に集団のなかで楽しくいられる彼らをうらやましがります。
この禁止令は、次のようなことでつくられます。
一つは、親の過干渉です。
子どもが外で仲間と遊んでいるよりも、家で一人遊びをしているほうが、親の目が行き届くので安心です。
このために、意識せずに仲間との交流を制限してしまうのです。
第二に、「あんな子と遊んではいけない」とか、「うちは違います」など、エリート意識を強調することで形成されることがあります。
中学や高校が越境入学であった人に大学での適応困難な人が多い、と指摘する臨床心理学者もいます。
第三に、深い葛藤を内在している家庭で育った場合や、実親でない人に育てられた場合に形成されがちです。
こうした場合、親のなにか分からない態度の不自然さが、「自分は普通ではない」と子どもに感じさせ、みんなと同じようにいることに不安感を持ってしまうのです。
たとえば父親に愛人がいて、そのことには触れないで表面上とりつくろった生活が続いている家庭では、「お父さん、どこに行ったの?」とか「何時ごろ帰ってくるの?」など、父親について問うことが禁句になります。
このために、自由な話題を恐れたり、そうした話題が出るかもしれない友達関係をおそれる、という心理が形成されるのです。
愛してはいけない、信用してはいけない
この禁止令にとらわれると、本当の愛など存在しない、愛など嘘っぽいと感じます。
愛とは移ろいやすく、もろく、早晩壊れるものと感じられます。
友達もやがて去りゆくものと感じられます。
このために、心から許し合って付き合うことができません。
表面的な付き合いにとどめます。
このために、心から許し合って付き合うことができません。
表面的な付き合いにとどめます。
寄せられる好意には下心があるように感じてしまいます。
この禁止令は、親しい愛情表現のみられない家庭で育つことにより、形成されます。
こうした家庭では、素直な愛情表現が傷つけられがちです。
あるいは、気分屋の親に育てられることで形成されることもあります。
気分の良いときは猫かわいがりにかわいがられ、気分の悪いときには見向きもされない。
こうした状態で育ったら、相手を信用して、心から愛するというようなことは危なくてできなくなるのは当然です。
さらに、親が離婚するなどにより、それまで注がれていた愛情が奪われてしまった体験によっても形成されることがあります。
先に、男性不信が植え付けられた女性の事例をあげました。
彼女は、母親により、男性を愛することへの禁止令がインプットされたのです。
このように、母親ないし父親が愛情を持てず、その不信感をストレートに子どもに吹き込むことによっても形成されます。
さらに母親の無意識の嫉妬が、この禁止令をつくることがあります。
たとえば、祖父母と同居している場合、子どもが祖父母と仲良くすることで祖父母に子どもをとられたかのような心理が起こり、母親は無意識のうちに気分を害します。
あるいは、夫との仲がうまくいかないとき、子どもが父親と親しくすると母親が気分を害してしまうことがあります。
こうしたことが繰り返されると、子どもに他の人と親しくなることに対して得体の知れない不安が形成されてしまうのです。
分裂病の家族に特徴的なコミュニケーションの様式を分析して、G・ベイトソンらはダブル・バインドという概念を提出しました。
これは、子どもが相反する二つの要請に応えることが求められながら、どちらに応えようとも片方の要請を満足することができない、そのため救いのない不安を背負わされる―そんな状況を表現する概念です。
たとえば次のような場合です。
母親が「子どもなんだから外で遊んできなさい」と言います。
しかし子どもは、外で遊ぶことを明らかに母親が心配していることを感じとっています。
遊びに行かないと、遊んできて欲しいという母親の要望に応えられません。
かといって遊びに行けば、母親を心配させたという罪悪感から免れられません。
あるいは「年頃なのだから異性の友達の一人くらいつくりなさい」と口では言いながら、いざ異性の友達から電話がかかってくると、聞き耳を立て、とがめだてするような口調になる親も同様です。
こうした状況では、他の人の言葉はそのまま信用できないということになります。
また、親のみでなく、他の人との感情的な交流も危険でできなくなってしまいます。
健康であってはいけない
いつでも身体のどこかが調子悪い人、心気症の人、病気と縁の切れない人などは、この禁止令にとらわれている可能性があります。
病気になることがストロークを受ける条件であるような環境で育ってきた場合に、この禁止令が形成されます。
たとえば、共働きでいつも忙しい母親が、病気になったときだけは会社を休んで添寝してくれたとか、あるいは、弟や妹が生まれ、両親の関心がそちらに移ってしまったが、病気になったときだけは両親とも自分に関心を向けてくれたなどです。
また家族心理学では、葛藤を抱えた家族が家族の誰かを犠牲者にすることで表面上安定が保たれていく、ということがあることを明らかにしています。
たとえば同居する祖父母と折り合いの悪い親が、病弱な子どもに付き添っているために、祖父母とぶつかる機会が減り、決定的な破綻を免れているなどです。
この子は、病気になることによって家族を救っているのです。
考えてはいけない
「考えると頭が痛くなる」とか、衝動的に行動する傾向などに、この禁止令が働いています。
自分の人生を自分で選択してつくっていくという姿勢ではなく、ただそのときどきの流れに任せてしまうという生き方も、この禁止令の現れです。
この禁止令が極端に形成されると、自分の行動の結末を考えないために犯罪者になったり、著しく常識を欠いた人になります。
この禁止令は、「黙って言うことを聞きなさい」「言い訳するな」「自分で勝手に決めるな」「ぼさっとしていないで、言われたらさっさとやること」など、子どもが自分で考えることをおさえつける養育環境で形成されます。
子どもに決定権を与えないことが、もっともこの禁止令を強く埋め込むことになるのです。
むろん「お馬鹿さん」とか「能無し」など、子どもの考える能力を否定するような養育環境もこれをつくります。
自然に感じてはいけない
「自分の好きなものが分からない」「したいことがない」「なんでもいい」「どちらでもいい」などと言う表現に、この禁止令の現れを見ることができます。
また、面白いとか、楽しい、うれしいなど、実感をもって感じられない場合も、この禁止令が働いていることがあります。
極端な場合には、おなかがすいているとか、怒っている、などの身体感覚さえも適切に感じ取れなくなってしまいます。
これは、幼児期の自然な姿をおさえつける養育に起源があります。
とりわけ、幼すぎる時期からのしつけの徹底が影響します。
しつけとは子ども本人の感じ方には価値がなく、養育者の感じ方に価値を置くことを求めるものだからです。