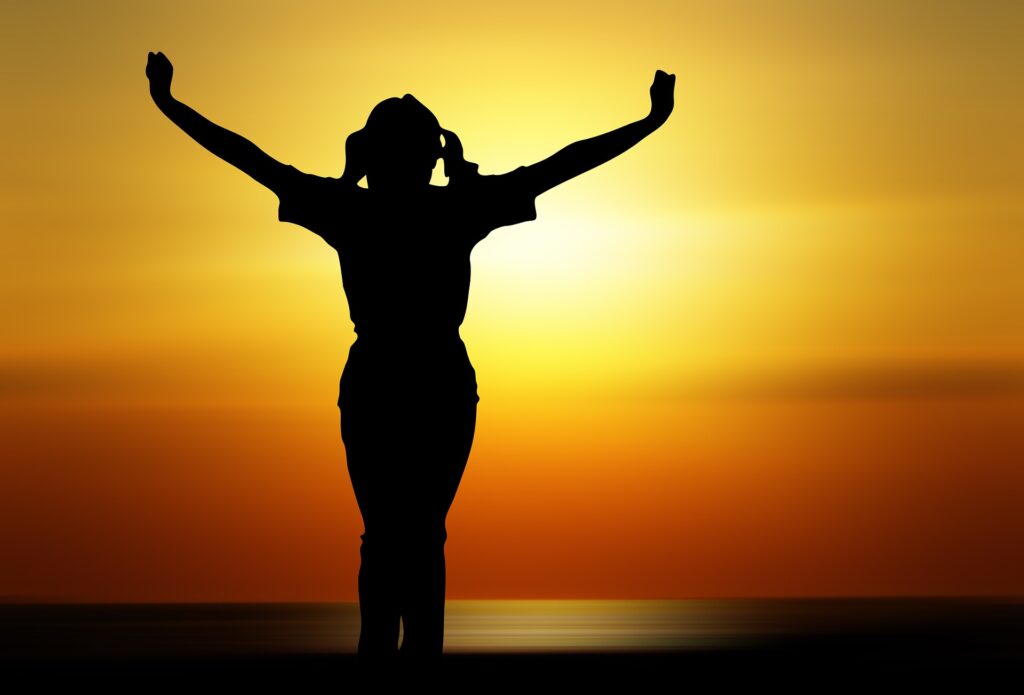利己主義者に対する悔しい心理とは
悔しさは利己主義者とは対極にある
悔しくて、悔しくて眠れない夜がある。
なかなか寝付けない。
しつこい嫌がらせをされて気がおかしくなりそうになる。
事実無根の悪口をいいふらす、どうしても許せない人がいる。
他のことに打ち込んで忘れようとしてもどうしても忘れられない。
心がその人にとらわれてしまっている。
こうして人間関係の中でいやされない心の傷を負って人間として破滅していく人はたくさんいる。
なぜいつもこうして苦しみ悩んでいる人がいるのか?
シーベリーは悩みの原因は「自分が自分自身ではなくなったからだ」という。
自分自身であり得ないなら悪魔になったほうがましだともいう。
過激なことをいうと思うかもしれないが、同じ趣旨のことは他の偉人たちもいっている。
「自分自身であろうと決意することは、人間のほんとうの使命である」
自分自身であろうと決意することでなにが生まれるか。
「喉に刺さった魚の骨」が取れることである。
それは、人からどう思われるかが怖くなくなることである。
そして安らぎから前向きに生きるエネルギーが生まれる。
したがって心の傷から回復していく。
年月はかかるかもしれないが、やがて心底元気になる。
自分自身であろうと繰り返し決意することで、なんとか神経質をまぬがれて、ほんとうにエネルギッシュになる。
憂うつになっている人が、かすかに光を見出す。
「人は幸せになるために生きているのではない。自らの運命を成就するために生きているのだ」
これはロマン・ローランの小説『ジャン・クリストフ』の中の言葉である。
人は「自らの運命を成就する」と決意する結果として幸せになる。
幸せになることが絶対の優先事項だとすると、絶望する人は多い。
幸せにはなれないから最後は自暴自棄になる。
幸せになることが、絶対の優先事項だと、どうしても「これがほしい、あれがほしい」という「求める心」だけになってしまう。
人生における絶対の優先事項は「自分自身になること」である。
自分自身である人が求めるものと、自分自身でない人が求めるものとはまったく違う。
とにかく自分が自分であることが最大の使命である。
同時にそれが悶絶の苦しみから解放される方法でもある。
したがって親子であろうと、配偶者であろうと、誰であろうと、私が私自身になることを許さない人とは別れることである。
これが「自分の人生を無意味にしない絶対の法則」である。
なかには、心はものすごく欲求不満で、人間として破綻しかかっているのにもかかわらず、社会的にはよく適応している人がいる。
肉体的にいえば隠れ肥満である。
外からはわからない。
やがて底知れぬ沼に落ち込んでいく。
自分自身になろうとすることで自己肯定感と成長への意欲が生まれる。
心理学者シーベリーの本の中に、直訳すると「利己主義の方法」というタイトルの本がある。
シーベリーのいう「利己主義の方法」とは、「自分を大切にする方法」である。
人から気に入られたいという、とらわれの感情から解放される方法である。
自分を大切にする人にしか他人を大切にすることはできない。
人は自分を受け入れる程度にしか、他人を受け入れられない。
自分を愛することなしに他人を愛することはできない。
「他人への義務は、自分ができるかぎり生きる歓びに満ちている存在であることによってのみ果たせるのです」
シーベリーがいわんとしている利己主義ということの意味は、この言葉を読めば理解できる。
身勝手ということではない。
自己中心性的ということではない。
ほんとうに他者と心が触れ合えるということである。
だからこそ生きるエネルギーがわいてくる。
これがすべての人生の諸問題の解決の根本である。
人と真のコミュニケーションをすることが、人生の諸問題を解決する方法である。
意志のある人は、相手の話を聞くが、迎合しない。
これが攻撃的不安のない人である。
意志のない人は、相手の話を聞かないで、迎合する。
これが攻撃的不安に悩まされている人である。
ある人は「真実とはなにか」と訪ねて世界中を歩いた。
アメリカ、アジア、ヨーロッパ、キリスト教圏からイスラム圏まで探し求めた。
ヒマラヤの麓まで行った。
そして真実があったのは自分の心の中だった。
利己主義という言葉が誤解を招くが、シーベリーのいう利己主義は健康的利己主義である。
健康的利己主義は自分本位主義である。
自己中心性ではない。
悔しい人が健康的利己主義になるには
無理をすることの弊害
フロムは神経質的非利己主義という言葉を使っているが、それは神経質の症状だという。
「あなたさえよければ私はそれでいいの」というようなことをいう人々の症状である。
このようなことをいう人は隠された憎しみに満たされている。
だからこのようなことをいう母親は子どもの心をおかしくする。
だからこのようなことをいう女は男をおかしくする。
この言葉に引っかかって生涯を棒に振った男や女のなんと多いことか。
それを聞いたとき、こんなうまい話はないと男や女は思った。
そのずるさに引っかかって男も女も、生涯を棒に振ったのである。
神経質的非利己主義の最大の問題は生きるエネルギーを失っていくことである。
努力して消耗するだけである。
根は利己主義者なのに無理して非利己主義的に振る舞うから疲れる。
心の底では憎しみが生まれる。
生きるエネルギーを失えば、他人のお荷物になるだけである。
フロムのいう神経質的非利己主義には愛がない。
常に相手から見返りを求めている。
しかし求めたものは返って来ない。
悔しい。
人は無利して親切をすると、相手を嫌いになる。
したくないことをしたのだからおもしろくない。
悔しい。
しかし「悔しい、嫌い」という感情を直接的に表現できない。
悔しい気持ちをじっとこらえて我慢している。
そこで憂うつになる。
そうなれば生きていても毎日が楽しくない。
その嫌いとか悔しいという感情を間接的に表現して、たとえば毎日みじめさを誇示する。
自分が毎日いかに苦労しているかを人に話さないではいられない。
ほんとうに「相手のために」という相手への愛情から親切をすれば、ますます相手が好きになる。
つまり自分がした行為が、ほんとうの親切であるか、それとも神経質的非利己主義の親切であるかは、その行動のあとのその人の気持ちを見ればわかる。
エネルギッシュになるか、悔しくて我慢して憂うつになるか。
あることで相手にゆずる。
ゆずるということは大切な徳である。
その行為のあとのその人の気持ちで、その行為が本物か偽物かがわかる。
嫌われるのが怖くてゆずる人がいる。
期待したものは返って来ない。
悔しい。
その結果相手が嫌いになる。
嫌いな感情を表現できなくて憂うつになる。
こうして神経質的利己主義は、結果として「自己の内なる力」を弱化する。
だからフロムが指摘するように神経質的非利己主義に関連した症状は、疲労、働くことへの無能力、愛の関係の失敗というような症状だという。
そして神経質的非利己主義の人はその症状にも悩んでいる。
要するに悔しくて、悔しくて悩んでいる。
彼らは努力して消耗する。
好かれるための自己執着的対人配慮は現代人の特徴の一つである。
神経質的非利己主義が、毒のある非生産的いい人であるとすれば、人も自分も励ます生産的いい人は健康的利己主義である。
神経質を判断するのは、行動ではなく、その行動の動機である。
他人に迎合するための非利己主義。
それは「他者を愛するため」ではない。
神経質的非利己主義とは自分の弱さを合理化していることである。
ほんとうは自分の依存心から離婚できない。
評判が気になるから離婚できない。
利己主義者と思われることの恐怖から離婚できない。
それなのに「子どものために離婚しない」という。
こうした場合、母親は子どもが嫌いになる。
そして自分はよい母親と思っている。
ところで利己主義、悲観主義と関係なく自分が自分ではないところで安住しようとする人がいる。
「あたかも自己喪失の状態にのみ安住の地があるかのように」生きている人がいる。
ありのままの自分には価値がないと感じている。
自分への失望感である。
その失望感が間違いと本人が気がつくこともある。
自分ではなく、親の側の劣等感が原因だと気がつくことがある。
治癒には一番大切な真実とはないかを突き止めること。
「自分自身にかけられている否定的な暗示に気がつくことから、治癒は始まるのです」
「汝のなるべきものになれ」というシーベリーの言葉で、迷いを吹っ切れば、人がどう思おうと関係なくなる。
人に低く評価されようが、人から拒絶されようが、気持ちの動揺はなくなる。
そこで悔しい気持ちと縁を切れる。
そして無理して好かれようとした人々と別れて生きはじめることで、自分の人生に意味が吹き込まれる。
自分自身になることを放棄すれば、毎年ジャンボ宝くじに当たっても確実に人間として破滅する。
自分自身になることを放棄して自分に絶望するか、自分自身になることで自分に誇りをもつか。
それは自分が決めることである。
ロロ・メイは「意志は対立から生まれる」という。
関連記事
人付き合いが怖いを克服する方法
自分を信じられないと他人も信じられない
「いわなくてもわかってよ」は甘え
心理的に孤立してくるということは、このように自分と他人の違いがわかってくるということでもある。
同僚とさえ同じように生きようとするのではない。
自分がわかり同僚がわかり、そのお互いの違いを理解したうえで、つきあっていくということである。
お互いの違いがわかってくるということは、相手にどこまで要求でき、どこから先は要求してはいけないかということがわかってくることでもある。
つまり、どこから先は自分自身に頼らなければ生きていけないのかということがわかってくる。
あるいは「そこまで自分のことをわかってくれというのは甘えだ」ということがわかってくることでもある。
それはまた逆に言えば、「ここまでわかってもらう努力をしよう」ということでもある。
心理的に独立していないと、いつも「私のこの行動はこのように解釈してほしい」という押し付けがましさが出る。
「このように解釈してほしい」ということの裏には、「だから私に対してこういうように対応してほしい」という欲求や要求がある。
だからこそ、心理的に独立していない人との付き合いは重苦しいのである。
なにもいわなくても、要求がましく感じられて自由ではない。
なんとなく束縛感がある。
つきあう側に束縛感があるように、心理的に独立していない人にも自由がない。
自分のことをこう解釈し、こうあつかってほしいという欲求があると、その相手に迎合していかざるを得なくなるからである。
単純にいえば、保護を求めている限り、心理的に自由にはなれない。
保護を必要としている以上、相手のご機嫌をとらざるを得ない。
上司や同僚に保護を求めていたり、自分をこのように認めてほしいという欲求をもっていると、淡々と生きるわけにはいかない。
なにかにつけて不満になる。
『「うらみ」の心理』(郷古英男著、大日本図書)という本では、「うらみ」のもっとも本質的な要素として、次の三つを挙げている。
- 相手の仕打ちに不満をもつ。
- 表立ってやり返せない。
- その相手の気持ちを推量できず、いつまでも執着し、じっと相手の本心や出方をうかがう。
たしかにこのとおりなのであるが、これは当の本人の主観的な心理的過程である。
まず相手の仕打ちに不満をもつのは、うらみとしては当然である。
ただこのとき、第三者から見てもその仕打ちが不当であるときと、そうでないときとがあろう。
当の本人が心理的に独立できておらず、自分のことをこう解釈し、このように認めてほしいというように相手が解釈し、認めないとき、相手の仕打ちを不当と勝手に解釈することがある。
そして敏感性性格で傷つけながらも、表立ってやり返せないでいる。
それだけに、いつになってもその不満や怒りや憎しみがはけずに、うらみとなって心の中にとどまる。
かくて上司や同僚と抜きさしならぬほど感情的にからんでいってしまう。
嫁と姑、隣近所の奥さん同士についても同じことである。
表立ってやり返せないから、陰にまわって足をひっぱるということになる。
さわやかに生きるために、心理的独立というものがどれくらい大切かということである。
「私は反対です」とはっきり言えた日
相手のいうことを聞いて、そのとおりにして相手から保護されて生きることはやさしい。
しかしこのような生き方をしていると、いつまでたっても心理的に独立することはできない。
また相手の言いなりになって生きたからといって、相手はこちらを尊敬するわけでも、重んじてくれるわけでもない。
甘く見られる、なめられるだけである。
「人を見る」ということが、この社会の中で快適に生きていくうえには、どうしても必要なことである。
この世の中の人は、敏感性性格の人が考えるよりはるかに心優しい。
また逆に、敏感性性格の人が考えるよりはるかに卑怯である。
というのは、敏感性性格の人は、人を皆同じに見てしまう傾向がある。
だから自分に対して好意的な人も、自分を利用しようとするずるい人も、同じに対応する。
そのように同じに見えてきてしまうのである。
さて、いろいろ長々と相手のいうことを真に受けすぎるということを記してきたが、次に大切なことは、「自分が」このように思う、「自分は」こう感じるというように、「自分」というものを他人に示すことを避けてはならないということである。
「だいたいこの会社に勤めている者なら」とか、「たぶん昭和生まれの者は」とか、「多くの男性は」とか、自分の意思を一般化して表示する。
だいたい「自分が」反対であっても弱い人間は、「彼も反対のようでした」というような言い方をする。
このように自分の意思をはっきりと表示することをいつも避けていると、いつのまにか自分の意思そのものがはっきりしなくなってきてしまう。
「みんな、これはほしいんじゃない」といった言い方をよくする。
決して「私はほしい」とはいわない。
このように自分の意思や要求をいつも一般化していると、「どれがほしい?」と聞かれて、「どれでもいい」というようになってきてしまう。
本当にどれでもよくなってしまうのである。
「どこのレストランに行こうか?」というとき、「彼がどこそこのレストランはおいしいといっていたよ」となってしまう。
自分の意思や要求や望みを一般化しないときは、自分以外の第三者を通してそれを表示する。
今も記した通り、「自分が」反対でも、まず「彼が」反対の意見だという。
そして「自分は」といわずに、全体が自分の望むように反対になることを期待する。
たとえ「彼が」反対でも、「私は」反対だといって、それを支持するものとして「彼も」というのはいいだろう。
しかし「私は」をぬかして「彼が」だけ述べて、その集団の意見がそのようになったのを「彼の」責任にするというのは弱虫にすぎる。
このような生き方をしていると、いつのまにか気力のおとろえた人間になっていくし、さっぱりした人生を送ることはできないだろう。
いつも誰かを恨んでいるようなことになる。
ことに人事の昇格などについては、人は問題になっている人に憎まれたくないということではっきりと自分の意見を言わない。
言わないけれど、「彼が昇格になるのはおかしい」と思ってはいる。
「それだけの業績をあげていない」と思ってはいる。
しかし公の会議でそれをいえば、やがてそれがその人に通じて憎まれることになる。
そこで憎まれたくないから自分の意見は公には言わないで、あとは陰口をいうことになる。
日本の社会でこれほどまでに陰口が多いのは、人々が弱いからである。
「だいたい女なら」「彼が」「たぶんあの人も」というような言い方でしか、自分の意思を人前でいえないから陰口が多いのである。
自分の意思を表示し、その意思を通すということは、自分が責任をとるということでもある。
それは怖い。
しかし自分の意思を重要な局面ではっきりと述べて、そのとおりに動かしたとき、それまでと世界は違って映ってくる。
いや自分も違ってくるのがわかる。
自分の内面もきしみをたてて変化していくのがわかる。
自分の意思をはっきりと表示しはじめたとき、それまでいかに自分が弱い自分を守るためにものすごい鎧をつけていたかがわかる。
長いこと弱さを武器にして生きていると、自分は弱くなければ生きられないと心の底で信じだす。
自分の弱さを誇示し、従順であることを示し、それによって保護されようとする。
弱くなければ生きられないという思い込みを捨てることである。
弱さを誇示して他人の同情を集め、責任をとらないで生きていこうと長いことしてくると、それ以外には生きる方法はないように思えてくる。
人生と自分に対する思い込みを捨てること。
強くなっても生きられるし、自分は強くなれるのだということである。
弱いままで生きるということは、いつも誰かにべったりとよりかかって心理的にも生活面でも面倒をみてもらおうということであろう。
そして何度もいうように、それが思うようにいかなければ相手をうらむということになる。
同情を求めて生き、期待した同情が手にいらなければうらむ。
交流分析のムリエル・ジェームスのいうごとく、うらむということは相手に罪悪感を抱けということであるから、この場合もなお受け身のままで自分を救おうということである。
最後まで、まわりの気持ちで自分の人生の苦しみをとりのぞいてもらおうということであろう。
相手が罪悪感を抱いて自分への態度を変えてくれるのを待っているのである。
はじめから終わりまで、他人に頼った生き方である。
そういった意味でも心理的に独立し、責任は自分で取るということは健康的利己主義になる。
まとめ
利己主義の方法とは自分を大切にする方法である。
しかし、根は利己主義者なのに、非利己主義者のように振る舞うから疲れてしまう人がいる。
恨みから元気になろうとすることは受け身のままで自分を救おうとすることである。
人も自分も励ます生産的いい人は健康的利己主義の人。
楽に人付き合いするには心理的独立が大切になる。