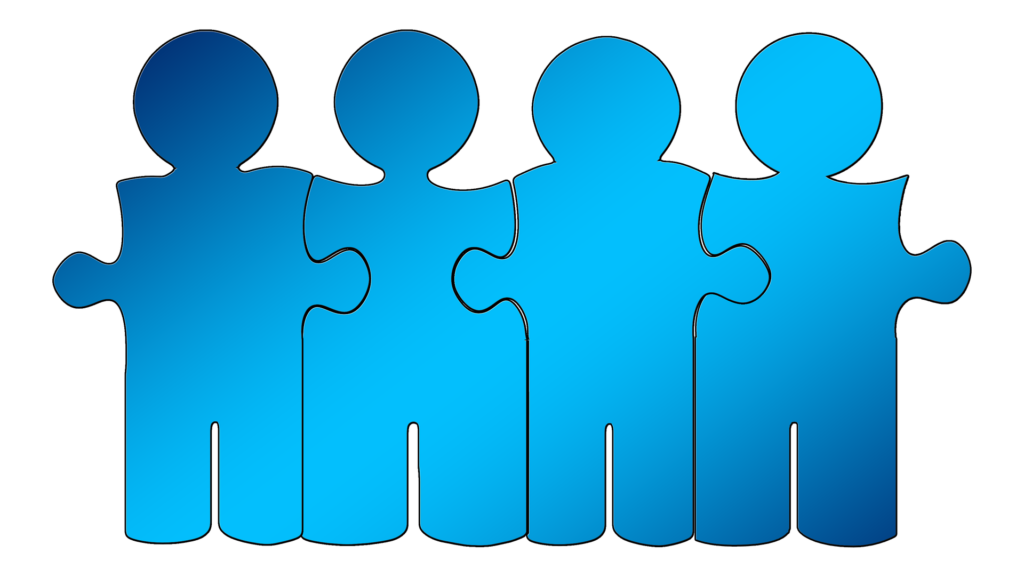心の傷と身体を傷つけること
自分の「身体を傷つけること」と、「心が傷つくこと」とは関係があるのでしょうか?
一般的には、心の傷つきのために身体を傷つけることに向かう、ということができます。
そして、心の傷が癒されると自傷行為もおさまっていきます。
若い女性の間で、手首を切るリストカットが広がっています。
大学に出てこない友人を心配してアパートを訪ねたある女子学生は、その友人の部屋の壁やカーテンのほうぼうに血が染み込んでいるのを見て驚いた、と語っています。
手の甲を切ったり、耳を傷つける人もいます。
タバコの火を手の甲に押し付けたり、太ももに焼き印を押す若者もいます。
リストカットする人は、血を見ることや傷の痛みで癒されると言います。
「血が出るのを見ていると、生きていると感じることができる」
「スッとして、気持ちが落ち着く」
「自分を取り戻せる感じがする」
などと言うのです。
自傷行為は、一種の自我の防衛機制としてとらえることができます。
関連記事
心の傷を受けた人は、自分でそれに取り組もうとしても、取り組み方が分かりません。
母親が愛情とともに傷を与える存在ならば、憎しみの感情を誰に向ければよいでしょうか。
また、対象が分かっているとしても、自分がどうやっても母親を変えることができないならば、ただ耐えるしか方法はありません。
それよりは、自分の身体の傷として取り組む方が容易です。
自分の苦しみ、傷つきは、目に見えるこの身体の傷だということであれば、気持ちは楽になります。
自傷行為はまた、自罰による救いという機能を果たしている場合もあります。
自分の心の中に、許されない敵意、憎しみ、嫉妬、願望等々が存在します。
自らを痛めつけることで、こうした自分の心が許されると感じるのです。
出血することで、心の汚れが流出し、浄化されると感じるのです。
関連記事
自傷行為は、ほとんどの場合、死のうとして行うわけではありません。
自分を喪失することを防いだり、心の高ぶりによる不安を抑えるために傷つけるのです。
しかし、一方で、自傷行為がエスカレートしてしまい、「これから自分はどうなってしまうのだろう」という自分でコントロールできなくなる恐怖をも感じています。
ですから、ぜったいに誰にも知られてはいけない秘密だと思いながら、だれかに知ってもらいたい、苦しさを分かってもらいたい、と願っているのが大部分の人の姿です。
心の傷つきは、身体の一部を傷つける行為に向かうだけではありません。
援助交際など、身体をお金で売り渡すことで傷つける場合もあります。
自暴自棄的生活やアルコール依存症、薬物依存症など、人生そのものを傷つけてしまう方向に向かう場合もあります。
関連記事
愛情の問題でなく
家族内における外傷体験で最大のものは、母親との愛情豊かな交流の失敗という体験です。
母親の愛情を信じ切れないという体験です。
この記憶が、のちのちまでも親に対するわだかまりの原因になっている人が少なからずいます。
しかし、実際に親に愛情が欠如しているというのは、ごくごく例外的な事例です。
もちろん、親は子どもに対して怒りを感じることがあるし、時には憎しみの感情が湧き起ることもあります。
しかし、基本的には子どもを愛しているというのが通常の姿です。
むしろ愛情の問題ではなく、親と子の性格的なすれ違いに原因があることが多いのです。
関連記事
一般に親が性格的な歪みを持つほど、許容性に欠け、子どもの感覚、感情、欲求を切り捨ててしまいがちです。
親自身の素質と生育歴により、親はある程度の性格的な偏りを避けることはできません。
子どもには子どもの素質があり、それをもとに親に適応しようとするのですが、親の性格が子ども自身の素質とひどく反したり、子どもが適応するのに困難なほどの食い違いがあると、子どもは愛されていないと感じる体験をするのです。
親と子供との間のこうした葛藤は、性格的な食い違いが大きいほど、大きくなります。
そして、親にとって、食い違いの大きな子どもと小さな子どもとで、愛情を持つ容易さに違いがあることも確かです。
「お兄ちゃんのことはスッと分かったのに、あの子のことはどうしても理解できない」
「下の子はいいのだけれど、上の子が学校から帰ってくる時間になると、気が重くなってしまう」
そんなふうに語る母親がいることも事実です。
しかし、多かれ少なかれこうした食い違いは避けることはできないものであり、問題は食い違いそれ自体でなく、その際の子どもに対する親の対応のあり方なのだと考えられます。
子どもの率直な感情や意思表示を許容し、子どもが感じていること、望んでいること、訴えていることを理解しようとする姿勢を持った親であれば、そうした食い違いが、親の愛に対する子どもの疑惑につながることはないと思われます。
子どもが困難にぶつかったとき、子どもに癒しを与えることができる最大の存在は母親であります。
子どもが父親とぶつかったとき、祖父母とぶつかったとき、友達とぶつかったとき、子どもの言い分を聞いて、慰め、抱きしめてあげられるのは母親であります。
母親のあたたかでやわらかい胸に抱きとめられた時、胎内にいたときの感覚を再現するかのような安らぎの感覚を体験することで、癒されるのです。
こうした機能を果たすべき母親が、外傷体験を与える人であったならば、その影響の大きさは容易に推しはかることができるでしょう。
関連記事
自分の人生は自分しか作れない
米国では、幼いときに親から受けた性的虐待について、子どもが親を裁判で訴えるということが起きています。
幼い時の性的虐待の記憶は抑圧され、記憶から消されていたのですが、精神科医やカウンセラーの治療を受けて、それが精神的疾患の源になっているということが分かったというのです。
子どもは、この抑圧していた記憶が自分を苦しめているのだとして、慰謝料を求めて親を訴えるのです。
これについて、疑問を呈する研究者がいます。
そのような大きな影響を与える体験を忘れているなどということが果たしてあるのだろうか。
じっさいには、それは偽の記憶ではないのか。
治療やカウンセリング場面で、被暗示性が高まっている状態で治療者から注入され、あたかもそれえをじっさいに体験したかのように思い込むということではないのか。
こうした疑問です。
実際、実験によれば、そうした偽体験記憶を作り出すことは意外に簡単にできるということが分かってきました。
しかし、こうした否定派には、現実の臨床活動をしていない人が多いそうです。
そうした人々の苦しみをまぢかに見て、治療にあたっている人の方が、親の性的虐待を事実として認める傾向が強いというのです。
実は、幼児期に性的いたずらを受けたと話すことは事実なのか、それとも偽りの記憶なのかという問題は、フロイトをも悩ませた古くからの問題です。
関連記事
フロイトの患者はそうした訴えをすることが多かったのですが、彼は最初これを事実と受け取って、そうした体験がヒステリー症状の基礎になっていると解釈しました。
ところが、最終的には、これは子どもの空想のなせることと理解し、それゆえに、エディプス・コンプレックスという、もっぱら子どもの心の中での出来事に原因を求める方向にいったのです。
偽の記憶か、事実の記憶か。
いずれにせよ、親との関係は、逃れることができません。
傷つける相手に依存せざるをえないこと。
愛してもらわなければならないこと。
愛さなければならないこと。
複雑な親の心を未熟な心で解釈しなければならないこと。
こうしたことで、幼児期の体験が大きな影響を残すことは確かです。
しかし、親の責任をいくら追及しても、自分が幸福になれるわけではありません。
自分のこの苦しみは、自分だけの責任ではない。
自分のこの有様は自分だけの責任ではない。
そう思えるだけで、少しは気持ちが楽になります。
それにとどめておくことです。
親もまた、その親の犠牲者なのですから。
幼い時に経験したことで、いまでも思い出すと心が痛む傷になって残っている言葉や仕打ちを一つも思い出せない、などという人はまずいないでしょう。
完璧な親など、どこにもいないのです。
自分がその年齢になってみればわかります。
親もまた、利己的で打算で動き、劣等感や性欲に悩まされる未熟な心を持った存在なのだということを。
親は、自己形成の途中で親になります。
ほとんどの親は、夫婦の絆がしっかり確立しないうちに、子どもが誕生します。
子どもが育つ月日のなかで、どんな夫婦の間にもいろいろな波風がたちます。
このために、子どもとは、親の結婚生活の不完全さを反映しないわけにはいかない存在なのです。
多かれ少なかれ私たちは、不完全な親と家庭をそのままに愛さなければならない宿命を背負っているのです。
親への怒りや恨みに目覚めると、極端に視野が狭くなり、そこから抜け出すことが困難になります。
なぜなら、親と家庭の不完全さを自分の心を歪ませた原因として理解すると、すべてが理解可能であるかのように思われるからです。
親に対して傷つけられた恨みをいつまでも抱いてこだわっていることは、無駄なことです。
「四十歳になれば、自分の顔に責任を持て」といいます。
自分の容姿さえ、自分で引き受けなければなりません。
ましてや、自分の人生、自分の心の持ち方は、二十歳を越えれば自己責任です。
自分の一生は、自分で背負っていくしかありません。
自分の人生をほかのほかの誰かに生きてもらうことはできません。
関連記事
自分の人生は、自分で作っていくしかないのです。
自分の幸福は、自分で努力して、自分で作り出すしかないのです。
自分の至らなさを親の責任に帰して親を責め続ける人は、自分の人生を自分で引き受けるつらさから逃げてしまっているだけなのです。
自分の人生を自分で捨ててしまっているだけなのです。