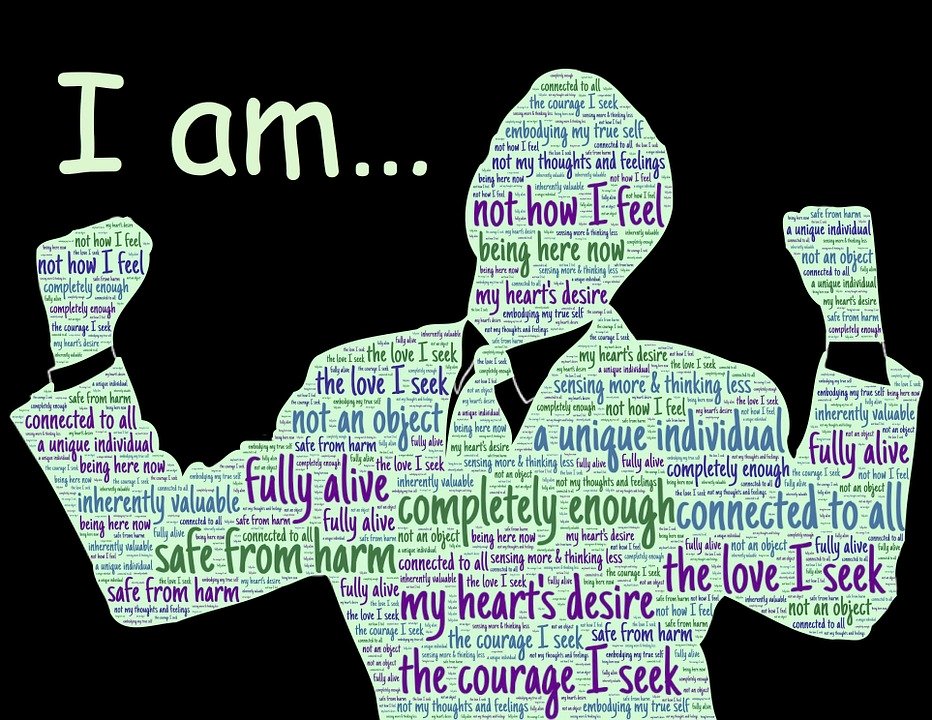自己評価=まわりの評価が一番幸せ
作家の石川達三は、小説『開き過ぎた扉』のなかで、主人公である男性医師の出生の秘密を通じて「人というのは、その人を取り巻くすべての人の評価を足し合わせたものだ」というようなことを書いていました。
物語の主題ではありませんが、読んだ当時非常に印象に残った部分です。
人間同士が接する時、みんなたがいを評価しています。
「この人はこういう人」「あの人はああいう人」という評価が、それぞれのあいだにあり、Aさんに関するBさんとCさんの評価は、かけ離れていることはほとんどなくて、不思議なことにたいてい似ている。
この「自己評価」と「まわりの評価」の関係が重要なのです。
なかには、自己評価は高いけれど、「実」がともなっていない人。
まわりから評価されているのに、自分を卑下してばかりいる人がいますが、どちらも不幸です。
できれば、「自己評価」と「まわりの評価」は一致しているほうがいい。
二つの評価がきれいに重なっている、または非常に近いところにあるほうが、人は幸せに生きられます。
人は誰でも、自分を価値ある人間だと思いたい。
けれど世間でいろいろと揉まれるうちに、頭のなかで描いていた「自己像」は、次第に砂にまみれていきます。
きれいな体で土俵に上がった力士が相撲をとるうちに砂で汚れていくみたいに。
その時どうするか。
大切なのは、「なるほど、今の自分の評価はこういうものなんだな」と一度冷静に受け止めること。
自己像が傷つけられると、つい「こんなはずじゃなかった」と環境や他人のせいにしてしまいたくなるし、そのほうがずっと楽だけれど、結局は自分のためにならないのです。
たとえば、テストで失敗して赤点を取っちゃった時、「自分が得意な問題じゃなかった」「あれが出なければ、できたのに」と全部まわりのせいにすることだって、もちろんできる。
だけど、なるべく若い頃は「自分の失敗は自分の責任」と引き受ける習慣をつけたほうがいいと思います。
そうしないと、自己評価ばかりが高くて実のともなわない「残念な人」になってしまう。
そもそも自己評価とは、自分自身が納得している評価のこと。
それと「まわりの評価」のズレを小さくしていくにはどうすればいいか。
一番は、自分の実力をできるだけいろんなところにぶつけてみることです。
たとえば、会議で発言する前に自分の意見を「取るに足らないつまらないこと」「誰でも思いつくようなこと」と判断して、発言しない人がいるけれど、それほど傲慢なことはない。
「これはすごい意見なんだ」と完全に確信できるまで発言しないのだとしたら、大半の人は一生発言なんかできやしない。
高かろうが低かろうがそれが自分の今の実力。
ぐずぐず言っていないで、自分より経験のある人、自分よりすごい人にぶつけて評価してもらえばいいのです。
周囲に自分の実力をぶつけるという他流試合を重ねて、勝ったり負けたりすることで、自己評価とまわりの評価はどんどん近くなっていきます。
評価のズレをなくせば、楽になる。
自己評価と周りの評価がズレているのはつらい。
高い周りの評価に自己評価をどう一致させていくか。
せっかく高い周りの評価を下げてしまうのは悔しいから、努力する。
そうするうちに段々と実力もついて、自己評価と一致するようになったのです。
自分が伸びる方向を見極める
まわりの評価と自己評価のズレをなくすには、とにかく周囲の環境に自分をぶつけていくしかありません。
そうすることで自分をみつけて自己評価を正しく修正していくチャンスを得られます。
ところが、今の社会には、そのチャンスがなかなかありません。
厳しいことを言うようだけど、「みんなで手をつないで一緒にゴールしましょう」というふうに世の中はできていない。
実際にとんでもなく足の速いヤツはいる。
「あいつは足が速いけど、自分は足が遅い」。
それでいいのです。まずは自分の限界点を知ることから始まります。
考えてみれば、大人の世界では、毎日そんなふうに自分の限界点を突きつけられてばかりでしょう。
大人はみんなある種の劣等感を持って生きている。
「あいつのほうが仕事ができる」「こいつのほうが女にモテる」・・・とか、いろんな劣等感があるけれど、そのなかで「でも、自分にはこれがある」と言える部分も同時に見つけているわけです。
人間が社会のなかで集団で生きる以上、こういう残酷さは当然のこと。
ところが教育の現場では、大人の世界の残酷さがあたかもないかのように、「みんな一緒」と教えています。
言い換えれば、「(子どもが)自分の限界点を知るのはかわいそう」というのが、今の日本の教育。
大人が勝手に子どもたちをフワフワの真綿に包んで無菌室で育てておいて、二十歳前後でいきなり真綿をバッと剥いだら風邪を引くのは当然でしょう。
「50人のなかで49番目」だと相手に知らせること自体は、問題ありません。
教育者の仕事は「君は100メートル走では49番目だけど、歌を歌わせたら一番目だね」というふうに、優劣をつけたまま放置するのは、教育ではないのです。
教育とは、得意な点、不得意な点を選択する機会を与えること、つまり引導を渡すことです。
がんばっても「これ以上は上がらない」という点を本人に理解させて、その後の60歳までの人生設計をさせる。
自分の背中に、どのくらいの大きさの甲羅がついていて、それはどういう色をしているのか。
現実をきちんと伝えて、その上で本人に選択させます。
「引導を渡す」というと、何だか最後通告をして無理やりあきらめさせるようなニュアンスがありますが、そうではない。
伸びる方向とがんばっても伸びない方向を見極めて、伸びる方向を伸ばしてやることで、それ以外の部分が自然と削ぎ落されていくようなイメージです。
引導をちゃんと渡してやれるかどうかで、その人が60歳を迎える時に、振り返った自分の人生の充実感はまったく変わってくると思います。
引導を渡されるタイミングは人それぞれですが、私自身の経験からするとできるだけ早いほうがいい。
たとえば、高校生というのも、一つのタイミングです。
反抗期をすぎ思春期も終わりに近づいて、自分のことを初めて客観的に見られる時期だから。
高校時代には、自分の甲羅でどこまでいけるだろうと、「人生の想定案」を作ってみることが、大学受験の準備よりも重要だと思います。
もちろん、この「人生の想定案」は、後々の人生で何度も修正されていきます。
高校生が考えた「人生の想定案」は、大学生になると変わるでしょう。
社会人になるとさらに変わるはずです。
変わるのは、成長の証です。
人生を登山に例えるなら、登り続けて標高の高いところからより広い視野で眺めてみると、自分が目指す頂がよりはっきりと見えてきて、以前よりも高いピークを目指すようになるからです。
もし「人生の想定案」を考えることなく、60歳になってしまったら、その人生は進むべき登山路を定めない、フラフラとしたものになってしまうでしょう。
■関連記事
自分から発言すると楽になる
負けることで自分の居場所が見えてくる
「挫折が人を成長させる」とよく言います。
勝つことはもちろん重要だけれど、負けることのほうが人生においては大きな意味を持ちます。
えてして人は勝つと考えないものです。
喜んでばかりで、なぜ、勝てたのかと勝利の理由を突き止めようとはしません。
けれど、負けた時はそうじゃない。
敗者になるのは誰でも悔しいから、原因を本気で分析するし、反省もする。
それが生きた教訓となって自分のなかに蓄積され、次の勝利につながっていきます。
言ってしまえば、勝負そのものより、挫折の経験とどんなふうに向き合うかが、成長のカギを握るわけです。
ある秀才は「わからない」という感覚がよくわからなかった。
学校で授業に出てもわからないことが一つもないので、そのうち退屈になって通学をやめてしまったほどです。
ところが受験して入学した中学校に通いはじめると、今度は「どうして、こいつはこれがわかるんだ!?」というようなレベルの生徒がうようよいる。
これは衝撃的な出来事である。
挫折体験です。
悔しい挫折があったから、「さて、どうしようか」と知恵を絞る。
次の道はそうやって初めて見えてくるものでしょう。
世の中、どうあがいても適わない凄いヤツはいます。
それを「学芸会で主役になれるのが一人だけではかわいそうだから、主役は10人にしましょう」というのはおかしい。
演技のうまいヤツ、歌のうまいヤツ、声のでかいヤツは主役になれるけれど、演技の下手なヤツ、音痴なヤツは脇役にしかなれない。
それは世の中のルールとして当たり前のこと。
このルールをきちんと教えない教育は、おかしいと思います。