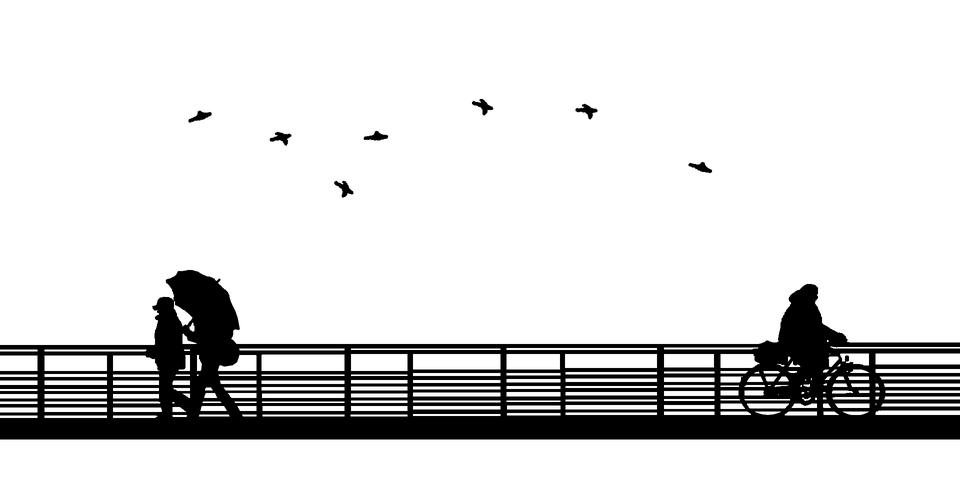人類の歴史は、文明を築き、自然を改変し、大規模な社会を現出させることで、人間一人ひとりの自己価値感を高める作用を果たしてきました。
しかし、同時に、自己価値感を脅かす無数の事象も生み出しました。
このことをいくつかの視点から見てみましょう。
「ぼんやりとした不安」の大衆社会
資本主義の発展は社会の流動性を拡大させ、大都市、大組織、大企業を生み出しました。
この社会的流動性は人々を住み慣れた地域から切り離し、頼るものもなく社会に投げ出された「寄る辺のない」感覚を人々にもたらしました。
人びとは、自分の生活を作り上げることに必死にならざるを得ず、人生は慢性的に漠然とした不安感、無力感、孤独感、無価値感をともなうものになったともいえます。
大衆社会においては、自分がとるにたりない存在であることを頻繁に意識させられます。
通勤のために駅の階段をのぼる多くの人びとの群れのなかにいるとき。
知らない人ばかりの街のなかで人混みにまじって歩く時。
選挙において自分の投票は何千何百万票のうちのたった一票にすぎないのだと、実感させられるとき。
自分が投票した候補が落選すればなおさらです。
大衆社会はまた、契約社会でもあります。
自分がある位置からはずれれば、その位置を次の人が占めます。
人事異動で、自分が座っていた席に他の人が座っているのを見ると、「かけがえのない自分」ではなく、「取り替え可能な自分」をいやというほど認識させられます。
ましてや、リストラにより会社を追われるとき、せっせと築き上げてきたと思っていた自己価値感は、無惨に砕け散ります。
機械に振り回される人間
科学技術の進歩は、私たちの環境を巨大な建造物に変えました。
高層ビルを見上げるとき、デパートやホテルの大きな吹き抜けの下にいるとき、これを作り上げた科学技術の偉大さを感じると同時に、それらに圧倒される思いがします。
昔から権力者や宗教家は、圧倒するという心理を利用して大衆を操作してきました。
宗教は巨大な寺社を作り、権力者は大きく、きらびやかな城を建造しました。
その巨大さで大衆に無価値感を与え、服従させることを容易にしたのです。
人間の力を超える機械の出現もまた、人間に大いなる有能感とともに、無力感をもたらしています。
自我との一体感が得られる機械は自己価値感を増大させ、一体感の得られない機械は自己無価値感を増大させます。
車で疾走するとき、私たちの自己価値感は高揚しますが、歩行者としての自分のすぐ脇を猛スピードの車が走り抜けたときには、自分の身体のひ弱さを痛感させられます。
新しい機器が次々と登場しますが、その取り扱いについていけない惨めさは無能感をもたらします。
普段使っている機械でも、どのようなメカニズムによるのかはほとんどわからないものがあります。
たとえば、インターネットで世界中の情報を瞬時に検索することをおこなっていても、それがどのようなメカニズムでおこなわれているのかを説明できる人が、どれほどいることでしょうか。
機械を使っていながら、自分はその支配者ではなく、機械に使われている存在であるように感じられます。
マスメディアの発達
マスメディアは、私たちが処理しきれないほどの情報をもたらします。
多くの情報と多様な価値観のなかで、それぞれの情報をどのように判断すべきか、途方に暮れてしまい、無能感を刺激されます。
テレビで多数のコメンテーターが起用されるようになったのも、こうした大衆の戸惑いを反映しているものと考えられます。
マスメディアから流れる多くのコマーシャルは、夢を与えるとともに、無力感をもたらします。
それは購買意欲を誘うとともに、それらの大部分は買うことをあきらめねばならない商品だからです。
マスメディアのなかでも、とりわけテレビは、不断に比較対象を提示することで無価値感を与えます。
定年までのローンで買った小さなわが家に、仕事で疲れ、帰って来て、夕食の卓を囲みながらテレビをつけると、勝ち組といわれるヒルズ族、富豪の大邸宅、何百万円もする装飾品をキラキラさせる若い女性、つい、自分の身と引き比べてしまいます。
抜群のスタイル、完璧の美貌、特異な才能。テレビ画面のそうした人々への賞賛とともに、自分の心の隅に生じる落胆を否定することができません。
自然との乖離
文明の進歩は、人間を自然から引き離す結果をもたらしました。
子どもの遊びも、大人の仕事も、自然そのものを対象とすることが少なくなり、機械や人間社会を対象とするものが多くなりました。
こうして自然との乖離が、自己価値感の獲得に不利な条件となっています。
自然との闘いは、遊びにせよ、労働にせよ、自分が持つそのときの知恵と力を最大限発揮して対処する機会です。
その結果は勝ち負けではありません。
競争でもありません。
うまくいかなければ、ただうまくいかないだけです。
うまくいかない原因を考え、自分なりに創意工夫して、次にはより賢明に対処しようとするだけです。
こうした一連のプロセスには、自分の力が客観的に表われ、それはつねに挑戦であり、充実感をともなった苦労であります。
自然相手の遊びや仕事は、自分の能力の向上を実感できるし、自分が達成できるようになった、という有能感の高まりも経験できたのです。
核家族化―地域社会と断絶
人類の歴史のなかで、永いこと子どもは地域みんなの子どもでした。
家族はその地域・社会にしっかりと根を下ろしており、子どもは「誰々さんとこの子」と、地域のみんなに知られ、みんなに受け入れられていました。
子どもにとっては、優しいおばさん、口うるさいおばさん、恐いおじさん、面白いおじさん、物知りのおじいさんなどがまわりにいて、うまれたときから自分がそうした多くの人びとに見守られながら成長してきたと感じられたものです。
親に叱られ泣いていると、声をかけてくれる近所のおばさんがいました。
家を飛び出した子どもを、気持ちが落ち着くまで家に居させてくれるおじさんがいました。
多少問題のある子どもでも、大人になったら真っ当になると、周囲の人は大目にみてくれたものです。
子どもたちは地域の人びとに受け入れられているという安心感があり、それは知らず知らずのうちに、自己価値の感情を根づかせる作用を果たしていました。
家族もまた大人数でした。
兄弟姉妹がいて、祖父母や、何らかの理由で親戚の人などが同居していることも珍しくありませんでした。
大家族のなかでは、両親とうまくいかなくても、自分を可愛がってくれ、自己価値感を満たしてくれるほかのだれかを見つけることができました。
夏目漱石の『坊ちゃん』に登場する「お清」、井上靖の『しろばんば』における「ばあちゃ」などです。
ところが、社会的流動性の急速な高まりとともに、家族は地域社会と切り離されました。
二男、三男は都会に出て、新たな家庭を築き、生活や収入、仕事に合わせて、住居を短い期間で次々と変えるようになります。
このために、となりの家の子どもの名前さえ知らない状況が生まれ、子どもはもはや地域社会の子どもではなくなりました。
同時に、核家族が多くなり、子育ては、母親が全面的に責任を負うという暗黙の規範ができあがりました。
「誰々さんちの子ども」というよりも「自分たちの子ども」という意識が親に強まりました。
とりわけ、子どもの養育を主に担う母親に、「私の子ども」という意識が強くなり、母親が子どもを抱え込むという状態がうまれました。
こうしたことの反映でしょうか。
百五十年間の少女たちの日記を分析したアメリカの研究者は、とりわけここ三十年ほど親からの自立に悩む傾向が強まっており、自己価値感の急速な低下が見られる、と指摘しています。
競争によるストレス社会
現在は国際的な競争の時代であり、企業は生き残り戦略で合理化を進め、社員を競わせています。
公務員も財政改革のために批判のやり玉に挙げられ、労働条件の切り下げを強いられています。
さらには、多くの若者が職に就けず、国民は「痛みに耐えよ」のスローガンのもとに、年金は減額され、福祉は切り下げられ、生活を切り詰めることを余儀なくされています。
規制緩和の名のもとに自由競争を導入した結果、競争はルールなきまでに激化し、勝ち組と負け組との格差も目に余るものとなっています。
自殺者が年間三万人を超えているということにも、現在のストレス社会の影響が反映されていますが、京都文教大学の島悟教授を主任研究者とする厚生労働省の調査は、さらに驚くべき実態を報告しています。
この調査は、都内の中小企業の従業員を対象としたものですが、「過去一年以内に死にたいと思ったことがありますか」という問いに、「頻繁に思った」が1.8%、「ときどき思った」が8.5%で、じつに10%を越える人が「死にたいと思った」ことがあるというのです。
さらに、「過去一年以内に実際に自殺しようとしたことがありますか」という問いにも、2.2%の人が「ある」と回答しているのです。
このように、国民にとって希望をみいだすことが困難で、敗北感や無力感、孤立感にとらわれやすいストレスの多い社会となっています。
こうした社会感情から、現在を「うつの時代」と名付けた研究者もいるように、自己無価値感は国民のなかに広範に広がっています。