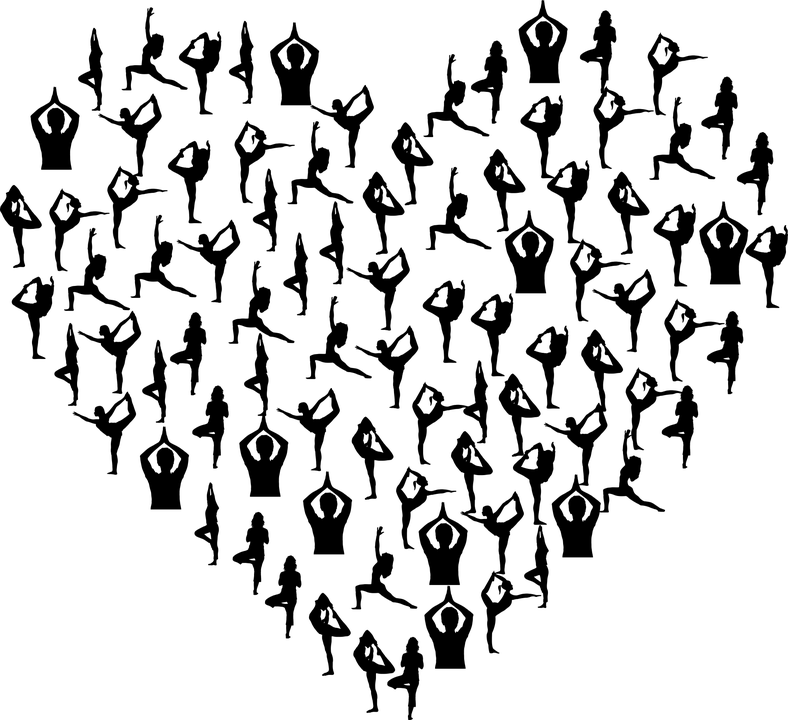傷つきやすさの根底には自己価値感の希薄さがありますが、それ以外の特性も傷つきやすさに関係します。
まず最初に、そうした特性を考えてみます。
傷つき体験の乏しさ
傷つきやすい人のなかには、体験の乏しさのために傷つくことに対する抵抗力が育っていない人がいます。
昔は兄弟が多く、幼い時から頻繁に兄弟ゲンカがありました。
親も感情にまかせて、遠慮なく子どもを叱り飛ばしていました。
こうした体験によって、家庭のなかで簡単には傷つかない心が作られていきました。
ところが現在は、少子化によって、こうしたぶつかりあいが少なくなりました。
また、親は一人ひとりを大事に育てるようになりました。
叱ることさえ、できるだけ差し控えるようになりました。
このために、叱られることに対する抵抗力がつかず、叱られることに敏感になっているということがあります。
さらに、今の親は、子どもが失敗をしないようにと配慮して育てます。
このために、失敗を過度に恐れる心が子どものなかに形成されています。
また、親自身が過度に競争を意識し、子どもが競争に負けることを恐れる傾向があります。
塾やスイミングスクールなどに子どもを通わせるのも、「せめて人並みに」という親の願いによる場合が少なくありません。
むろん他の人よりも優れることを求める親もいますが、多くの場合は「人並みに」という意識です。
このために、人並みでないこと、人に劣ること、競争に負けることが自己価値に直結する心理を作ってしまい、傷つきやすくなるのです。
友達との遊びも、遊び仲間の数が少なくなり、子ども同士の激しい感情のぶつかり合いの機会が少なくなりました。
遊びの内容も変わりました。
他の子と直接激しく競争したり、争ったりする遊びではなく、テレビゲームなどなんらかの物を介した遊びが多くなりました。
こうしたことのために、遊びが傷つき耐性の強化につながりません。
昔は傷つきやすいのは女の子の特徴とされていました。
しかし、現在の若者を見ていると、女子の方が傷つきやすい、とはいえないように思われます。
母親は男の子がどのようなものであるかが分からないために、女の子に接するよりも、つい大事に気分を損ねないようにと育てることも一因だと思われます。
傷つき耐性が低い人は、傷つくのが怖いので、人と交わる機会を自ら狭めてしまいます。
このために、いっそう傷つき耐性が弱化されてしまうという悪循環のなかにいます。
登校拒否や、引きこもる人のなかに、この典型をみることができます。
参考記事>>人付き合いが怖いを克服する方法
関連記事
感情処理能力の弱さ
傷つきやすい心の問題の一つは、自ら傷口を広げてしまうことです。
すなわち、傷つきやすい人は、マイナスの感情を心の全面に広げてしまい、日常生活にまで影響を受けがちです。
そして、この日常生活での混乱が、いっそう自分をストレスフルな状態に追い込んでしまいます。
子どもが一人の存在として尊重されず、それゆえに、「すねる」とか「ぐずる」ことで初めて意志を通すことができるというような育てられ方をした場合、感情を乱していることが状況を打開する武器になります。
このために、「気分を害する=傷つく」という対処法を多用することになり、健全な感情処理能力を育てることができません。
こうした人は、自分が傷つきやすいと思っているのですが、じっさいにはその傷つけられたという不機嫌さで人を支配するようになります。
周囲への迷惑を気にせず、傷ついた心の不機嫌さをそのまま出し、すねたり、意固地になったりして、自分の欲求を押し通すのです。
逆に、「泣くんじゃない」とか「細かいことを気にするな」など、ただじっと我慢することを求められたり、いつでも理性を優先する感情処理の仕方を求めて育てられると、自分の感情を発散させるのではなく、抑圧する方向へと向かいます。
こうした人は、自分の感情とは裏腹な行動により、その場を取り繕う態度を身につけてしまいます。
その結果、表面では屈託なさを装いながら、内面は傷ついており、恨みや敵意の感情を密かに蓄積していくような心理傾向になります。
子どもの感情表出を不必要に抑えることなく、子ども自身が感情を処理することを気長に見守ってあげる。
こうした親の態度が、子どもの感情処理能力を育てていくのだと思われます。
関連記事
無意識の甘え
周囲の人に裏切られて傷つくことが多いと感じている人は、甘えと依存心が強い人である可能性があります。
私たちは人と接するとき、自分がどう振る舞うかを考えているばかりでなく、相手にどう振る舞ってほしいかを暗黙のうちに期待しています。
たとえば、「こんにちは」と笑顔で相手に挨拶したとき、相手もまた、笑顔で反応を返してくることを期待しています。
ですから、相手が挨拶を返さなかったり、堅い表情のまま挨拶を返してくると、「おや?」と戸惑うのです。
傷つきやすい人は、このような相手の反応に対してある種の甘えを持っていることが少なくありません。
甘えを求めることそのものが間違いである相手に、無意識のうちに甘えてしまっているのです。
交流分析(E・バーンが中心となって発展させてきた人格形成の理論と治療法)によれば、私たちの心は親の心(Parent)、成人の心(Adult)、子どもの心(Child)という三種類の心から成り立っています。
親の心(P)とは、両親から受け継いだ「親としての心」です。
具体的には、庇護的であったり、批判的であったりする心です。
成人の心(A)とは、成長する過程で現実とぶつかるなかで作り上げてきた心です。
具体的には、現実的であるとか、物事に合理的に対処するなどです。
子どもの心(C)とは、大人になっても残っている子どもの心です。
具体的には、天真爛漫であるとか、依存的な心、あるいは、従順な良い子などです。
私たちは、他の人と接するとき、このうちのどこかの心で接します。
そして、その時に、相手の人にこの心のどれかで応えて欲しいと期待しているのです。
たとえば、「子どもの心」が強い人は、子どもの心で相手に働きかけ、暗黙のうちに相手に「親の心」で応えて欲しいと期待しています。
こうした人は、命じられた仕事を仕上げたとき、「よくできているね」とか「がんばったね」などの言葉を上司から期待します。
しかし、仕事をきちんと仕上げるのは、給料をもらっているかぎり当たり前のことです。
ですから、上司は、間違いや不十分な点をチェックして、「ここを直して」などと、修正を命じます。
こうした時、「一生懸命やったのだから、それに対して一言くらいあってもいいじゃないか」と、思ってしまい、自分の努力が無視されたと傷ついてしまうのです。
まさに、子どもが一生懸命やって親にほめられることを期待している、親に甘える子どもの姿の再現なのです。
じつは甘えとは、その言葉とは裏腹に、相手を支配しようとする心なのです。
なぜなら、自分に都合の良い行動を相手がするように、と求めることなのですから。
このために、過度に甘える人に対してうっとうしく感じてしまい、つい甘える人を傷つけたくもなるのです。
関連記事
過度の自責感
傷つきやすい人のなかには、本来、相手を怒ったり、憎んだりすべき場面で、自らを傷つけてしまう人がいます。
自責感が強すぎるためです。
乳幼児は不快なことがあると泣き、ぐずり、だだをこねます。
自分にとって心地よい状態になるまで、こうした行動をとります。
ごく幼い子どもでも、理不尽な扱いをされると怒ります。
しかし、このように、イライラする心を相手にいつでもぶつけていては、ぎすぎすした人間関係になり、住みづらい世界になってしまいます。
このために、子どもはこうした心の状態を、次第に自分のなかで処理するように育てられます。
人を責めてはいけません。
人を傷つけてはいけません。
人を悪く言ってはいけません。
我慢のできない子は悪い子です等々と。
ところが、あまりに幼いうちからこうした育てられ方をされると、自分の心をまったく犠牲にしてまで、穏やかな関係を優先する傾向が作られてしまいます。
そして、本来相手に向けるべき怒りや憎しみの感情を、もっぱら自分にしか向けられなくなってしまいます。
通常母親が幼子の世話をしますから、幼子が敵意を感じる最初の相手は母親です。
しかし、母親なくして幼い子どもは生きていけません。
母親の感情を害することは、自分の安全を脅威にさらすことです。
母親に敵意を表現すると悪い子だとされ、母親の気分を損ねたり、悲しませたりします。
このために、母親に対する敵意は抑圧され、そうした敵意を持つ自分を責める心理が形成されていきます。
少し大きくなると、父親もこの対象に入ってきます。
絶対的に力の強い父親は、愛してほしい対象であると同時に、恐怖の対象でもあります。
父親を困らせたり、感情を害したり、悩ませたりすると、手ひどい罰を受ける恐れがあります。
このために、父親に対して率直な反抗や敵対の感情を表現することができなくなり、父親にそうした感情を抱く自分は悪い子だ、と自分を責めることでこの感情を抑圧するのです。
このように、自責感の根源とは、善悪を教えられることではありません。
親のご機嫌をそこね、愛情を失う恐れなのです。
だから、自責感は、人に嫌われることを恐れる心理と結びついているのです。
自責感の強い人は、自分に原因があるのではと、いつでも自分を責めてしまう心優しい人です。
相手を傷つけてしまうのではないかと、いつも恐れている人です。
だから、こうした人は、すぐに謝ります。
「すみません」「申し訳ありません」「ごめんなさい」という言葉を頻発します。
このタイプの人は、「確かに悪意で行動する人も、この世に少しは存在する」という事実を受け入れる必要があります。
そして、そうした人とは、きっぱりとこれを機会に縁を切ることです。
傷つき体験を、その良い機会にすることです。
万一、傷つきが誤解や状況のせいであれば、そして、相手が本当に信頼できる人であれば、時間の経過が再び関係を修復してくれるはずです。
関連記事
柔軟性のない価値観
柔軟性のない価値観を持つために、傷つくことが多い人もいます。
子どもは真実、正義、勤勉、誠実、潔癖、純潔などを教え込まれます。
ところがじっさいにはこうした価値の適用に関して、表のルールと裏のルールがあります。
建前と本音といってもよいでしょう。
裏のルールをうまく使うことによって、表のルールの厳しさを緩めないと、楽に生きていくことができません。
裏のルールを適当に使うような許容性がないと、自分や他の人のささいな不正を大目に見ることができません。
厳格すぎるルールの適用は、本人を責め、苦しませます。
また、相手を責めることになり、そのあげくに相手からの反撃にあって、心が傷つくという結末を迎えるのです。
柔軟性のない価値観を持つ人は、他の人にもルールの厳守や同じ価値観を強制する傾向があります。
しかし、他の人は、その人なりのルールや価値観で行動しますから、当然ぶつかることになります。
こうして、自分の真面目な思いが裏切られたと傷つくのです。
しかも、自分の正当性を疑いませんから、自分がいつも「どうしようもない人たち」から傷つけられると感じるのです。
一方、相手の立場に立ってこの場面を考えてみると、柔軟性のない価値観を持つ人の言う事は正しい、と感じられる部分があることを否定できません。
しかし、「現実にはそうは言っても・・・」というのが率直な感覚です。
そのうえ真正面から正論を吐かれると、すなおに受け入れることに反発を感じてしまいます。
こうして、結局、自分の不完全さが非難され、自分が不正を選び取ったという状態にされてしまいます。
このために、相手の人も、傷ついているのです。
柔軟性のない価値観を持つ人は、自分が傷つくだけでなく、周囲の人を傷つける人でもあることが少なくありません。
関連記事
親とのトラウマの再現
親との間のトラウマが、傷つきやすさの源になっている人も少なくありません。
こうした人は、年上の人とか、目上の人に会わなければならないとひどく緊張してしまいます。
上司の思惑がとても気になってしまいます。
嫌われることを恐れてびくびくし、嫌われたのではないかと思うと混乱してしまいます。
このように、親に対する感情を、親以外の人に無意識のうちに向けてしまうことを一般に転移といいます。
精神分析による治療では、これにより患者さんの心を理解しようとし、また、これを解決するのが治療の重要な要素とされています。
年上の人や目上の人に限りません。
身近な人に対して、無意識のうちに転移は生じます。
ある男性は、妻のちょっとした言葉に傷ついてしまいます。
たとえば、夫が出掛けに「僕の定期券、知らない?」と妻に聞いたとき、「だから、いつもカバンに入れておくように言ってるでしょ」と妻が答えたとします。
妻の方は夫を非難しているつもりはないのですが、我の強い母親にいつでもこうした返し方をされて育った夫は、妻の言葉が母親の言葉と重なり合い、母親に叱られている自分を再演してしまうのです。
また、ある若妻は、夫のちょっとした行為に、裏切られたかのように傷つき、気持ちがひどく落ち込んでしまいます。
たとえば、帰宅後仕事のことで携帯電話が鳴って、話すために夫がベランダに出ると、それだけで自分が裏切られているように感じてしまうのです。
「仕事で帰りが遅くなるので、夕食は外で食べてから帰る」と電話があると、それだけで見捨てられた気持ちになってしまいます。
彼女の父親は、愛人が居ていつも遅い帰宅でした。
母親は彼女に夫への不信感を語り、彼女は母親と二人で父親を責めることで、心が不安定な母親の愛情を得てきたのです。
こうして母親から注入された父親に対する根深い不信感が、夫に対して無意識のうちに転移してしまうのです。
関連記事
欺瞞と空虚な内面
私たちが「自分」というとき、その内容は大きく二つに分かれます。
「外に出す自分」と「内に秘めた自分」です。
この二つの自分の間での食い違いが大きく、どちらも「欺瞞と空虚」であるという感覚を持っているために傷つきやすい人がいます。
「外に出す自分」とは、人と接するときに相手に表現する自分であり、実際に社会に適応して、行動している自分です。
外に出す自分とは、もともと親に気に入られるための自分であります。
ですから、いくら外に出す自分が出来が良かろうとも、それで心からの充足感が得られるわけではありません。
満足は、親の満足した顔を見ることに置き換わってしまっています。
親に対するこうした態度は、他の人に対しても広がっていきます。
そのために、外に出す自分は、もっぱら相手の気に入られるように振る舞うということになり、演技であり、本当の自分ではない、という感覚を免れません。
外に出す自分は、たとえ立派な意見を言ったとしても、改めて自分を振り返ってみれば、あれも知らない、これも知らない、知らないことだらけです。
外に出す自分は、平気な顔で日々仕事をこなしていますが、なんとなく上っ面だけで、心からの自信が持てません。
このように、外に出している自分に対して、欺瞞であり、空虚であるという意識があります。
思春期以降になるとますますこの意識が強くなり、「外に出す自分」は「偽の自分」という感じがします。
そして、外に出さない「内に秘めた自分」こそ、「本当の自分」と感じるようになります。
ところが、「内に秘めた自分」とは、想念だけの自分です。
現実の裏づけを持ちません。
だから、現実に達成できないことでも、「内に秘めた自分」は達成しています。
完成した作品を一編も書いていない人でも、「内に秘めた自分」は将来の芥川賞作家であり得ます。
太り気味の少女も、ほっそりした美少女です。
実際には影の薄い人も、皆から注目されるスターでありえます。
このように、「内なる自分」はいっそう欺瞞性と空虚性に満ちています。
じつは、現実とある程度遊離したこうした自分独自の世界があるからこそ、私たちは自分を保っていられるのです。
すなわち、「内に秘めた自分」とは、仮想のなかで現実とは異なる自分を作り出すことにより、無力感や劣等感に全面的に圧倒されることから我々を守ってくれるものなのです。
ともあれ、「外に出す自分」も「内に秘めた自分」も上記に述べた理由で空虚で欺瞞的であるという意識を否定できません。
この意識を刺激されると、自分という存在全体が否定されたかのように感じ、傷ついてしまうのです。
外と内との乖離の大きい人ほど内面の空虚さや欺瞞性という意識が強いのですから、こうした人は、他の人にそれをさとられないように、つねに自分を注意深くチェックしていなければなりません。
このために、他の人が自分をどう見ているかがいつでも気になり、自意識過剰にならざるをえません。
この過剰な自意識のために、他の人の何気ない言葉やしぐさが自分の欺瞞性や空虚さを脅かすものに感じられ、傷つきやすいのです。
自己防衛としての高いプライド
劣等感や内面の空虚さの感覚は、自分自身に価値があるという実感、すなわち、自己価値感を危機に陥れます。
このために、心はいろいろな防衛策を講じて、自己価値を守ろうとします。
その一つの方法がプライドです。
自分は能力があり、重要な人物であり、人から重んじられるべき人間だと、自分で仮想することによって、自己無価値感から逃れようとするのです。
このために、こうした場合のプライドは、その人の現実の姿から離れて、不自然に高いものになります。
この防衛的な高いプライドで自分を守ろうとすると、自分が有能であり、完全である姿をいつでも見せつけておかないと心の安定が保てません。
このために、ちょっとでも弱みを見せることは脅威です。
ささいな落ち度や、ちょっと劣ること、あるいは遊びで負けたりすることさえ、自己価値を脅かします。
このために、こうした防衛的なプライドは傷つきやすいのです。
事実、傷つきやすい人は、自分が低く見られたということにとりわけ敏感です。
たとえば、上司から、他の人は声をかけてもらえたのに、自分はかけてもらえなかった、と気にします。
若い女の子は、他の友達と同じように扱われなかった、と傷つきます。
結婚式に招待されなかったと傷つきます。
デパートで服を見ている時にさえ、店員から、「どうせ、あの人は買わない人」と見られることに耐えられません。
それで、つい、買う予定でなかったものを、買ってしまうなどということさえあります。
プライドが高いから傷つきやすいのだと、単純に考える人がいます。
そうではなく、この高いプライドの根底には自己無価値感があるのです。
高いプライドは、この自己無価値感の上に建つ砂上の楼閣だからこそ、傷つきやすいのです。
こうした防衛的なプライドは、自分本来の充実感や満足感を大事にすることを放棄して、自分の価値をもっぱら他の人の評価によって実感しようとすることです。
しかし、他の人がどう思うかは、その当人が決めることです。
ですから、自己価値が実感できるかどうかは、相手次第ということになります。
このために、防衛的なプライドを持つ人は、いつでも他の人に蹂躙されているような感じがします。
自分を支配するのは自分ではなく、他の人であるかのように感じられます。
何をするにしても、自分の内からの欲求で行っているのではなく、強制されてしている、という感覚があります。
こうしたことのために、高いプライドとは裏腹に、無力感が同居しているのです。
このように述べてきたところで、やはり傷つくことの根底には自己価値感の問題があるということに至りました。