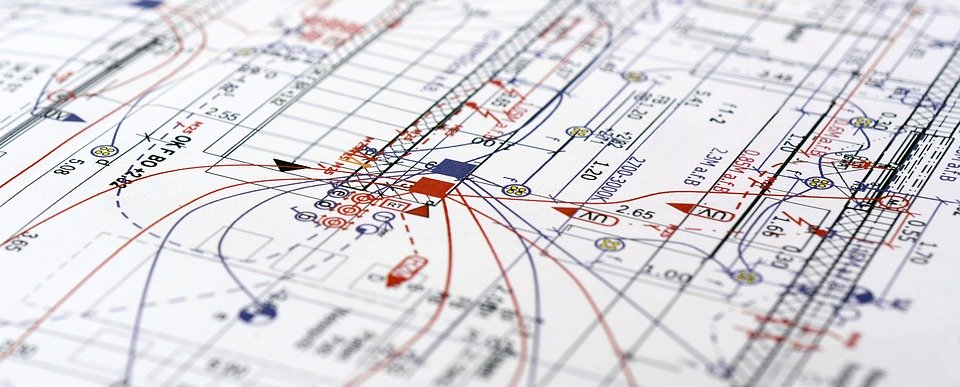自己価値感とは、「自分に価値があるという感覚」のことです。
たとえ人と比べて劣っていても、未熟なところがあったとしても、自分はかけがえのない価値ある存在だ、という感覚です。
自己価値感は、自信や、有能感、自尊心、自己肯定感などを含み、また、それらの基盤ともなる感覚です。
人はこの自己価値の感覚をつねに意識しているわけではありません。
暖かな愛情に包まれていると感じたときや、一人の人間として尊重されていると感じたとき、あるいは、大きな仕事をやり終えたときなど、幸福感や達成感、充実感、成長感などとともに自己価値の感覚を体験します。
むしろ自己価値感は、その価値がおびやかされたときに、自己無価値感として体験されやすいものです。
自己価値感がおびやかされているときとは、愛を失ったり、失敗したり、軽んじられたり、劣っていることが明らかになったり、自分を偽ってしまったときなどです。
こうしたとき、「自分はだめだ」とか、「どうせ私は・・・」とか、「私なんか・・・」などという言い方をします。
また、わざと乱暴な口をきいたり、すねたり、反抗したりすることもあります。
浪費したり、過食したり、深酒をするなど、ふだんの生活リズムを崩してしまうこともあります。
自分の身体を汚す行為をするなど、自暴自棄的行動に走ってしまう人もいます。
いずれの言動も、自己無価値感の表れです。
このために、自己無価値感は、屈辱感、孤独感、空虚感、無力感、卑小感、虚脱感、絶望感、不安感、恐怖感などの感情とともに体験されがちです。
また、自己価値感が稀薄な人ほど自己価値感が容易にゆらぐので、無価値感を頻繁に、しかも深く体験することになります。
このことは、身体感覚と同じようなものです。
私たちは生まれてからいままで、休むことなく呼吸していますが、ふだん呼吸を意識することはほとんどありません。
走って息苦しくなったときや、咳き込んで苦しいときなどにはじめて意識します。
喘息など呼吸器系に障害がある人は、健康な人よりも日常的に呼吸を意識させられます。
心の深層と表層
自己無価値感の希薄さは、劣等感と結びついていることが少なくありません。
しかし、自己の能力への自信を持っていながら、あるいは客観的に優れた業績を上げながら、自己無価値感にさいなまれる人も少なくありません。
こうした人は、業績を上げることや他者からの評価によって希薄な自己価値感を埋め合わせしようとしている人なのです。
人間の心は単純ではありません。
心の表層と深層とは、おうおうにして食い違います。
このことは、フロイトが百年も前に明らかにしたことです。
にもかかわらず、警察やマスコミが、たとえば、猟奇的な事件を犯した少年の犯行動機を指摘するときなど、いまだに人の心を単純で一次元的なものとしてとらえようとする傾向から抜けきれません。
人の心の真実を理解するためには、少なくとも心の表層と深層とのくい違いをとらえることが必要です。
自己価値感も同様に、深層にひそむ基底的で中核的な自己価値感と、表層の状況的な自己価値感とに分けてとらえなければなりません。
なぜなら、基底的な自己無価値感を補うために、表層の状況的自己価値感を肥大化させている場合が少なくないからです。
深層の自己価値感―幼児期の環境
基底的な自己価値の感覚は、幼児期から形成され、児童期の初期には確立してしまうといわれています。
その形成条件は、愛情豊かで適切な養育環境です。
自分が誕生した世界で自分が歓迎され、自分の内面に即応した養育がなされることです。
逆に、基底的な自己無価値の感覚は、愛情に欠けた適切でない養育において形成されます。
自分と外界との不適合をつねに体験する養育環境です。
自分の欲求や願望が頻繁に挫折させられ、自分の感覚や感情が無視され、自分の行動がしばしば意図したとおりの結果を生み出さないような状況です。
このような不適合な状況では、子どもは自分の感覚、欲求、意思、感情、行動に価値があるとは感じられず、自分そのものが無価値な存在だという感覚を形成してしまうのです。
もちろん、ごく幼い時期のこうした心の動きは、無意識のものです。
しかし、無意識であるがゆえに、それだけ強烈に脳に刷り込まれ、心のすみずみに広がり、そののちの人格を作り上げていく基礎になってしまうのです。
たとえば、しっかりとした自己価値感を持つ子どもは、自分と他者を信頼し、外界が自分を受け入れてくれることを疑いません。
このために、自分の感情や欲求を素直に表現し、外界に働きかけます。
こうした能動的な行動が外界への適応能力を発達させ、自分と外界への信頼感をいっそう高めます。
こうして、自分を取り巻く世界はますます魅力を増し、生活は喜びや楽しみに満ちあふれたものになっていきます。
これに対して、希薄な自己価値感しか形成できなかった子どもは、自分を取り巻く外界を信頼することができず、外界に率直に働きかけることを躊躇してしまいます。
これが、諸能力の発達の機会をせばめ、自信の獲得を妨げます。
そのために、外界は脅威的なものと感じられ、必然的に自分を守ることへと意識が向いてしまうのです。
表層の自己価値感―児童期以降
状況的自己価値感は、意識性が強まる児童期以降に形成されます。
そして、思春期、青年期、成人期、老年期を通して形成と変容がおこなわれます。
状況的自己価値感が形成されるプロセスは、大きく三つに分けられます。
一つは、人との交流によるものです。
愛されること。
尊重されること。
受容されること。
こうした体験が自己価値感を高めてくれます。
なかでも、自己無価値感に苦しむ青年にとって、深く心を通じ合う友情や恋愛、心の師となる人との出会いなどは、基底的無価値感そのものを修復する作用を果たすことがあります。
二つめは、自分の力の拡大の自覚です。
身体が大きくなること、身体が魅力的になること、能力が高まること、何ごとかをやり遂げること、成功した体験、競争で勝つこと。
こうしたことが、自信をもたらし、自己価値感を高める作用を果たします。
とりわけ、青年期にスポーツや特技などに徹底的に打ち込んだ体験は、「やればできる」という基礎的な自信をもたらします。
また、成人期を迎えて、一人前に仕事ができたという体験は、その後の人生を生きていけるという現実的な自信を与えてくれます。
三つめは、他者から寄せられる評価です。
注目されること、賞賛されること、尊敬されること、憧れの目で見られること。
こうしたことはいくつになっても嬉しいことであり、自己無価値感の高揚をもたらします。
人は自己価値感を求める
オーストリアのせいしん分析学者A・アドラー(1870~1937)は、自分の価値感が減少させられるのは許せないということが「人生最高の法則」だ、と述べています。
自分という価値を守り、自己価値感を高めたい欲求は、人間にとって基本的で、強烈なものなのです。
このために、私たちは意識的、無意識的に自己価値感を獲得し、維持し、高めようとします。
愛し、愛される関係を求め、深めようとします。
また、自分の力を伸ばし、自己成長しようと努力します。
親や教師、友達、社会から認められようと努めます。
自己価値感を守ることは、ときには自らの命と引き換えにするほどの重さがあります。
たとえば、いじめられて自殺を考えるほどつらいのに、そのことを親に訴えない子どもがいます。
親に言ったら、親にさえ情けない自分の姿があからさまになってしまうからです。
そのつらさを口に出したら、自分で自分の無価値さを確認することになり、耐えられないからです。
親からひどい虐待を受けいている子どもも、その親をかばいます。
親にさえ愛されていないという事実を受け入れることは、耐え難い無価値感情をもたらすからです。
子どもばかりではありません。
恥辱により自己価値感を傷つけられて生きるよりも、死を選ぶ大人もいます。
「たら」「れば」-無価値感を埋める心理
基本的な欲求は、それが満たされないと、その欲求への過度の執着が生じるという性質があります。
自己価値感欲求も同じです。
自己価値感が満たされないと、強迫的な自己価値感への欲求が形成されてしまいます。
このために、基底的自己無価値感を、状況的自己価値感で埋めようとする心理がうまれます。
したがって、基底的な自己無価値感を持つ人ほど、強迫的に状況的な自己価値感を獲得しようと躍起になります。
誰からも受け入れられることを求め、自分の力を誇示したがり、賞賛を得ることに執着し、嫌われることを極度に恐れるようになります。
しかし、こうして得られる自己価値感は、「・・・になったら」「・・・であれば」という条件付きのものです。
すなわち、「受け入れられたら」「愛されたら」「何々ができるようになったら」「成績が上がったら」「賞をもらえれば」「一流校に合格すれば」「痩せてスタイルがよくなれば」、そのとき、はじめて自分に価値が生じると感じられるものです。
ですから、幸せは、「いま、ここ」の自分にはありません。
いつでも「未来の、現在とは違う自分」に幸せを夢見ることになります。
これに対し本来の自己価値感とは、無条件性のものです。
自分の能力や容貌が劣っていようと、未熟だろうと、現在のあるがままの自分が受け入れられ、歓迎されているという実感です。
ですから、「いま、ここ」の自分に幸福があるのです。
関連記事
競争意識の過剰な人ほど自信がない
さて、こうした強迫的な自己価値感への欲求は、直接的な形態として表現されることもあり、偽装され、屈折した形態として表出されることもあります。
直接的な表現形態としては、次のようなものがあります。
・評価への過度の敏感性
・嫌われることへの過度の恐怖
・度をこえた努力
・旺盛な競争心
・強い顕示欲求
顕示欲求や競争意識の強い人は、一見すると自信がありそうに見え、そうした意識や行動は、自己価値感の強固さに起因するかのように思われます。
しかし、実際は逆なのです。
確固とした自己価値感がないために、決して負けられない、劣っている姿を見せられない、と思うのです。
そのため、過度に自分を顕示し、競争意識があらわになってしまうのです。
しっかりと自己価値感が確立している人は、人との比較で評価するのではなく、自分のなかの基準で評価します。
また、たとえ人と競争しても、それを楽しむ余裕があり、負けたとしても根底的な自己価値感に揺るぎはないので、ライバルをほめ称えることができます。
ことさら人に自分を印象づける必要性を感じないのです。
強迫的な自己価値感への欲求が偽装され、屈折した形で表現されると、次のような行動になります。
・努力しない
・競争しない
・評価に無関心を装う
・ひねくれる、強情になる、気分を害しやすい
・幼稚な態度を示して人への依存性が高まる
・頻繁な心身症的症状を呈する
いずれも表面的には自己価値感への欲求がないかのようですが、そうではありません。
このような人は、人並み、あるいはそれ以上の自己価値感への渇望があるのですが、自信がないためにあえてこうした行動をとるのです。
たとえば努力しないことは、自分の無価値さを感じる状況を避けている行動なのです。
努力しても成功できないという徹底的な自己無価値感に向き合わざるを得ない事態を、努力しないことで回避しているのです。
ひねくれることや強情になることは、それにより周囲の人を手こずらせ、自分の存在感を実感しようとする行為です。
幼さや病弱であることを示すことは、それにより周囲の保護や注目を引き出すことで、屈折した形で自己無価値感を埋めようとする姿なのです。
このように自己価値感を得ようとする人のそれぞれのスタイルが、その人の性格の重要な部分を構成します。
そして、人生とは、その人が自己価値感を獲得し、保持し、高めようとする行動の集成として理解することができるのです。