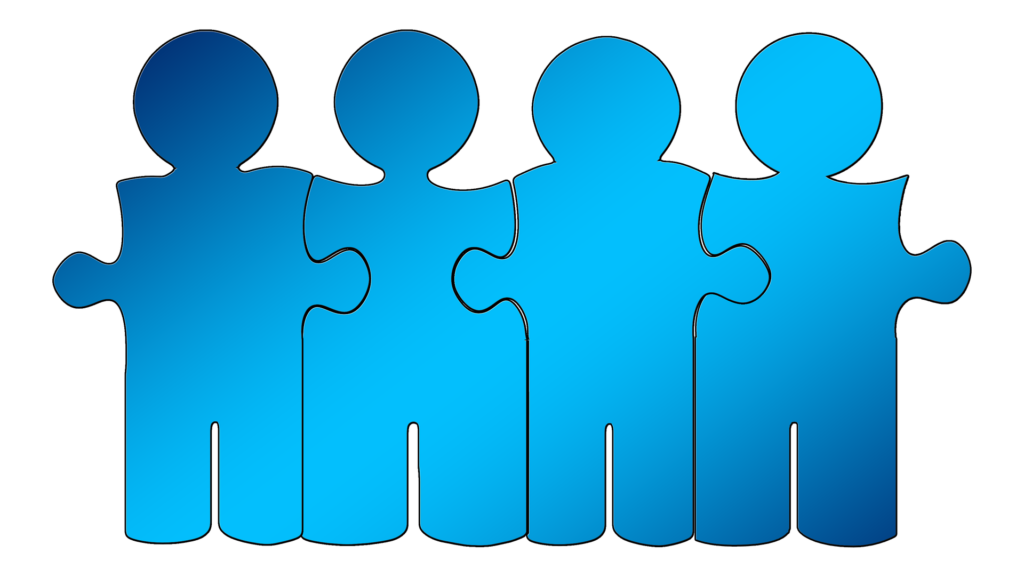褒めることは価値観を伝えること
人を育てる一番の方法は、褒めることです。
褒めれば、人は必ず伸びていく。
最近は子どもを育てるにも、学生を育てるにも、部下を育てるにも、「褒めなさい」とよく言われるようになりました。
だけど、ただ褒めればいいわけじゃない。
そもそも、「褒める」とはどういうことでしょうか。
一言でいえば、褒めるとは、価値観を伝えること。
褒めることで相手に「こちらの方向で合っているよ」「その部分を伸ばせばいいんだよ」というメッセージが伝わるのです。
つまり、教える側と教えられる側で一つの価値観が共有される。
逆に価値観が共有されていない状態では、育てられる側は何をどうしていいのかわかりません。
また、否定でも価値観は伝わらない。
「これじゃ、ダメ」と言われたところで、次にどうすればいいのかわからないのです。
たとえば、上司に何か提案をして「これじゃ、ダメ」と言われても、次にどうしていいのかわかりませんね。
心の中では「じゃあ、どうすればいいの?」と疑問が浮かびますが、たいていの上司は「自分で考えろ」と言うばかりだったりします。
ヒントもくれなければ、アイデアも何もないので、強がっているだけかもしれません。
ですから当然、褒める側が明確な価値観を持っていなきゃならない。
褒める側に軸がなかったり、軸がブレていたりする状態で「すごいね」「いいよ」と褒め倒しても、それは薄っぺらい「おだて」のしか映りません。
相手もバカじゃありませんから、気づきます。
「こういうふうにしてほしい」という価値観をきちんと伝えないで、何となく「これじゃ、ダメ」「なんか、違うんだよな」と否定されると、相手は途方に暮れてしまいます。
たとえば、これが部下なら「うるせえなあ」「じゃあ、自分でやれば?」としか思わないでしょう。
今どきの部下は育てにくいなんてことがさかんに言われるけれど、どんな部下も褒めながら共通認識を伝えていけば、いつか必ずいい方向に育っていきます。
片目をつぶって褒める。
相手の仕事ぶりをまずは受け入れて、自分の求めている方向に一番近い部分を褒めるのです。
褒めることによって、その部分が完璧に近づいていく。
最初五割だった出来が五割五分になる。
さらに別の部分を褒めていくというのを繰り返すと、最終的に7~8割は自分が望むように仕事をしてくれるようになるものです。
人を育てるのはとても時間がかかります。
ですが、褒め続けていれば、子どもでも、部下でも、人は必ず伸びていくものです。
日本人は褒めない理由
アメリカ人は、とにかく褒めて育てます。
子どもであれば、多少やんちゃがすぎようが、勉強が苦手だろうが、まわりと違っていようが、頭ごなしに否定はしない。
それを個性と捉えて認め、本人のよいところを探し出して褒めちぎります。
彼らは、「長所を見いだすこと」が、とても上手です。
アメリカに留学していた日本人から、「どうして(アメリカ人は)あんなに自信満々でしゃべれるんだろう?」と疑問の声が聞こえてくることがあります。
また時には「大したことを言っているわけでもないのに・・・」と陰口が聞こえてくることもあった。
思うに、アメリカ人の「自信」は褒められることによりついたのでしょう。
実際、英語には、日本語と比べて褒め言葉がとても多い。
「good」から始まって、「great」「amazing」「fantastic」「brilliant」「superb」「cool」・・・たくさんのバリエーションがあります。
反対に日本人には褒めて育てる習慣がない。
それはなぜかというと、肯定するより否定したほうが何となく偉そうに見えるからではないでしょうか。
とりあえず、批判や否定のスタンスをとっておけば、何だか威厳が保てる気がする。
自分が相手よりも格上の存在になったような雰囲気になるわけです。
とはいえ、日本人が全然人を褒めないかといえば、そういうわけじゃない。
褒めるところは、ちゃんと褒めている。
特にお母さん方は、子どもが三歳になるまでは非常によく褒めます。
なぜ、三歳になるまでなのか。
それは、お母さんの側に自分が三歳になるまでの記憶がないから。
0~3歳の自分がどんなふうだったか、お母さん自身が知らないのです。
ですから、「あの頃の自分は〇〇できたのに、どうしてこの子はできないの!?」とカリカリせずに、何をしても本能的に、無条件に褒められる。
いわば、子どもが三歳になるまでは「這えば立て、立てば歩めの親心」でいられるけれど、それより大きくなると自分と子どものあいだに比較が生まれてしまう。
人間というものは、自分がすごしてきた時間に対する思い入れが非常に強いのです。
育てる側にとっては「普通の育て方=自分の育てられ方」になるわけです。
もっと言えば、父親と娘、母親と息子といった異性の親子よりも、父親と息子、母親と娘といった同性の親子のほうが、この傾向は強くなります。
なぜなら、自分と同じ成長プロセスをたどってこの子も成長するに違いないという思い込みがあるから。
よく「一姫二太郎」と長子は女で次子は男がいいなんて言いますが、育児を母親が積極的やる場合は、案外むずかしいパターンです。
親子であってもDNAは半分しか共有していないのだから、別の人間です。
ましてや、先生と生徒、上司と部下ならばもっと違う。
比べたくなる気持ちをグッと抑えて、具体的に褒めるのがコツ。
具体的に褒めることがみつからない時は、「垂直比較」をしてみましょう。
「垂直比較」とは、身長が上に向かって伸びることから、作った言葉です。
子どもの身長を、今と一年前で比較してみると、必ず成長しているはずです。
同じように、子どもの今と一年前を比べてみると、上手にできるようになったことや、成長した点が必ず見つかります。
そのような点を見つけて、褒めることが「垂直比較」。
具体的にトコトン褒めてあげる。
そうすれば、どこかでスイッチが入ります。
また、褒めることは人間関係の上でもいいのです。
やっぱり、子どもでも大人でも褒められて「自分のことをちゃんと見てくれている人がいる」とわかれば、気持ちがいいし、もっと成長したいと思うものです。
■関連記事
自分の評価と客観的評価では世界が変わる
他人と比較せず、過去の自分と比較する
要は、人を育てる時に大切なのは、「水平認識」ではなく「垂直比較」なのです。
「水平認識」は、他人と見比べること。
いわば、横(水平方向)の比較です。
対して「垂直比較」とは、現在と過去を比べる縦(垂直方向)の比較です。
つまり、「本人の時間軸」において成長を見てあげる。
そうすれば、誰だって昔よりできることは増えています。
一番わかりやすいのが子どもの成長。
一カ月、二ヵ月・・・と順にさかのぼっていけば「ああ成長したな」と思える部分が見えてきます。
仮に三カ月前と比べて「成長してねえなあ」と感じても、半年、一年とさかのぼれば、絶対に何か見つかる。
オギャーとこの世に生まれたばかりの頃は、立てもしなかったのに今はしっかりと自分の足で歩いている。
ご飯も食べて、笑って、怒って、自己主張までしている。
そういうふうに見れば、まあ、腹の立つことはいろいろやらかしても、「しっかり成長しているんだなあ」と感じられるでしょう。
大人の場合もまったく同じ。
なかなか伸びない部下だって、入社当日から順に思い出していけば、多少は成長しているはずです。
それを踏まえたうえで、ちょっとでも伸びている部分を褒める。
人には誰でも「こういうふうにしたい」という方向性があるものです。
本人が望んでいるのだから、褒めて褒めて、その方向に伸ばしてやるのが一番いいに決まっている。
もし、左に行きたいと言っている相手を右に向けさせたかったら、どうするか。
ちょっとしたコツはあるけれど、やっぱり褒めること。
途中で左から右にぐにゅっとまげちゃえばいい。
ただし、相手が「自分で(右へ)曲げた」と思い込めるようにうまく伝えます。
間違っても、「左じゃない、右だよ」と言ってはダメです。
そのやり方では、決して右に向いてくれない。
「左もいいけど、行き過ぎちゃうと危ないから、もうちょっとだけ右に修正したほうがいいんじゃないかな?」なんて、何度か繰り返しているうちに、自分で納得して右に伸びはじめます。
とにかく、相手に「自分で決めた」を信じさせること。
それがミソです。
■関連記事
自分から発言すると楽になる
背中を見て覚えるじゃ育たない
褒めることには、本当に大きな効果がある。
なのに、日本人はその効果をイマイチ理解していないように思います。
これは大変もったいない。
たとえば、日本の職場で昔から上司が部下に向かって言うのが、「俺の背中を見て覚えろ」「盗んで覚えろ」。
上司はむっつりした顔で黙々と仕事をして、部下はその真似をするわけです。
日本企業の伝統的社員教育なのかもしれませんが、私に言わせればこれは「教育」じゃない。
普通に経験を通して身につけようとしたら何十年、何百年とかかることを数ヵ月、数年で圧縮して伝える。
これが教育です。
ですから、「俺が30年かけてやったことを、30年かけて身につけろ」というのは、教育ではないわけです。
特に、今のように伝えるべき情報が大量にある時代には、向きません。
「背中を見て覚えろ」は、世の中がゆっくりと変化していて、社会の知識量が少ない時代だったからこそ機能していた、「教育法」なのです。
特に仕事の現場では、褒めながら育てることで、仕事が「標準化」されるという効果がある。
標準化というと、ファーストフード店のスタッフ教育マニュアルを思い浮かべる人もいるかもしれないけれど、「標準化」はあれとは違います。
仕事の具体的な手順を決めるのではなくて、「この仕事は、こういう方向性で進めますよ。こういう考え方に基づいてやるんですよ」というふうに根本部分で共通認識を持てるようにすることです。
よく「日本人は共同作業が得意です」なんていうけれど、あれは違うでしょう。
一人ひとりが独自の手順で完結したことをやっているというのが実態で、日本はチームのメンバー全員がバラバラに仕事をする社会だと思います。
最もやさしい「自信の歯車」を見つける
ある塾講師は生徒数が定着せず悩んでいました。
「どうして辞めていくのだろう?」
講師は必死で考えました。
授業の内容やテキストには絶対の自信があった。
なのに、辞めたということは、生徒を飽きさせる何らかの要素があるのだろうな。
そして、「伝え方に工夫が足りなかった」という結論に至ったのです。
目をつけたのは「落語」。
講師は落語を聞きに通ったのです。
そして、毎日落語を聞くうちに、大きな発見がありました。
それは、うまい噺家は動くということ。
落語は扇子と手ぬぐいだけですべてを表現しないといけない。
財布から銭を取り出す様子、本を読む様子、それから蕎麦を食べる様子、ありとあらゆる動作を体と二つの道具だけで表現するわけです。
この「動き」の芸と話芸がうまくマッチしている噺家の話には吸い込まれていくのです。
二つがずれているとすぐに飽きてしまうし、つまらない。
終始ざぶとんに座っているように見えて、うまい噺家は体を上下左右に大きく動かして、観客の注意を引き続けます。
「よし、授業では私も動いてみよう」
そう決めて、自分が塾でしゃべっている声を録音し、自分の話を何度も再生しては、話の進め方を検討しました。
自分の声のトーンや大きさ、息の継ぎかたなど、細かいところまで研究し尽くしました。
当時はテープに録音するしかありませんでしたが、今なら簡単に動画を撮影できるので、それを見ると「知らない自分」を発見できるはずです。
以来、講師は授業中、教室を動き回るようになりました。
眠たそうにしている生徒がいると、スススッとその隣に移動して話します。
他の生徒の視線も動いて飽きることがないし、眠い人も先生がそばに来てプレッシャーになるから、一気に眠気が飛んでいきます。
緊張しないプレゼン術
プレゼンテーションは「中身」と「伝える力」で成り立っています。
まず「伝える力」において、緊張しすぎて自信がない人が少なくありません。
緊張しないようにプレゼンをできるようになるには、まず緊張を受け入れることです。
どういうことかというと、緊張しすぎても、声が震えても、過呼吸で途中で止まってしまっても、それを受け入れ、
声が震えながら、過呼吸になりながら、おどおど言葉を伝えていくことです。
それを繰り返すうちに、緊張する必要が無くなり伝える力が培われていきます。
「中身」は前日までにいくらでも準備できるのです。
用意した原稿をすっかり覚えてしまって、どんなふうに論理を展開させていくか、ビシッと頭に叩き込んでおく。
さらに「中身」の中心にあるのは「論理」です。
そして、「論理」は配布するペーパーやパワーポイントなどにまとめてしまうこと。
こうしておけば、伝えることに集中できるのです。
「論理」を作る時は、できるだけシンプルなほうがいい。
10分程度のプレゼンなら、キーワードは三つくらいで十分です。
それを一ページにデカデカと書いて、発表中ちらりと目をやった時に自分の頭の中の内容と結びつくようにしておきます。
そして、各ページの一番上には「ヘディング」を置く。
要は見出しです。
こうして余分をトコトン削ぎ落した「論理」を用意しておけば、よく伝わるプレゼンテーションができるはず。
「中身」と「伝える力」、そして「論理」。
この三つに分解して自分の話を組み立てる方法があります。
さらにいえば、プレゼンに対する質問にも準備をしておきます。
「きっと、こういう質問が出るだろう」という質問をいくつか想定しておいて、自分のなかで回答を組み立てる。
時には回答用のスライドを準備しておくこともあります。
時々「カッコイイなあ~!」と憧れる発表者がいますが、それは会場から出された質問に、「素晴らしい質問ですね」とニヤッとしながら、あらかじめ用意しておいたスライドを出す人。
やっぱりカッコイイです。
「伝える力」も「中身」にも人が知らないような、地味な努力が最後に実を結ぶものです。
聞く耳を持たせる方法
まず、日本人はとにかくパワーポイントの資料に内容を詰め込み過ぎる。
だから、伝わらないのです。
逆に言えば、相手が理解できるシンプルな「論理の構造」に載せてあげればちゃんと伝わる。
「伝えること」で大切なのは、相手を聞く気にさせること。
つまり、場の「空気をつかむ」、要は全員を聞く気にさせるわけです。
ちょうどいい目安が、一番うしろの席に目をやって自分の話にうなずいてくれる人を見つけること。
遠くまで自分の声が届いて、なおかつ内容が理解されているとわかるからです。
少し慣れてくると、演壇に立って、「私の声、聞こえますか?うしろの人、手を挙げてください」とやる余裕も出てくる。
いわゆる「つかみ」というヤツです。
英語では、それを「ジョーク・クラッカー」と呼びます。
まずは、ジョーク・クラッカーを爆発させて聴衆の意識と耳をキュッとこちらに向けさせるのです。
とにかく「つかみ」は大切。
どんなにいい内容も、聞いてもらえなければ意味がない。
前の日までにパワーポイントを全部用意して内容を頭に入れたあとは、「明日はどんな人たちが来るかな?その人たちにはどんな冗談がウケるだろう?」と徹底的に考えます。
そして毎回、参加者や観衆に合わせてジョーク・クラッカーの部分を少しずつ入れ替える。
年代や職種に応じて、それぞれに響くネタは違って当然。
ですから、できるだけたくさんのネタを仕入れておきます。
例えば、「易しいことを難しく言うのが大学教授で、難しいことを易しく言うのが落語家、私は落語が大好きなもので・・・」
こうして聴衆を聞く気にさせてから、本題に入ります。
的確な例えができるように、いろんなネタを参考にします。
もし、芸人に話を振られたら
TVにはニュースやバラエティ、スポーツなど、いろんなジャンルの番組がありますが、「伝える技術」において一番刺激を受けるのは、実は「お笑い番組」です。
「伝える技術」を学ぶのに、あれほど参考になるものはない。
特に落語は非常に高度な話芸です。
話だけで観客をグッと引き込んで飽きさせないのだから、あれは本当にすごい技術。
お笑いやバラエティ番組を見る時には、芸人さんがどんなふうに話を振って、どう受け答えしているのか、そのやりとりや展開をじっくりと観察します。
彼らは非常にサービス精神が旺盛だから、「相手に興味を持ってもらう」「わかりやすく伝える」術に長けている。
参考になる点が多いのです。
番組をチェックする際に、よくやるといいのが、立ち位置を変えた「想定問答」。
たとえば、「司会の明石家さんま役」、あるいは「さんまに話を振られる役」と、両方の役柄をシミュレーションしてみる。
「自分ならこうやって話を振るかな」とか「こんなふうに振られた時はどう答えようか」と、頭のなかであれこれ話の展開を広げてみるのです。
これは思考の練習にもなるし、視点を変えてシミュレーションすることで、それまで気付かなかったモノの見かたができるようになります。
これは、あらゆるシーンで役立ちます。
上司に怒られた時は、上司の視点でそれを検証してみる。
すると、「ああ、求められている役割がつかめていなかったな」とか「この部分はもっと早めに報告すればフォローを入れてもらえたな」と、気づく。
いろんな視点でものを見る練習をすることで、視野がはるかに広がります。
ぜひやってみてください。
「想定問答」が伝えるための予習なら、「ひとり反省会」はその復習。
ある教授は講義や講演をする時は、ICレコーダーをスーツの胸ポケットにいれて話を録音しておいて、あとで聞くようにしています。
自分で聞くと、「これじゃあ、伝わらないな」「自分にはこういう癖があるんだな」というのが、本当によくわかるのです。
毎回、自分の話を聞きながら、「ここはちょっとウケが悪いな」「次回はこんなふうに変えてみようか」とひとりで反省会をやる。
ビデオで撮影することもあります。
話と動作をチェックして、軌道修正を重ねていくわけです。
明石家さんまが、「自分の出たテレビ番組はビデオに録って全部見る」とよく言っている。
それを聞いてみんな「ナルシスト」だとバカにしますが、そうではないのです。
自分が聞いている自分の声と、他人が聞いている自分の声はまったく違う。
自分の声は体内の骨を振動させて伝わるので、空気を通して伝わる他人が聞く声とは、音質が異なるわけです。
だから、ICレコーダーで他人が聞くのと同じように自分の声を聞いてみると、すごく勉強になります。
たとえば語尾の発音。
特にメリハリをつけないで軽く流しながら話したい時は語尾を消して、演説風にはっきり伝えたい時は語尾まできちんと発音してから、そのあとにポーズを入れるといいわけですが、録音したものを聞くと語尾が上手に発音できているかよくわかります。
こういう小さな小さな軌道修正が、何年もすれば大きな差になっていくのだと思います。
わからないと言う勇気を持つ
アメリカ人は「伝える」努力を惜しみません。
これは、「伝わらないこと=わからないこと」に対して堂々と「わからない」と言える点が大きいと思います。
アメリカの社会が「わからない」とごく自然に言える雰囲気であるのです。
逆に言えば、伝え方がまずいと、あっさり「わからない」と言われちゃうから、アメリカ人は伝える努力を惜しみません。
言葉だけではなくて、態度でも相手にわかるように説明する。
これはプライベートでも同じ。
長年、連れ添った妻に対してさえ身振り手振りを交えながら、「I love you.」なんて、愛の言葉をささやく。
日本人からすれば、とてもこそばゆくてマネできたものではありません。
がんばってやったところで「具合でも悪いの!?」と言われるのが関の山。
そんなことは言葉にしないほうが男らしくて粋だ、という価値観もあります。
日本は、「1を聞いて10を知る」「以心伝心」の国だから、相手が伝え下手でも、端々にあらわれたわずかな言葉を拾い集めて、意図を汲もうとする。