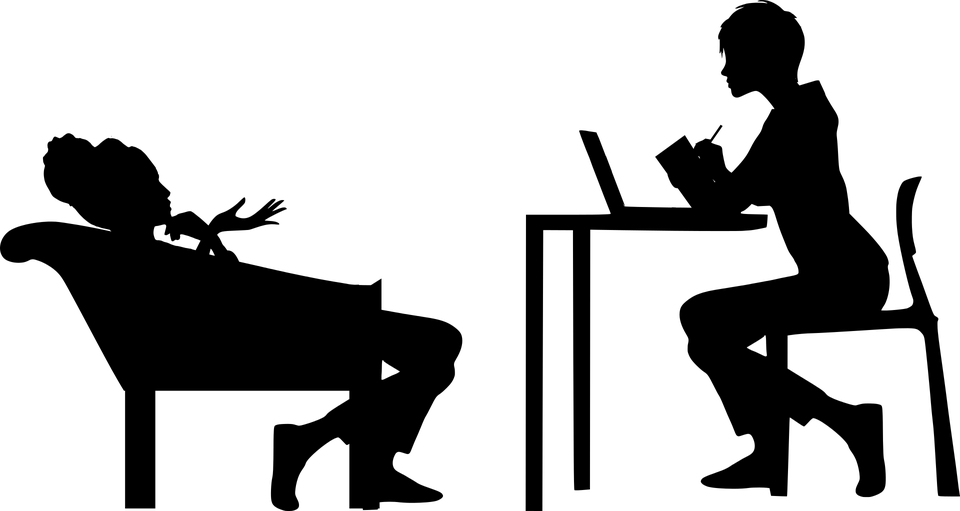無価値感に苦しむ人の多くは、自然な心の発露が許されず厳しく育てられた、と語る。
しかし、なかには愛情を受けて育ったのに、なぜ、こんな自分になってしまったのだろうかと自分を責めている人もいる。
そんな人を念頭に置いて無価値感を形成する要因を考える。
生まれつき感じやすい人
かつては、性格形成において決定的な影響を及ぼすのは、養育環境だと考えられていた。
しかし、現在は、行動遺伝学、脳神経学、生理心理学、乳幼児期の発達心理学、双生児研究等々により、生得的要因の影響が意外に大きいことが明らかになっている。
むろん無価値感の遺伝などというものは存在しない。
しかし、無価値感につながりやすい生得的な素質は存在する。
その最大のものは過敏性である。
生得的過敏性を研究したアーロンは、この特質を備えて誕生した子どもをHSC(Highly Sensitive Child)と命名した。
HSCの幼児は、ちょっとした味の違いや室温の変化などでぐずりだし、大きな音や、まぶしい光にびっくりして泣き出す。
チクチクする服の感触を気にするようなこともある。
また、少し大きくなると、心の面でも傷つきやすく、心配性であったり、臆病であったりする。
さらに、細かなことに気がつくだけでなく、残酷さや不公平さ、無責任さなどにも気づきやすいという。
それだけに、HSCの子育てには特別に注意深い配慮と手立てが必要であると注意を促している。
HSCの比率は子ども全体の15~20%であり、その割合は男女で差がなく、また、人種によっても差が無い。
いかなる動物でも大胆な動物ばかりでは生き残れず、細かいことに注意が向くことでいち早く危険を察知し、慎重に行動することで危険を回避する働きをする仲間が必要である。
HSCの存在は、こうした種族保存の原理が働いているのではないかと考えられている。
実際HSCは敏感さの程度の違いではなく、質的違いとしてとらえられ、また、関連すると思われる遺伝子も見出されている。
かつてHSCであった人が大人になると、以下のような特質を持つようになる。
1.物事を深く考え、徹底的に処理する
このために、鋭い質問をするとか、いろいろと考えすぎて行動を起こすのに時間がかかるとか、なかなか決断できなかったりする。
過去のことをいつまでも引きずるようなこともある。
2.刺激を過剰に感受する
このために、精神的負荷が大きくなり疲れやすい。
旅行やイベントなど、本来楽しいはずのこともストレスになってしまう。
集団に参加するとか、人前で発表するなど、刺激の多い場面ではしりごみし、実力を発揮できない。
たとえ発揮できてもひどく疲れてしまう。
3.感情反応が強く、共感力が高い
物事を深く感じ取るので、人の気持ちを読み取る力や、共感する能力が高い。
また、感情が喚起されやすく、心が動揺しがちである。
fMRI(磁気共鳴機能画像法)を用いた研究では、そうした機能を担う脳の部位の働きが活発であることが明らかにされている。
4.ささいな刺激を察知する
これは感覚器の敏感さというよりも、思考や感情のレベルが高いことに起因する。
たとえば、会話のちょっとしたニュアンスや声のトーン、目の動きなどに敏感に意味を感じとる。
この能力は有利に機能することもあるが、刺激の過剰負荷をもたらしたり、相手の心を読みすぎたりするなど、不利に働くことが少なくない。
こうした繊細さのために、集団活動が苦手で、友達との関係にも困難を抱えることがある。
無価値感に苦しんでいる人は、これらの特徴はまさに自分のことだ、と思い当たるのではないだろうか。
■関連記事
生きづらさを引き寄せる無価値感
生きる自信がない無価値感の克服
成長してから自信を失う無価値感
無価値感を乗り越える視点
親の愛情の問題ではない
多くの場合、子どもに無価値感を持たせてしまうのは、親の愛情の欠如のためではない。
愛情があっても無価値感をもたらしてしまう状況はいくらでもある。
そうした状況の一端を述べる。
兄弟関係
新たに生命が誕生すると、それまで自分に一身に集中していた親の関心と献身は、新たな弱い命の方に向けられる。
このために、上の子は自分が見捨てられたかのように感じる。
このとき、「赤ちゃん返り」することで、自分への関心と献身を取り戻そうとすることはよく見られる現象である。
上の子の気持ちに共感し対応してあげることで、子どもは親の愛情を分け合うという状況を受け入れ、弟や妹への愛情を表現するようになる。
しかし、上の子がこの状況を受け入れるには幼すぎる場合には、親の愛を下の子と争ったり、下の子をいじめたりすることがある。
それで、叱られたり、拒絶されたりすることが多くなり、自分を否定的に感じてしまう。
「お兄ちゃんなんだから」「お姉ちゃんなんだから」ということで我慢を求めるしつけは、比較的大きくなってからも続く。
気持ちが落ち込みやすいという女子学生は次のように書いている。
「長女なので、親の目が妹の方にいってしまうと十分な甘えが得られなかったのだと思う。
それで、すねたりすることで自分の方に目を向けてほしいというメッセージを出していたのかも知れない。
その結果、自分ばかりに目がいってしまい、周囲の現実に目を配る余裕がなくなってしまった。」
こうした構図は、心身になんらかのハンディを持つ兄弟が存在する場合、いっそう顕著になることがある。
親の関心と献身がハンディを持つ兄弟に集中せざるを得ないからである。
子どもの性
親が望んだ性でないために、子どもが無価値感を持つ場合がある。
「上二人が女の子。それで”また女の子”と言われることが多かった。
このために、自分が女であることに申し訳なさというか、負い目を感じていた。
父親に叱られるたびに、家族にとって自分は不要な人間だ、と感じた。」
母親は、女の子よりも、男の子の世話を焼き、男の子に献身することが多い。
このことが、女の子が自分を肯定するのに不利に作用することもある。
「私を近くに住む祖母に預けて、母はサッカーや水泳など兄の方に付き合っていた。
それで女の子ではダメという思いがあり、男の子っぽかった。
”男の子みたい”と言われると嬉しかった。」
親と子の不適合
子どもにとって母親とは適応しなければならない最初の対象であり、また、最大の対象でもある。
逆に、母親もまた子どもに適応しなければならない存在である。
両者の性格によっては、この適応が容易な親子もいれば、困難な親子もいる。
「上の子はわかるんだけど、下の子はどうしても理解できない」と語る母親がいるし、「この世で一番適応するのが難しいのが母親」と語る人もいる。
細かいことにさほど拘泥しないさっぱりした性格の母親に対して、大多数の子どもは適応が容易であるかもしれない。
しかし、過敏な子どもや内省的傾向の強い子どもにとっては、そうした母親の対応は細やかさに欠けるものであり、不適合の感覚がもたらされる。
親の共感性
子どもが誕生したために、自分のキャリアをあきらめる母親がいる。
こうした母親は一般に優秀で、社会的地位へのこだわりが強く、自分の願望を子どもに投影しがちである。
この場合、愛情を持って子どもに関心を向け、十分すぎる献身をするけれども、子どもへの共感が不十分なことがある。
「母が何かほかのことに気を取られていることをいつも願っていました。
カレンダーに母の外出予定があるとその日が楽しみでした。」
親もまた、いろいろな葛藤や心の傷を持っている。
その葛藤や傷を刺激するような性質の子どもは疎まれがちである。
たとえば、劣等感の強い未熟な親は、子どもに劣等感を刺激されると不機嫌になり、子どもへの共感性を忘れる。
関連記事
「お前は無力だ」「ダメだ」というメッセージ
過保護・過干渉の影響
無価値感や自信のなさに悩む人の中には、「自分は過保護とも思えるほど親から大事にされていたのに」と言う人が含まれる。
大方の見方に反して、過保護は自己価値感よりも無価値感をもたらしやすいのである。
過保護・過干渉はセットで述べられることが多く、両者が子どもに与える影響には共通する部分が多い。
しかし、異なる部分もある。
典型化して言えば、過保護は「お前は無力だ」という暗黙のメッセージを送り、過干渉は「お前のままでは駄目だ」というメッセージを送る。
このために、過保護は子どもを無力化することで無価値感をもたらし、過干渉は子どもの自我を奪い取ることで無価値感をもたらす。
健全な心の発達とは、子どもが生得的に持っている健康に成長していく力(内発的成長力)により達成される。
だから、内発的成長力が発現する環境を与えてあげれば、子どもは自らのびのびと成長していく。
この子どもの内発的成長力を信頼できない親が過保護・過干渉になるのである。
親が子どもを信頼できずに日々対応するのであるから、子どもが自分を信頼できるわけがない。
自分を信頼することこそ自信の本質なのであり、子どもは自信が持てず、自分を無力な存在であると受け止めざるを得ない。
その上、過保護・過干渉により子どもが自らの力で外界に対処する機会が奪われ、外界への対処能力の発達が妨げられる。
こうして、「自分が無力である」という思いは、現実の体験によって裏付けられてしまう。
過保護はいつでも何らかの形の過干渉と結びついている。
子どもの感覚や感情を親が先取りし、子どもが感じないことを感じさせ、欲しくないものを押しつけるからである。
「お腹すいたでしょ、これ食べなさい。」
「寒いでしょ、もう一枚着なさい。」
「プレゼントもらって嬉しいでしょ。お礼を言いなさい。」
親が先回りして欲求を満たしてくれ、親が先回りして感情を言語化してくれる。
そればかりでなく、親の感覚、感情、欲求を受け入れ、それに従って行動するよう求められる。
このために子どもは、自分が感じているもの、自分の感情、自分の欲求を、生身の自分の感覚として体験しないままに済んでしまう。
こうして、身体感覚、感情、好みさえ希薄化していく。
「お腹が空いた」とか「疲れた」ということが、本当はどんな感覚なのか子どもの頃わからなかった、という人がいる。
大人になっても、「本当は何が好きなのか」、「本当は何をしたいのか」わからない。
「嬉しい」「楽しい」「幸せ」といった感覚が、本当はどんなものなのか、確信が持てない。
「自分」とは、感覚、感情、欲求、願望そのものである。
だから、上記のような状態とは「自分」という実感が希薄であることであり、これが「自分がない」とか「透明な自分」などと表現される状態である。
子どもを導くという危うい高揚感
過保護・過干渉な親は、それによって自分を支えていることが多い。
「この子のために自分はこんなに尽くしている」
「自分がこの子に必要とされている」ということで自分の価値を実感できるからである。
さらに言えば、子どもを支配している自分の力への満足感や、自分がこの子をよい方向に導いているのだという自己高揚感も得られる。
このように、過保護・過干渉は、見かけ上は子どもに依存させることであるが、実際には親が子どもに依存している状態である。
親は、過保護・過干渉を受け入れてくれる子どもを必要としているのである。
こうした環境では、子どもは成長することや自立することは、親の愛と保護を失う恐れと結びつく。
このために、無力なままにとどまろうとする心性を形成する。
過保護・過干渉により無力化されて育てられたために、親に世話を焼かせる以外に、親の愛を得る方法が身に付いていない人がいる。
そうした人は、無力さを演じることで、自己価値感を得ようとすることがある。
すぐ拗ねる子、転んで怪我ばかりする子、しょっちゅうけんかする子、頻繁に体調を崩す子、非行で親を悩ませる子、借金を作ったり、仕事を転々としたり、異性問題を繰り返したりして、いつまでも大人になりきれない人等々。
親はこうした子どもを愚痴るけれども、心の隅ではこの関係を歓迎していることが少なくない。
優しくいい子の悲劇
愛情深く良心的な母親は、早い時期からしつけをしがちである。
しつけることとは、親の感覚、感情、考え方が、子ども自身のそれらよりも大切なのだと強要することである。
このために、親の願いとは裏腹に、子どもは自分が無価値だという感覚を持ってしまう危険がある。
自分を大切にするという姿勢を身に付ける前にしつけられると、エリクソンの言う「早熟な良心」が形成される。
早熟な良心とは、自分を大切にすることをないがしろにして、期待される「良心的」行動に埋没してしまうことである。
いわゆる「いい子」として表現されるのはこうした子どもである。
たとえば、親は子どもに優しさを育てようとする。
思いやりの心を持つように求める。
ぬいぐるみを抱っこしているのを見て、「抱っこさせて」と友達が手を伸ばしてきたとき、子どもは一番のお気に入りで大切なぬいぐるみなので「イヤ!」と拒否する。
すると、母親から「貸してあげなさい。友達には優しくしないとだめよ」と言われる。
逆に、自分の本心とは裏腹な「優しさ」を示せば褒められる。
子どもは「自分にとって大切」ということは、「優しさ」ほどの価値はないのだ、と受け止めざるを得ない。
こうして早すぎる良心は、自分を無くして他者に奉仕する「厳格すぎる良心」へと発達していく。
厳格すぎる良心とは、いつでも他者の快適さを優先して自分を犠牲にしなければならず、自分を大事にしようとすると罪責感にとらわれてしまうような心である。
メサイヤ・コンプレックスと呼ばれるものは、こうした心理の一種である。
それは、自分を無にして他の人のために尽くすことによって初めて自分の価値を実感できる心理である。
そうした人のなかには、社会的奉仕活動など崇高な生き方をする人が少なくないが、この心性につけ込む人に利用され、悲劇的な人生を送る人もいる。
早期教育は無駄?
わが子に早期に教育的環境を与えてあげようとするのは、親の愛情である。
ところが、親の愛情や意図とは反対に、有能感や自信よりも無力感や無価値感を育ててしまう恐れがある。
現在の子どもは徹底的に遊ぶことよりも、習い事を中心に生活が回っているかのような例が少なくない。
厚生労働省が2001年に生まれた子どもを追跡調査している「21世紀出生児縦断調査」によれば、すでに2歳半で14%の子どもが習い事をしており、三歳半で23%、4歳半で38%、5歳半では56%を超える。
習い事は、「できるようになった」という表面的な自信、すなわち、状況的自己価値感を子どもに与える効果があるかもしれない。
しかし、習い事とは、外的基準に自分を適合させることを求められることであり、今の自分では駄目なので、外の基準に合うよう自分を変えないといけないのだ、という深い信念を植え付けてしまう恐れが強い。
習い事のためには、子どもは遊んでいたいのにそれを中断しなければならない。
習い事を継続するには子どもも親も相当な努力と犠牲を要する。
しかし、その努力はほとんど報われないこともある。
たとえば、内田伸子の研究によれば、読み・書きを早めに習得させたことで幼稚園の年長のときには読み書き能力が優れていても、その優越性は1年生の9月には消失してしまうことが明らかになっている。
また、杉原隆らの一連の研究では、運動指導をすることが多い保育園・幼稚園の子どもほど運動能力が劣る、という驚くべき結果を得ている。
自由に思い切り体を動かして遊ぶことで、子どもの運動能力は高まるのであり、幼児の心身の発達とは遊ぶことを通してこそ達成されるのである。