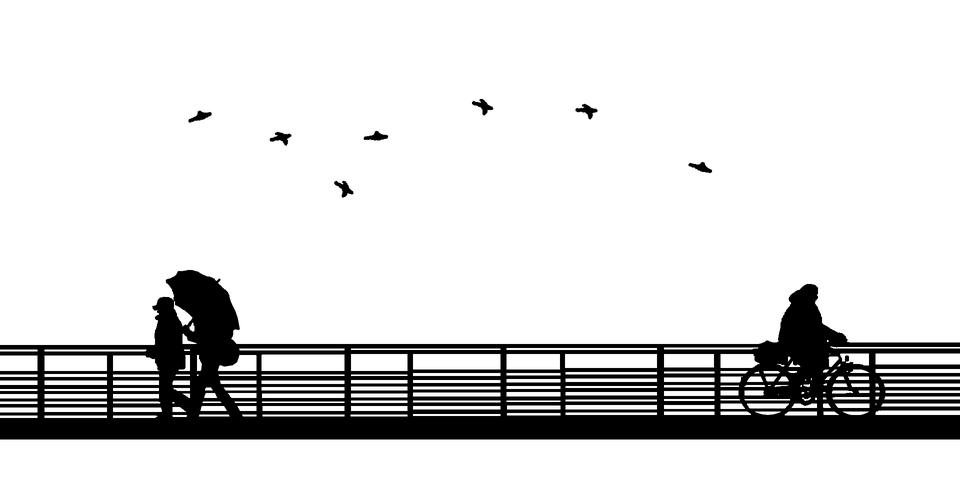よい子の悲劇とは
ニューヨークの精神分析医、ウェインバーグの著書に、イレーネという女性のエピソードが出てくる。
イレーネは両親にとって最初の子どもだった。
彼女はとくに父親に可愛がられて育った。
彼女が五歳になった時、弟が生まれた。
もう彼女は以前ほど、皆にかまってもらえない。
幼いイレーネは、両親の関心が弟のほうに移っていくのを見て、愕然としてしまう。
傷つきながらも、彼女は何とかして父親の愛情と注意を取り戻そうと、試行錯誤を始める。
まず、カンシャクを起こしてみる。
しかし、そんな彼女に対する父親の態度は厳しい。
今度は、病弱でかよわい小さな女の子のように振る舞ってみる。
これも効果はない。
そこで再び作戦を変え、今度はよくお手伝いをするよい子になってみた。
するとどうだろう、父親が彼女に微笑みかけてくれたではないか。
これがイレーネが「よい子」を演じるようになったプロセスである。
人は誰でも、試行錯誤を繰り返して、自分の欲しいものを手に入れる方法を探し続ける。
人間の行動に対する動機は、二つの要素から成り立っている。
目的と信念である。
イレーネの場合、目的は「父親に認めてもらうこと」、信念は「役に立つこと」であった。
いたずらをして自分を誇示したり、泣きわめいたり、弟と競争したりというイレーネの試みは、いずれも失敗に終わったが、ついに父親に近づく道を発見した。
それが、父親の役に立つ「よい子」になることだった。
人にとっては、子どもの時からずっと首尾一貫した姿勢でいることのほうが容易である。
だから、幼い頃にいったんある行動パターンを選び取ると、成長してもそれをそのまま引きずることになる。
イレーネの場合、その後、男に奉仕する女性となっていった。
二十歳になったイレーネは、ある男に恋をした。
彼女は彼を失うことを恐れる。
彼女は自分のことを何の価値もない人間だと、心の底で確信している。
だから、彼に向かって異論を唱えたり、不平を言ったり、何かを要求したりはしない。
その代わりに、彼女は毎晩愛する彼のためにいそいそと料理をつくり、原稿をタイプしてあげたりしてつくす。
彼女は彼との関係に、幼い頃の自分と父との関係をあてはめたのだ。
彼女は恋人の役に立たなければ、捨てられてしまうと感じているのである。
こうして彼女は自分の負担を増やしていく。
イレーネは懸命に彼につくしたが、やがて二人は別れを迎えた。
それから数年後、彼女は彼の夢を見た。
夢の中で彼女は、彼への怒りでいっぱいになって目が覚めた。
驚いたことに彼女はそれまで一度も、自分を粗末に扱っていた彼に対して、腹を立てるということさえ自分に許していなかったのである。
彼女はまた新しい男に出会う。
そして、また彼を満足させるべく努めることを誓うのである。
こうして彼女は、自分を侮り、食い物にしようと狙う男たちの、格好の餌食になってしまう。
よいことをすれば褒められる方式の罠
小さい頃を思い出してみよう。
誰でも家の手伝いをしたりして、ほめられた経験があるはずだ。
弟の世話をすると褒められる。
庭の掃除をするとほめられる。
親の虚栄心を満たした時も同じだ。
成績がいいと親が嬉しがる、運動会で優勝すると親が喜ぶ。
自慢の種になると可愛がられる。
しかし、ここには問題がひそんでいる。
そのように親の役に立つ時だけ、親の虚栄心を満足させた時だけ、ほめられると、子どもはそうでない時の自分は意味がないのだと感じるようになる。
役に立たない、自慢されない自分は、愛されるはずはないと思い込んでしまうのだ。
だからいつも、親を嬉しがらせることで認めてもらおう、可愛がられようと努めることになる。
この傾向は、大人になるにつれ、さらに拡大されていく。
人に愛されるためには、相手の虚栄心を満足させなければならない。
何か相手の役に立たなければいけないと思い込む。
ただ一緒にいることがお互いに意味があるのだ、ということが理解できない。
それでは何か落ち着かない、相手に申し訳ないような気持ちになってしまうのだ。
このような人の困った点は、自分は役に立ち「さえ」すれば相手に気に入られるのだという確信を持ってしまっていることである。
子どものうちはまだよいが、問題は大人になって周囲の人が変わった時である。
それでもその人は自分が気に入られるためには、相手の役に立ちさえすればいいのだと思う。
そしてひたすら相手のためになにかをしてあげようとする。
しかし、相手がいつもそのようなことを望んでいるとは限らないのだ。
こんなにも尽くしているけれど反応が薄い
たとえば、子どもの頃よく家の手伝いをしてほめられていた人が、大人になって結婚したとする。
その人は、やはり家のことをしさえすれば、配偶者に気に入ってもらえると思い込んでいる。
だが一方、配偶者がそのようなことより、一緒にどこかへ出かけることを望んでいたらどうだろう。
相手の情緒的成熟を望んでいる、あるいは楽しむ能力を期待する、一緒に音楽会に行きたい、一緒に酒を飲みたい、いろいろ生きることを一緒に楽しんでいきたい、というように。
しかし、配偶者のこの希望が、理解されることはまずないだろう。
なぜならこの人は、家のこと「さえ」していれば配偶者に気に入られると確信してしまっているからである。
ところが配偶者は喜んでくれない。
そこで何かおかしいと気づけばまだいいが、たいていの人は、気に入られるためにもっと精を出して役に立とうと頑張ることになる。
相手の好意が欲しいから一生懸命つくすのに、その効果がない。
するとそこで怒りだす。
「私がこんなにつくしているのに」
「俺がここまで犠牲になって家のことをしているのに、何でお前は・・・」
というわけだ。
どうして自分がもっと気に入られ、評価されないのか理解できない。
そして不満を感じ、相手に面白くない感情を持つようになる。
人間関係をうまくやるためには、ただ単に相手の役に立とうとするだけではなくて、自分が心理的に成長することが必要である。
見返りを期待してするのでなく、純粋に相手の役に立つことが嬉しくなれば、相手にも好感を持たれ、時には感謝される。
自然と人間関係もうまくいくようになる。
しかし心理的に未成熟な人が、気に入られたい、評価されたいという動機から相手の役に立とうとすると、どうしても恩着せがましくなる。
それでは、相手も何となく不愉快なだけである。
自分がこんなにしているのだということを、誇示されるからである。
隠された神経質な愛情要求
ひたすら相手の役に立とうとする人は、それが気に入ってもらうための切り札だと思っている。
相手につくすことが、評価され、気に入られるためのオールマイティーだと信じているのである。
たしかに、自己中心的な親に育てられた人にとっては、それは真実である。
自己中心的な親は、子どもが自分の役に立ち、何か自慢の種になることだけが嬉しいのである。
それだけにその人は、いつも相手の役に立っていないと罪の意識を持つことになる。
相手の役に立っていないと、罪悪感に苦しめられる。
人といても、リラックスできない。
リラックスすることに罪悪感を覚えるからである。
不幸なことにそのような人は、罪悪感に苦しめられるようなことをしている時に、人から好感を得るということさえある。
周囲の人は、その人に自分の好きなことをしてもらいたいと思っていることもあるからである。
このように人を喜ばそうと努めるのは、何度も言うように、相手に気に入られるためである。
その意味ではこれは外面なのである。
そして隠された内面は、実は神経質な愛情要求である。
神経質な愛情要求を心の底に宿しながら、気に入られたいがために必死で人の役に立とうとする。
しかし、時にはこの努力もなかなか成功しないことがある。
そうなると本人はいよいよ追い詰められていく。
人間関係が破綻していくのだ。
よい子の心理
素直で明るいよい子は精神的な自虐者
人間の自己実現について、深い研究をしたアメリカの心理学者マズローは、その著書の中で次のようなことを言っている。
子どもは自分自身の喜ばしい経験と、他人からの是認の経験とどちらを選ぶかという時には、たいてい他人からの是認を選ぶ。
そして自分の喜びの感情は殺す、あるいは目をそらす。
小さい子にとって、周囲の人の心を失うほど恐ろしいことはないからだ。
そしてそれらの子どもは人知れず精神的死をもって人生が始まる、と。
つまり、「明るく素直なよい子」とは、精神的死をもって人生を始めた人たちなのである。
自分の内面を信頼できない子どもは、親を喜ばすことによって、自分を認めてもらおうとする。
親を喜ばせれば自分は賞賛されるということを学び、この態度を大人になっても持ち続ける。
たしかに、人を喜ばそうとすること自体は悪いことではない。
しかし、その動機が、相手から認められ、賞賛されたいということによるものだと、問題が生じてくる。
マズローの言葉を使えば、「成長動機」から人を喜ばせようとすることはよいが、「欠乏動機」からそうしようとすることは好ましくない。
それは間違いであるという。
ここでいう成長動機とは、基本的欲求が満たされ、自己実現の欲求に動かされることである。
反対に欠乏動機とは、安全、所属、親密な愛情関係などの基本的欲求が欠乏している時に、それを満たそうとする動機である。
したがって、人の心を失うことを恐れて、自分の本性を裏切るなどといった行動は、欠乏動機によるものといえる。
またマズローは、子どもの場合、人から受ける賞賛と自己への信頼感とは対立すると言う。
人から賞賛を得ようと努力すればするほど、自分を信頼することができなくなるのだ。
これと同じことをカレン・ホルナイは、「他人に迎合することの結果は、自分を頼りなく感じることである」と言っているし、ロロ・メイも、次のように述べている。
「われわれがだれか他人の賞賛を目当てに行動するとき、その行動自身は自分に対する弱さと無価値さの感情をそのまま思い出させるものである」
とくにロロ・メイは、このような態度は人間にとって最もひどい屈辱であり、それは臆病な気持ちにつながる、とまで言っている。
しかし、情緒的に未成熟な親のもとで育った人は、他人のお気に入りになることこそが、人から認めてもらう方法だと信じてしまう。
ありのままの自分では、誰も好きになってはくれない、そう思い込んでしまうのである。
こうして自分を偽り始め、ついには実際の自分がわからなくなってしまう。
心理療法の技法の一つ、交流分析では、”Don’t be you”(あなたであってはならない)という言葉を、「親が子どもの心を破壊するメッセージ」として取りあげている。
「あなたであってはならない」とはすごい言葉であるが、これは考えてみると、マズローが言っているのと同じことを指しているのではないだろうか。
子どもは親に気に入られるために、自分にとっては喜ばしい体験さえも否定してしまう。
親のお気に入りの言葉を使い、お気に入りの態度をとらなければ、親はひどく不機嫌になるからだ。
これはまさに「あなたであってはならない」というメッセージそのものであり、子どもは自分の感じ方、考え方を断念するようになってしまう。
自己喪失である。
子どもはとにかく、親が気に入る特性を身に付けなければならないのである。
親が気に入る特性を身に付けた時にのみ、愛される。
親の自己陶酔のために、愛されているのである。
そのように育てられた人は、どうしても心理的に不安定になる。
成功している時のみ、相手が気に入ることを言っている時のみ、愛されるのであるから、逆にいつ相手から見放されるか判らないと感じている。
その結果、周囲の期待に敏感になり、自分自身の願望は押さえつけてしまう。
こうして相手の気に入る人間になろうと努力すればするほど、自分に対する信頼感は失われていく。
怖くてたまらないからよい子を演じる
人が自分の本性に逆らう罪を犯すと、それは例外なく無意識のうちに記憶され、自己蔑視の念をかきたてる、とマズローは述べている。
自分の本性に逆らって気に入られようと努力する場合も、どうしても自分で自分を軽蔑してしまう。
それによって、傷つきやすくなるなど、さまざまな病的な心理傾向が表れると言う。
「よい子」を演じる子どもは、いつも親の愛を失う不安を持っている。
愛を失うことを避けるために、彼らはよい子であろうとする。
見捨てられたくないから、誰よりも強く、優れていようとするのだ。
彼らにとってよい子であることは、親からほめられるための手段でしかない。
本当の自分、実際の自分であったら親はほめてくれないであろうと感じているのだから、よい子を演じることは、実際の自分、本当の自分を軽蔑することにつながっていく。
あるいは本当の自分に罪の意識を持つようになる。
そうなると、ますます「よい子」はいつもほめられていないと不安になる。
実際の自分を蔑視するようになればなるほど、賞賛を必要とするのだ。
そこで前にもまして親の顔色を窺い、その承認を心理的に求めるということになる。
虚栄心やナルシシズム的傾向を持った子どもは、いつも親にほめられていないと、自分は価値がないものと感じるようになる、とロロ・メイは述べている。
だが、それは何もそんな特別な子どもに限ったことではなく、一般によい子は皆そうである。
いつもほめられていないと、自信を失ってしまうのである。
我が子を精神的奴隷にする親
相手の期待する特性を備えている時のみ愛される、ということによって起きる悲劇はこれだけではない。
そこにはいつでも捨てられる可能性もあるということである。
心理的に成長していない親、情緒的に未成熟な親、欠乏動機で行動する親、それらの親にはたとえどれだけつくしても、彼らにとって役に立たなくなれば、その子はすぐに見捨てられる。
期待に沿わなくなれば、子どもはいつでも見捨てられるのである。
自分の欲求を満たす相手がいれば、それはいつでも代えられるということである。
これは当事者にとっては大変な悲劇である。
当事者とはこの場合、子どもである。
今述べたように、どれだけ自分を犠牲にして親のお気に入りになっても、親の期待する特性を失えば、子どもはすぐに見捨てられてしまう。
すぐに別の子どもが「愛」を獲得する。
そしてその子が、親のお気に入りの役を演じ始める。
親に必死になって迎合している子どもは、彼らのお気に入りになった時に、「自分が」気に入られたのだと錯覚してしまう。
自分はいつでもほかの子どもに置き換えられる存在に過ぎないということに気づかない。
欠乏動機で動く親にとって必要なのは「精神的奴隷」であって、その子自身ではないということが理解できない。
その子がいなくなっても、別の子が親を賞賛するようになれば、その子は忘れられる存在でしかない。
親が求めているのは自分を尊敬してくれたり、欲求を満たしてくれる相手であって、その子どもそのものではないのだ。
親にとって都合のよい存在として求められる子どもとは、奴隷以上の存在ではない。
親の欲求を満足させてくれるものであればいいのだ。
また、子どもは決して文句を言ってはならない。
都合が悪くなれば、いつでも捨てられるからである。
精神的奴隷とは、何も親を賞賛することだけではない。
要するに親にとって都合のよい存在であればいいのだ。
たとえば父親に愛人がいるとすれば、その秘密が母親にばれないように動くというようなことも期待されるのである。
親子の関係で最も密接なのは共生関係であろう。
お互いに自立性を犠牲にして成り立っている関係である。
親から押しつけられた考えや感情を忠実に守り、二人で閉ざされた世界に生きる子どもに多い。
このような関係にある子どもは、まさか自分がいつでも代えられる存在だとは思っていないだろう。
しかし、共生関係はやはり本当に触れ合っている関係とはいえない。
お互いに一人の人間であることを放棄している以上、どんな密接に見えても、そこに心の触れ合いはない。
共生関係にあるもの同士が、何かの事情で別離するということも起きる。
たとえば親子で共生関係にありながらも、子どもが心理的に成長して親と別れようとする。
無意識のレベルで抑圧していた親への敵意が意識化されてくるからである。
こうして、親と別居するなどということが起きてくる。
その時、子どもは家を出て行くという自分の行動が、親に心理的打撃を与えると思う。
共生関係にあると、相手から自分はすごく愛されていると錯覚するからだ。
相手と自分が別れることは、相手にひどい打撃になるに違いないと思う。
しかしそれはまったくの自惚れである。
というのは、共生関係にある相手は、またすぐに誰か別の人を見つけてしまうからである。
つまり、共生関係というのは、相手を愛しているから成り立っているという関係ではないのだ。
もし誰かまた心理的に依存する人ができれば、今までの相手のことは忘れてしまう。
心理的に成長すると、相手にとって自分はどのような意味を持つ存在かということが、理解できるようになる。
その点、共生関係にある人はやはり成長していない。
相手にとっての自分の価値が理解できていないのだ。
相手にとって自分は交換可能な商品のようなものなのである。