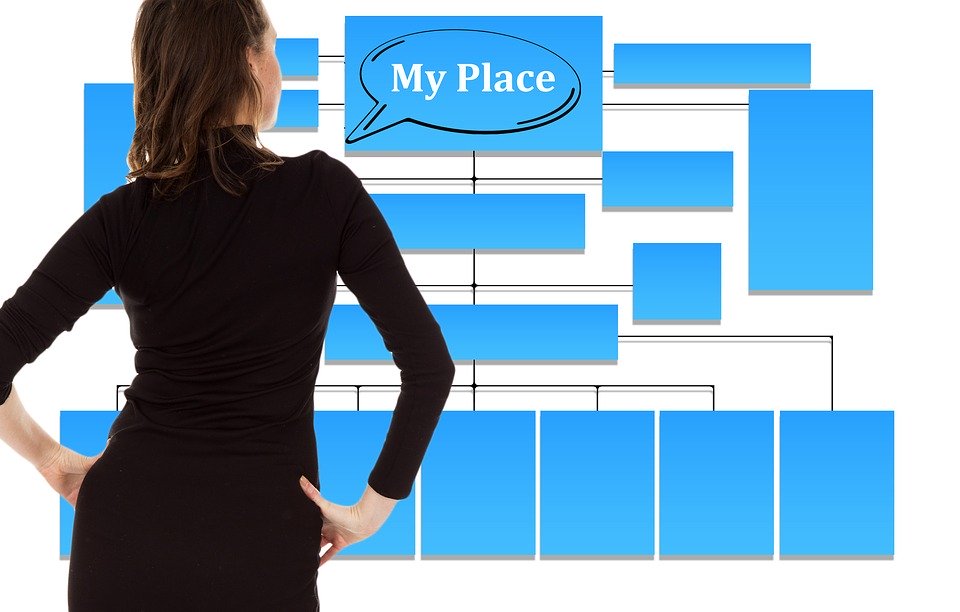自己物語の破綻
モラトリアム時代の倦怠感
モラトリアムの時代と言われるようになって久しい。
モラトリアムとは、もともとは支払猶予期間という意味の経済用語であったらしいが、精神分析学者エリクソンが心理・社会的モラトリアムというように心理学用語に転用した。
心理・社会的モラトリアムとは、社会的な責任や義務を免除された形で青年たちがさまざまな役割実験を試みる期間であり、大人になって社会の中に自分の居場所をみつけるための準備期間である。
つまり、「自分とは何か?」という問いに対する答であるアイデンティティの決定を猶予されていることをさす。
この猶予期間の社会的遊びの中で、自由に役割を選択したり変更したりしながら、自分に最も適した社会的役割を探し出し、身につけていく。
モラトリアムとは、そのための試行錯誤の期間のことだ。
現代は、家業を継がなければならないという時代でもないし、学校を出てすぐにどこかに就職しないと食べていけないという時代でもない。
個人の自由が尊重される時代の空気と、フリーターでも食べていける豊かな時代の価値観を背景に、学校を終えても就職するわけでもないし、結婚するわけでもないという人たちが増えている。
仮に就職したとしても、ほんとうにやりたいことはまだ他にあるはずと信じ込んでいるかのように、自己定義を可能なかぎり先延ばしにする傾向が、ますます広まっているように思われる。
今ただちに自己定義しなくてはならないとしたら、自分が思い描く理想からかけ離れていようと、とりあえずは現時点で自分の能力が届く範囲内で自己を定義するしかない。
だが、今すぐに自己定義しなくてもよいとなれば、自分の可能性を最大限追求できるように自己定義を先延ばしにしようとするのも当然のことと言える。
自己定義を先延ばしにしている間に、何が起こるかわからないし、可能性が広がるかもしれない。
そんな思いでフリーターを続けている人もあるだろう。
もっとも、そうした積極的な意図はなく、就職にしても結婚にしても相応の義務を伴うので、義務による束縛からただ逃げているというだけの人たちも少なくないのだろう。
アルバイトであれば、責任はあまり問われず、身軽なままでいられる。
さしあたって将来展望は棚上げし、今がよければいいといった姿勢でいくことが許されるのなら、独身のフリーターほど身軽な存在はないだろう。
ただし、そうした身軽さが、必ずしも居心地の良さにつながっているとはかぎらない。
というのは、社会的な義務や責任を免れている身軽さは、社会的に安定した位置づけを確保していない不安定さにつながるからだ。
自分にはまだまだ可能性があると思うことができるとしても、そこには必然的に、今はまだ何物にもなっていないことの不安や焦りが伴う。
社会的にどっしりと腰を据えて何かに取り組んでいるということがないのだから、使命を果たしている、やるべきことをやっているといった充実感が得られることもない。
結局、自己定義を先延ばしにし、自己物語を身にまとわないために、社会に安定的につながることができず、生きる方向性が見えてこないし、自分の日々の経験や行動に意味が感じられない。
このままではだるすぎる、何か目標がほしい、燃焼感がほしい、などと思いつつも、自己物語という枠組みがないため、どうしたらよいのかがわからない。
モラトリアム時代の倦怠感は、このような事情で蔓延しているのではないか。
自己物語の破綻と多重人格
人にはいろいろな可能性がある。
せっかくいろいろなものになり得る自分を、ひとつの可能性にのみ封じ込めるのはもったいない。
とりあえずはある生き方を選んだとしても、別の可能性も残しておきたい。
できることなら、複数の生き方を生きることはできないものだろうか。
そんな気分になるのももっともである。
複数の自己物語を同時的に生きようとすると、個々の行動を導く座標軸が定まらないため、混乱が生じ、安定しない。
だが、下位レベルの複数の小さな自己物語を時間をずらして生きるというのは可能だ。
たとえば、昼間はバリバリのビジネスマン、夜は反社会的なパンク・ロッカーというように。
でも、その場合も、複数の物語を包摂する、より大きなひとつの自己物語があるわけである。
自分の可能性をあまり挟めずに、いろんな自分を活かすということを考えたら、下位レベルに別の物語を包摂できるような柔軟な自己物語をもつことが大切だ。
自己のさまざまな体験をひとつのつじつまの合った物語に綴りあげることができないとき、解離性人格障害というのが生じることもある。
一般には、多重人格と呼ばれるものだ。
北米にとくに多いと言われる解離性人格障害の発生に関与しているとかんがえられているのが、幼い頃の被虐待経験である。
日本でも、精神医学者の町沢静夫らが被虐待経験が生んだと思われる人格解離による12もの人格をもつ人物の症例を報告している。
この患者の心の中には、両親から虐待を受けても恐怖におののくだけで抵抗できない人格、父親から性的虐待を受けそうになったときに抵抗した人格、こうした過酷な境遇の中で生まれた残酷な人格、平然と虐待を受け何の痛みも感じない人格、母親を恨む人格のように、多くの人格が解離しつつ同居している。
過酷な体験による恐怖や親に対する憎しみを意識するのはあまりにも恐ろしいので、そうした体験や意識を含む人格の部分が別人格であるかのように切り離される。
とても受け入れがたい経験を別人格に帰属させ、それを切り離すことによって、中心的人格が表面上は心の安定を得ることができる。
だが、それはあくまでも偽りの心の安定にすぎず、一貫した自己物語の中に身を置いていないことの不安定さに苦しめられることになる。
そうでなければ、人格の解離は病理とみなされる必要はなかっただろう。
自己物語を通して生きる
自己物語を通してものごとを考えたり感じたりする
演劇や映画、テレビドラマを見るとき、役者がそれぞれ与えられた役柄を演じているということに異議を唱える者はいないはずだ。
プロの脚本家が設定した役柄をそのシナリオに沿って、これまたプロの役者が迫真の演技を演じるのだから、見る者はいつのまにか演じられている世界に引き込まれ、登場人物が自分の意思で自発的に動いているかのような錯覚を起こしてしまう。
でも、一歩引いてみれば、登場人物が自分の意思で動いているわけではなく、その人物を演じる役者が与えられたシナリオに沿って動いていることは、だれもが認めざるを得ない。
では、現に生きている生の人生はどうだろうか。
テレビドラマのような人工的に演じている世界ではなく、ごく自然に生きている世界なのだから、人生をテレビドラマなどにたとえるのはおかしいと思われるかもしれない。
だが、自己物語の心理学の立場からすると、役者ばかりでなく実人生を生きる人たちも、自己物語というシナリオに沿って動いていると見ることができるのだ。
自己物語の筋立てに沿って動くことが自動化しているために、そうしていることを改めて意識することはないかもしれない。
でも、じつは、自分自身の意思によって自発的に動いているように思い込んでいるけれども、人は採用している自己物語の主人公がとるであろう考え方を推測して考え、感じるであろう感情を推測して感じ、とるであろう行動を推測してとるのだ。
人が自分らしさにこだわり、自己のアイデンティティを強く求める理由もここにある。
自分がどんな物語の主人公を生きているのかがわからないと、日常生活でどんなふうに感じ、考え、行動したらよいかがわからず、路頭に迷ってしまう。
自分がわからないといって身動きがとれなくなる人は、そんな心理状態に置かれているのだ。
社会学者クーリーは、自己というのはすべて社会的自己であると言い、個人と社会は決して切り離すことはできないという立場をとった。
たしかに人は、社会から切り離された独自な個人として考えたり、感じたり、行動したりしているのでは決してない。
そもそも社会から切り離された個人などというものは考えられない。
そして、人は、社会と自分をつなぐ自己物語の筋立てを生きている。
ゆえに、自分がどんな自己物語を生きているのか、その筋立てを知ることにより、日々の生活のどんなところが困難をもたらしているのか、どんなものの見方や行動のとり方が他者との間に軋轢を生じたり自分を苦しめたりする方向に作用しているのかの見当がつけられる。
自己物語の筋立てをチェックし、その主人公として振る舞う自分のものの見方や行動のとり方が他者との間に軋轢を生じたり自分を苦しめたりする方向に作用しているのかの見当がつけられる。
自己物語の筋立てをチェックし、その主人公として振る舞う自分のものの見方や行動のとり方の癖がわかることで、生活の立て直しがしやすくなる。
どこをどう変えたらもっと楽になるかのヒントがつかめる。
論証的思考と物語的思考
認知心理学者ブルーナーは、思考には二つの基本的な様式があるという。
それは、論証的思考と物語的思考である。
論証的思考とは、あることがらが真実であることを、論理的という意味での形式的な説得力を武器として証明しようとするものである。
そこでは、論理的に判断して正しいか正しくないかが問われるのであり、科学的な議論の場では一般にこの思考様式が用いられることになる。
これに対して、物語的思考とは、あることがらが真実であることを、迫真性というものを武器にして納得させようとするものである。
そこでは、論理的に正しいか正しくないかでなく、つながりのよい筋の流れ、興味を引く話の展開、心を動かす話の筋立て、信憑性のある説明の仕方が重視される。
それによって、なるほどと思えるようなもっともらしい話、共感できる話を導こうというものである。
ある人が自己を語るとき、聞き手はその語りを論証的思考において理解しようとするのではない。
同じく人生を生きる者として、その語り手の気持ちをわかりたい、その人生の流れを理屈よりも感情レベルで理解したいと思って耳を傾けるのだ。
物語る側も、論理的な整合性よりも、聞き手の注意を喚起する興味深いエピソードや思いがけない展開を組み込むことに留意し、論理よりも自分の気持ちをアピールする。
それによって、伝えたいことがらに信憑性をもたせ、共感を得ようとする。
論理的な整合性とは関係なく、いつの間にか話に引き込まれ、思わずうなずいてしまう。
物語ることの上手な人は、そんな説得力をもっているものだ。
そこに働いているのが物語的思考である。
正解を追求する論証的思考に対して、物語的思考は、よいストーリー性を追求する。
よいストーリー性をもつ物語とは、いかにもありそうな物語であり、なるほどと思わせる物語であり、思わず共感してしまう物語であり、興味を引く物語である。
そして、自己物語は、論証的思考ではなく物語的思考によって綴られ、また語られるのである。
自己物語の役割
自己物語に求められる社会性
宗教や神話、その土地に根ざした慣習やしきたりのような、生きる枠組みとして機能してきた物語的文脈を失った多くの現代人は、新たな自分の物語を求めて、自己探求の旅に出ることになった。
自分探しというのは、そのような流れの中で、現代人にとってのキーワードとなっていったのだろう。
自分探しといって、自己の内面を見つめるということがよく行なわれるが、いくら自分の内面を見つめたところで、そこに社会とつながる視点が豊かに蓄積されていなければ、その自己探求の旅は成功しない。
自己探求の旅でさがし求められているのは、生きる勇気を与えてくれる自己物語である。
ただし、自己物語は、社会的なものでなければ、過去から現在に至る諸経験に意味のあるまとまりをつけ、目の前の現実に対する行動を調整するものとして、うまく機能することはできない。
そこで必要なのが、他者と語り合う中で物語に社会性を注入すること、他者の視点を導入することである。
自己物語は、自分というものが社会に根ざしたものであるかぎり、自分のものであると同時に社会のものでもある。
自分の物語だからどんなものを構築してもよいということはなく、社会に根ざしたものでないとうまく機能していかない。
独りよがりの自己物語では、ただの妄想になってしまう。
正しい自己物語、正しくない自己物語というように診断する絶対的基準があるわけではないけれども、現実社会に自分をつなぐものとしてうまく機能するかどうかを見極めることは必要だ。
独りよがりの自己物語にせずに、社会に根ざした自己物語を構築するのに欠かせないのが、語り合う他者の存在だ。
相互に承認し、部分的に共有しあえる自己物語の構築をめざす中で、自己物語は社会性を獲得していく。
人生の節目には自己物語の書き換えと語り直しが必要
人生の節目には、アイデンティティの大きな危機に見舞われると言われる。
それは、言い換えれば、自己物語の書き換えが必要になるということである。
つまり、それまで機能していた自己物語がもはや現実と自分をつなぐものとしては通用しなくなり、以前とは違う、目の前の現実に適用可能な新たな自己物語の構築が求められるのだ。
受験、入学、卒業、就職、結婚、子どもの誕生、中年期の体力の衰え、子どもの独立、定年退職、配偶者の死など、人生のあらゆる節目ごとに、自己物語の大きな書き換えが求められる。
それまでの自己物語にこだわり、しがみついていても、どこかに無理が出てくる。
現実との間の距離が生じ、しっくりいかなくなる。
だからといって、「はい、では、つぎはこの物語を」といった具合に、ただちに新たな自己物語がどこかから与えられるというものではない。
やはり、相互に自己物語を承認し合ってきた仲間との語り合いを通して、納得のいく形で自己物語を書き換えていくことが必要だ。
自分がこれまで生きてきた、そして今も生き続けようとしている自己物語へのこだわりや、それと自分が現に置かれている現実状況との間のギャップについて語り合う中で、断念すべきところは断念し、付け加えるべき新たな要素を付け加えながら、全体としての物語筋も徐々に組み換えられていく。
新たな自己物語創出の必要性に迫られているときこそ、語り合える仲間、語り合いの場が求められるのである。