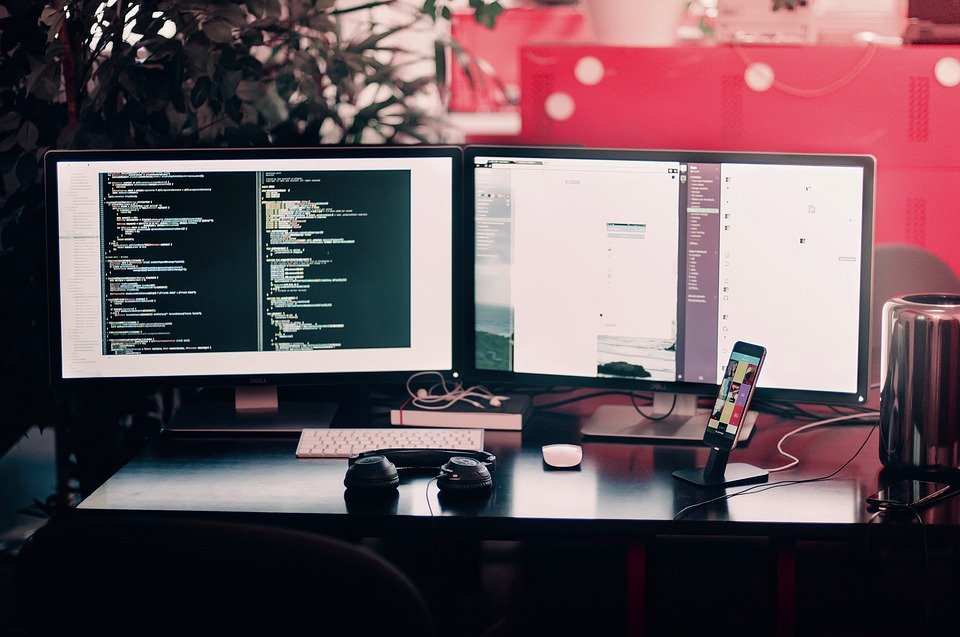社会的ひきこもりのスチューデント・アパシー
ひきこもりに関連する問題行動として、不登校とともにもっとも重要なものが、この「スチューデント・アパシー」です。
スチューデント・アパシーは70年代から注目されるようになった疾患概念です。
ひとことでいえば大学生の不登校を意味します。
ただし、通常の不登校とはいくつかの点で異なった特徴を持つため、独自の概念として研究が進められてきました。
まず、この概念について簡単に説明しておきましょう。
1961年にスチューデント・アパシーを初めて記載したP・A・ウォルターズは、その心理について次のように説明しています。
スチューデント・アパシーは男性にしばしばみられ、テストなどの競争的場面を避ける傾向があります。
このため男性としてのアイデンティティが発達しにくくなり、これが主な原因となってアパシー状態が続きます。
また「競争の回避」は一種の攻撃性としての意味を持つといわれています。
名古屋大学名誉教授の笠原嘉氏は70年代から80年代にかけて、このスチューデント・アパシーの概念をわが国に紹介し、本国アメリカ以上に活発な研究活動の基礎を作りました。
笠原氏はスチューデント・アパシーの病理を学生にのみ限定せず「退却神経症」という新たな臨床単位を提唱しました。
以下にその特徴をまとめてみます。
- 中心は大学生年齢で、男性に多い
- 無関心、無気力、無感動、また生きがい、目標・進路の喪失の自覚、アイデンティティの不確かさを訴える
- 不安、焦燥感、抑うつ、苦悶、後悔などといった苦痛感をともなわないため、みずからすすんで治療を求めない
- 自分のおかれている状態に対する深刻な葛藤がなく、その状態から抜け出そうという努力をまったくしない
- 自分が異常であるという自覚がないわけではなく、対人関係に敏感で、叱られたり拒まれたりするとひどく傷つく。自分が確実に受け入れられる場面以外は避ける傾向がある
- 苦痛な体験は内面的な葛藤などの症状には結びつかず、外に向けて行動化される。すなわち、無気力、退却、それによる裏切りなどの行動としてあらわす。暴力や自殺企図などのような激しい行動化は少ない
- 学業への無関心については部分的なもので、アルバイトには熱中するなどのいわゆる「副業可能性」が高い
- 優劣や勝ち負けへの過敏さがあり、敗北や屈辱が予想される場面を避ける傾向がある
以上の特徴は、社会的ひきこもりの青年たちの一部にもかなり当てはまります。
とりわけ大学生のひきこもり事例については、そのかなりの部分がスチューデント・アパシーと重なるでしょう。
通常、社会的ひきこもりの事例では、しばしば強い葛藤や暴力などの行動化がみられます。
この点ではスチューデント・アパシーの記述とは一致しないようですが、こうした葛藤が何に由来するものであるかを考えれば、それほど相違がないということが判ります。
ひきこもり青年たちの葛藤は、現状への不満や劣等感から引き起こされることが多いのです。
しかし大学に籍がある場合は、こうした強い葛藤は当面棚上げにすることができます。
大学生という社会的なポジションが、強力な心理的よりどころとなるためでしょう。
また世間も大学生という身分にはまだまだ寛容です。
浪人生や留年生が珍しくない大学という空間は、わが国においてほとんど唯一、年齢差による焦燥感を免れうる社会です。
また義務や生産性もほとんど期待されない時期でもあり、さまざまな点でプレッシャーの少ない生活圏があります。
しかし大学在籍時は葛藤を棚上げにできても、卒業してしまえばそうはいきません。
スチューデント・アパシーからはじまって深刻な社会的ひきこもり状態にいたった事例はまれではありません。
また大学生の不登校事例でも、対人困難が強い場合は、通常の社会的ひきこもりと同様、強い葛藤を訴えることも少なくありません。
スチューデントアパシーと社会的ひきこもりとの間に、あえて区分を設けることには、あまり積極的な意味がないように思います。
したがってここではスチューデント・アパシーも社会的ひきこもりの一形態であるとみなすことにします。
関連記事
社会的ひきこもりと回避性人格障害
ひきこもり事例に対して、最近この診断名を用いる医師が増えつつあるようです。
「人格障害」とは、冒頭でもふれたように心因性の精神障害とみなすことができます。
ただし、まだ発達途上にあるとみられる多くのひきこもり事例について、それを「人格障害」といった固定的な見方(定義上そうなります)で捉えきれるものなのか、疑問がないわけではありません。
さて「回避性人格障害」はDSM-Ⅳの診断基準では次のような特徴を持つとされています。
社会的制止、不適切感、および否定的評価に対する過敏性の広範な様式で、成人期早期にはじまり、種々の状況で明らかになる。
以下のうち、4つ(またはそれ以上)で示される。
- 批判、否認、または拒絶に対する恐怖のために、重要な対人接触のある職業的活動を避ける。
- 好かれていると確信できなければ、人と関係を持ちたいと思わない。
- 恥をかかされること、または馬鹿にされることを恐れるために、親密な関係の中でも遠慮を示す。
- 社会的な状況では、批判されること、または拒絶されることに心がとらわれている。
- 不適切感のために、新しい対人関係状況で制止が起こる。
- 自分は社会的に不適切である、人間として長所がない、または他の人より劣っていると思っている。
- 恥ずかしいことになるかもしれないという理由で、個人的な危険をおかすこと、または何か新しい活動にとりかかることに、異常なほど引っ込み思案である。
これらの診断基準は、たしかに「社会的ひきこもり」状態のかなりの部分に該当するものといえるでしょう。
ただし、重なる部分が大きいことも事実ですが、実はこれらの診断基準は、強い対人恐怖傾向のある人にもあてはまってしまいます。
もちろん社会的ひきこもりの成人事例に対してこの診断事例に対してこの診断を下すことは、誤りとはいえません。
後に「国際比較」の項でも述べるように、標準化を考えるならこの診断がもっとも適切とすらいいうるでしょう。
私がこの診断を全面的に受け入れることができないのは、そもそも「人格障害」という診断をあまり信用していないという個人的事情が理由の一つです。
回避性人格障害の診断基準にある行動パターンは、思春期事例の経過の中で、しばしば一過性にもみられるものです。
そのような事例にまで「人格障害」の診断を下すことには、どうしても抵抗があるのです。
むしろ広義の心因性障害の一つと考えて治療戦略を立てるほうが、有効かつ有意義であろうと思います。
関連記事
- ひきこもり青年のインターネット
- ひきこもり青年の独り暮らし
- ひきこもり青年への経済的な公的支援
- ひきこもり青年のお金の問題の解決法
- ひきこもり青年のお金の面はどう支えるか
- ひきこもり青年の心配な行動にどう接すればいいか
社会的ひきこもりと境界性人格障害
「境界性人格障害」は、最近では「境界例」や「ボーダーライン」としてマスコミにも取り上げられる機会がふえてきました。
これはひとことでいうなら、対人関係や情緒などがきわめて不安定で、しばしば暴力事件や自殺未遂を起こして問題となる事例を指しています。
人やものに対する態度が善と悪の両極端にわかれがちで、いつも空しさや漠然とした怒りを抱えており、孤独に弱い反面、安定した人間関係をつくることもできず、長年にわたり不安定な状態が続く人というイメージです。
このように述べると、社会的ひきこもり事例とはあまり関係がなさそうに思われるかもしれません。
なんといってもこの「病気」の特徴のひとつは、「人とかかわらずにはいられない」というものですから、ひきこもりどころか、その対極にあるとみることもできるでしょう。
しかし、ことはそう単純ではありません。
しばしば経験することですが、経過からは通常の社会的ひきこもりの事例と同じようにみえていた人が、克服への試みが進むにつれて、次第に境界例のような状態に変わってくることがあります。
とりわけ、入院治療でそのような変化が起こることが多いのです。
どのような事例がそうした変化を起こすかについては、事前に区別することが困難で、克服への試みを開始してみなければ判りません。
なぜこのようなことが起こるのでしょうか。
精神科医の笠原嘉氏は、スチューデント・アパシーと境界例が、病理としてかなり共通するものがあるのではないか、と指摘しています。
境界性人格障害の特徴といわれる病理には、自己アイデンティティの障害、自己分割、無快楽、空虚感があるとされます。
これらは社会的ひきこもりの事例でも、しばしば認められるものです。
また笠原氏は、境界例では「行動化」、すなわち暴力や自殺未遂などの症状がみられるのに対して、スチューデント・アパシーでは社会生活からひきこもるという「陰性の行動化」がみられるとしています。
いわゆる境界例とは、私たちすべてが多かれ少なかれ所有している、必ずしも病理的とは限らない心理が極端なかたちで表現される事例です。
例えば境界例の病理とされる「投影性同一視」は、私たちの日常生活においてもみられます。
これは友人に腹を立てている時に、逆にその友人が自分に対して怒っていると感ずるような場合です。
このように、程度によっては正常とみなされるはずの心理状態が、境界例では極端なかたちで出てしまうと考えてよいでしょう。
だから、私たちと境界例の事例との間には、「健康」と「病気」をわけるような明確な境目はありません。
また、ある種の対人関係の中にあっては、健康な成人が境界例のようなふるまいに出ることも珍しくありません。
「治療者が境界例を作り出す」といわれるのは、このような場合を指しています。
したがって、健常者以上に病理的な状況におかれやすい「社会的ひきこもり」の事例が、時に境界例のような状態に変わっていくのは、十分にありうることです。
関連記事
社会的ひきこもりと思春期妄想症
「思春期妄想症」とは、思春期に特有の、とくに自己視線恐怖、自己臭などを中心に訴えるような事例の総称です。
これらの訴えは、いくら周りの人が彼らの「思い込み」「勘違い」を説得しても、ほとんど変わりません。
その意味では、妄想に近い思い込みなのですが、さまざまな点で統合失調症とは区別されます。
経過中も症状がそれ以上に発展することは少ないことや、症状についての頑固な思い込みを除けば、日常の言動にさほど異常な点が目立たないということもあります。
この種の事例は、名古屋大学(当時)の植元行雄氏らによって最初に報告されました。
名古屋大学の村上靖彦氏らの報告では、思春期妄想症では「自己不全感」、「出直したい」願望、「魔術的短絡思考(過去に戻って一からやりなおせると思い込むような)」が強いとされています。
また、他人が自分に対して持つであろうイメージを、自分のものとして受け入れることを拒む傾向があるとされます。
これらの特徴は、社会的ひきこもりにもあてはまるところがあります。
「思春期妄想症」は、ひきこもり事例とかなり重なる診断とみることができるでしょう。
関連記事
社会的ひきこもりとうつ病
笠原嘉氏は、うつ病とスチューデント・アパシーとの鑑別に関して、帝京大学の広瀬徹也氏のいわゆる「逃避型抑うつ」など、関連性のある診断名についてふれながら、うつ病と異なるスチューデント・アパシーの特徴として、次のような点をあげています。
a,憂うつ感、非哀感、罪責感が欠けていること
b,自律神経症状、睡眠障害(うつ病にみられがちな)気分の日内変動が欠けていること
c,二次的にはうつ状態になりうるが、それが主な感情ではないこと
d,他者の助けを求めないこと
e,生活全般にわたり、活動性の低下がみられるわけではないこと
またスチューデント・アパシーの概念を唱えたウォルターズの指摘によれば、スチューデント・アパシーの事例は、うつ病患者のように「外界から愛をむしりとるようなことはしない」といいます。
スチューデント・アパシーの事例はむしろ、「外界は自分の欲するものを含まない」として拒むことが多いというのです。
この点は、社会的ひきこもり事例一般にもあてはまる指摘といえるでしょう。
ここに引用した笠原氏の指摘は、一部のひきこもり事例にはよくあてはまるものですが、a,eなどのように、あまり該当しない項目もあります。
「うつ病」と診断する上で重要な、bのような「身体症状」、とりわけ睡眠障害や食欲不振、朝の抑うつ気分などといった症状については、ひきこもり事例には顕著ではありません。
また、cのように、「抑うつ気分が一次的ではない」という点はやはり重要な違いです。
しかし、なんといっても最大の違いは、「うつ病」であれば薬物療法で治療しうるという点です。
抗うつ薬の進歩で、通常のうつ病であれば、薬物療法によって、ほぼ100%に近い改善率が期待できます。
社会的ひきこもり事例については、もちろん薬物が部分的に有効である場合もありますが、これほどの効果は期待しにくいことが多いのです。
関連記事
社会的ひきこもりと分裂病質人格障害
この診断は、かつて「精神病質」の一つであった「分裂気質」にほぼ相当します。
一つの性格傾向として、内向的で孤独を好み、社会的にひきこもりがちな人を指しています。
こうした傾向は、部分的にはひきこもり事例と共通するものでしょう。
しかし笠原氏は、この診断とスチューデント・アパシーとの主な違いとして、次の点をあげています。
a,(スチューデント・アパシーでは)他者への疑り深さ、孤立傾向、物事に受け身であること、態度に「冷たさ」や「硬さ」がすくないこと
b,(スチューデント・アパシーは)問題が起こる以前は活発であることが多く、また克服への試みによって回復する可能性があること
これに加えて、DSM-Ⅳの分裂病質人格障害の診断基準の項目で、ひきこもり事例には典型的ではない特徴としては次のものがあります。
c,他者の賞賛や批判に対して無関心である
d,社会的関係に対する欲求を持たない
これらの点は、ひきこもり事例では、むしろ正反対の傾向がみてとれます。
つまり、ひきこもり状態にある人たちは、普通以上に「ほめられること」を望んでおり、「批判されること」に過敏になりがちです。
つまり、心のどこかでは他人との関係を強く求めていることが多いのです。
関連記事
社会的ひきこもりと循環性気分障害
近年注目されている診断概念に「循環性気分障害(チクロミア)」というものがあります。
これは、ごく簡単にいうと、軽症の躁うつ病にあたります。
この診断は主にアメリカで使用されることが多く、わが国ではあまり使用されず、事例の報告もほとんどありません。
しかし、かなり重いうつ状態と、軽躁状態を繰り返すこの疾患は、臨床の現場では時おり出会うことがあります。
アメリカでは、H・S・アキスカルをはじめ、多くの研究者がこの疾患について報告をしています。
本質的には躁うつ病と同じ疾患で、たんに重症度が違うだけとされることが多いようです。
また実際に、長期間経過を追っていくと、しばしば本当の躁うつ病に移行するとされています。
この疾患は、早く発症すると、社会生活のうえで深刻な問題を引き起こしがちです。
もともとは能力もあり対人関係も苦手ではないので、学生時代までは問題なく過ごす場合もあります。
しかしひとたび社会に出ると、行動に一貫性がないため、安定した就労はきわめて困難になります。
このため軽躁状態のまま就職しては、トラブルを起こしてクビになり、自信をなくしてうつ状態になるようなことを繰り返します。
性格や行動の傾向については社会的ひきこもり事例と対照的ですが、結果としてひきこもっているにもひとしい経過をたどる場合が多いようです。
事例の数としてはけっして多くはありませんが、私もこれまでに5例ほどこうした事例の経験があり、稀な疾患ということでもないようです。
循環性気分障害の事例は、ひきこもり事例とはむしろ対照的なところが多いので、みわけることはさほど難しくありません。
また、ひきこもり事例よりは薬物療法による改善が期待できます。
ただし、対応をあやまるとひきこもり事例以上に治りにくい場合もあるため、安易に考えるべきではありません。