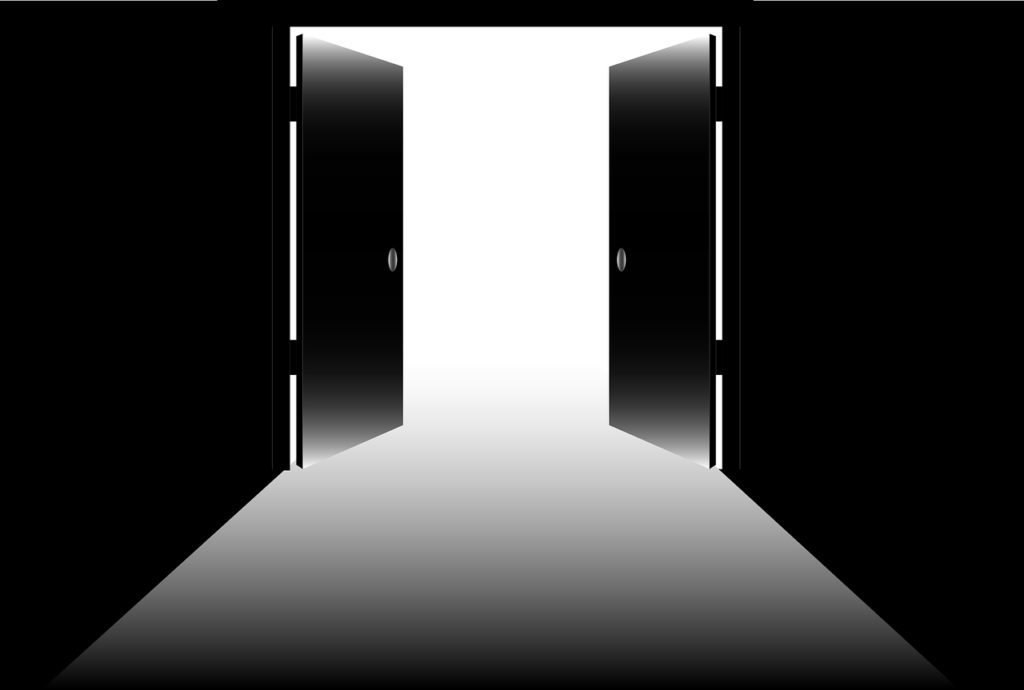従来の精神医学の中での位置づけ
「社会的ひきこもり」は病気なのでしょうか。
この点はある程度はっきりさせておく必要があります。
もし病気であるのなら、とりあえずの対処法を講じつつも、診断と治療のシステム整備を並行してすすめていく必要があるでしょう。
事例の増加に伴い、専門家もその存在を無視できない状況になった時、混乱を少なくする方法はあるでしょうか。
それが「ひきこもり」という状態を、できるだけ従来の精神医学の中に位置付けておくことだと考えます。
もちろんこうした事例には、さまざまに時代を反映する部分もあり、従来の枠組みのみではくくれない部分もあります。
しかし、ことさらに新しい部分に注目する前に、共有可能な言葉で記述しておくことは、やはりどうしても必要な手続きです。
ここでは「社会的ひきこもり」状態を、従来の精神医学の中にどのように位置付けることができるかを考えてみます。
関連記事
精神科医アンケート調査
全国の大学医学部などの精神科教教授、日本児童青年精神医学会会員の精神科医、全国の上記以外の治療機関の精神科医、102名を調査対象として、「社会的ひきこもり」に関する意識調査を試みました。
その結果を集計したところ、なかなか興味深い結果が得られました。
残念ながら、三つの群で回収率にばらつきが多く、医学論文としては必ずしも意味のある結果とはいえないのですが、一つの参考資料としてここで紹介してみましょう。
アンケートでは、次のような4つの特徴条件をすべて満たすような事例について、医師としてどのように判断するかを尋ねました。
- 一年以上にわたって持続的に社会的ひきこもり状態にある
- 心因性に発症した可能性が高い(器質性・内因性の可能性が否定されるか、きわめて可能性が低い)
- 二十代後半までのあいだに発症している
- ひきこもり以外の他の症状を伴わないか、伴っても二次的に生じた可能性の高い症状(対人恐怖、強迫症状、家庭内暴力、軽い被害念慮、その他)にとどまる
まずこうした事例の増加傾向についての質問に対しては、「事例の経験はあるがとくに増加傾向は感じない」という回答が57%、「近年増加する傾向にあると感じる」という回答がこれに次いで29%でした。
診断的にはどのように考えるかとの質問に対しては、「従来の診断分類で診断できるが、かならずしも十分でない」という回答が57%、「何らかの形で新たな診断分類を必要とする」とした回答が22%でした。
また、こうした事例にもっとも該当すると思われる診断名については「回避性人格障害」が最多で36%、「随伴する症状によって診断する」がこれに次いで25%、「退却神経症」が23%、という結果となりました。
意外だったのは、このような事例の経験がない治療者が意外に多かったこと、また逆に、増加傾向を指摘する方が三割近くを占めていたことでした。
従来の診断分類では足りない、あるいは不十分との判断が八割近くを占めていたことは、納得できるものでした。
診断名については複数回答がほとんどで、ひきこもり事例群が必ずしも一様のグループではなく、その中にさまざまな状態像が含まれているとみる治療者が多いようです。
関連記事
- ひきこもり青年のインターネット
- ひきこもり青年の独り暮らし
- ひきこもり青年への経済的な公的支援
- ひきこもり青年のお金の問題の解決法
- ひきこもり青年のお金の面はどう支えるか
- ひきこもり青年の心配な行動にどう接すればいいか
社会的ひきこもりの治療の必要を認める見解
さて、アンケート結果の引用を続けましょう。
こうした事例の治療の必要性については、「治療が必要である」という回答が50%、「事例によっては治療の対象でありうる」という回答が48%と、なんらかの形で治療の必要を認める回答がほとんどを占めていました。
また、どのような事例に対して治療を開始するかについては「本人、もしくは親が希望した場合」「統合失調症が疑われた場合」「自傷他害の恐れが高まった場合」といったコメントが多く寄せられました。
ここで治療の必要を認める見解が回答のほとんどを占めたことの意義は、たいへん大きいと思われます。
ひきこもり事例に対して有効と考えられる治療法については、「精神療法」が87%、「薬物療法」が67%、「入院治療ないし収容治療」が31%となっていました。
ここでは「精神療法」の意味をひろくとって、精神科で行われる治療法のうち、薬物や物理的な刺激を用いない方法全般を指していますが、一口に精神療法といっても、その内容は実にさまざまです。
アンケートではさらにさらに、精神療法としてはどのような治療技法を念頭において対応するか、という質問項目を設けました。
それに対する回答としては「家族療法」という回答が54.2%、「来談者中心療法」が家族療法に次いで53.1%となっていました。
もちろん日本で本格的な家族療法が普及しているわけではありませんから、この結果は多くの精神科医が家族を重視しているというほどの意味に解釈すべきでしょう。
同様に「来談者中心療法」というのは、別名ロジャーズ法などとも呼ばれますが、患者さんの訴えをまず受容することを大切にして、あまり指図がましいことはいわないようにするという姿勢を意味しています。
この結果には、多くのひきこもり事例が治療意欲に乏しく、治療が中断しがちであるために、治療者の対応は受容的・非指示的なものにならざるをえないという事情が反映されているかもしれません。
さて、家族が重要であるという認識がかなり広くなされているならば、なかなか通院しようとしない本人に代わって家族だけが相談に通うことについてはどうでしょうか。
結果は「何らかの改善は期待できる」という回答が64%、「どちらともいえない」という回答が26%となりました。
社会復帰への道筋
治療が進み、本人も通院するようになって、いよいよ社会復帰となった時、それをどのように進めていくべきか。
社会復帰のために有意義と考えられる活動について質問してみました。
「精神科デイケア施設」が56%、「アルバイト」が34%、「知人・親戚の職場」が33%、「趣味の同好会など」が25%、「専門スタッフがかかわる形での”たまり場”的施設」が22%、「精神障碍者のための作業所」が22%という結果でした。
また「ひきこもりの予後」についての質問には、「典型的な経過というものはない」という回答が63%、「治療的関与があればよい見通しをもちうる」との回答が21%、「治療をしてもきわめて深刻」という回答が12.8%でした。
「ひきこもりは放置した場合はさまざまな経過をたどるが、治療への導入が成功すれば、それなりによい見通しが持てることが多い」というものです。
このアンケートには、通常の回答に加えて、多くの貴重なコメントが出ました。
なかでも治療の基本姿勢として、「治療者との接点」「場の共有」「治療者とのパイプ」などといった表現で、治療場面で本人との接触を持続すること自体に意味があるのだ、という指摘があり、大いに啓発されました。
また社会復帰の経路については、寄せられたコメントからも、どのような経路を利用していくかはケースバイケースといったコメントが多く寄せられました。
こうした経路に乗せる事自体の困難さも、しばしば指摘されていました。
以上がアンケート調査の集計結果となります。
関連記事
ひきこもりの国際比較
ひきこもり問題はわが国に独特のものなのでしょうか。
これは難しい質問です。
そうだとも、そうではないとも答えることができるからです。
わが国の引きこもり事例と同じものが、海外に存在しないかといえば、まったくそんなことはありません。
しかし、ひきこもりをとりまく周囲の対応や社会状況には、わが国独特のものがあります。
このことがおそらく、わが国のひきこもり事例が独特の経過を辿る一因となっているでしょう。
関連記事
アメリカの心理学者、ポール・マロイ氏は、ひきこもりが恐怖症の一つであるとして、抗不安薬と行動療法の組み合わせによって治療することが可能である、としています。
文化的差異については、個人主義社会のアメリカと集団主義社会の日本、という対比をしています。
また、同じく臨床心理を専門とするモリ―・ブランク博士は、それが不安障害の一種であり、しばしば不登校ではじまって成人後も慢性的な社会的ひきこもりとして持続すると述べています。
博士はさらに、それが思春期以降にはじまった場合は、小児期からの事例に比べてその後の経過が悪く、抗不安薬などで治療が可能であるが完全な社会復帰は望めない、としています。
博士はその病理が、「失敗への恐怖」に関係していると述べています。
複雑で困難な競争の場と化しつつある世界を前にして、そこから完全に撤退しようとする個人が増加するのは自然であるというのです。
ひきこもりに関する著作もあるイギリスのアイザック・マークス博士は、この種の問題はイギリスでもまったく珍しくないとした上で、汎社会恐怖の一つと捉えています。
また博士は、アメリカでは彼らは回避性人格障害と診断されるであろうと述べています。
台湾出身でアメリカ留学中の精神科医、ローレンス・ラン氏は、これらが恐怖症と関連していることをふまえた上で、台湾ではそれほど経験しなかったこと、また、それが社会的・文化的状況と密接に関連しているという可能性を述べています。
また、やはり台湾の精神科医、カオ・チェン・リン氏も、このような事例は台湾ではまれであると述べています。
さらにリン氏は、分離不安による不登校はあるが、長期化したひきこもりは、社会恐怖、回避性人格障害、分裂病質人格障害のいずれかを疑う、としています。
タイの精神科医、プラモト・スカニッチ氏は、このような問題はバンコックでは経験がないと述べた上で、もっともな疑問を投げかけています。
「彼らは、生活費をどうしているのか?」
関連記事
フランスの精神科医、デニス・ルグア氏は、このような事例はフランスには存在せず、日本文化や日本的生活様式に関係していると述べています。
またやはり精神科医のルネ・カソー氏は、それは日本的文脈における社会恐怖ではないか、と述べています。
しかし、匿名のある心理学者は、次のような、注目すべき意見を持っています。
フランスでも状況は同じです。
社会的ひきこもりは中学の一年くらいからみられるようになります。
彼らの多くはホームレスになるため、果たしてどのくらいの事例が存在するのかは判りません。
父親の権威をなくした崩壊家庭が一般的です。
精神病のようにすらみえます。
彼らはどこから来たのでしょう?
彼らは他人をあてにするばかりで、みずから動こうとはしません。
フランスでは、彼らに関する論文をみたことがありません。
私たちはやっと、問題の端緒についたばかりなのです。-
こららの見解をまとめると、一般に「社会的ひきこもり」としている事例は、「社会恐怖」ないし「回避性人格障害」のいずれかに分類されているようです。
そのような前提に立てば、たしかに治療の可能性はもっとみえてくるでしょう。
今回の国際比較を通じて、「社会的ひきこもり」という問題が、いかに個人病理だけでは説明できない多様性をはらんでいるかということが明らかになりました。
そう、たしかに事例個人だけを取り上げるなら、それが「社会恐怖」や「回避性人格障害」であってはいけない理由はありません。
それにもかかわらず、この問題の特異な点は、こうした診断の問題だけでは語りきれないところにあるようにおもわれるのです。
その意味からも、さきに引用したフランスの心理学者の指摘は重要です。
もし彼らが、こうした重度の精神障害を抱えたまま成人したとしたら、確かにホームレスになるよりほかはありません。
関連記事
本人が二十代、三十代にいたっても、親が働けるうちは養い続けるということ。
またそのような家族関係がいつまでも葛藤の原因となるという状況にこそ、日本的な特異性があるのかもしれません。