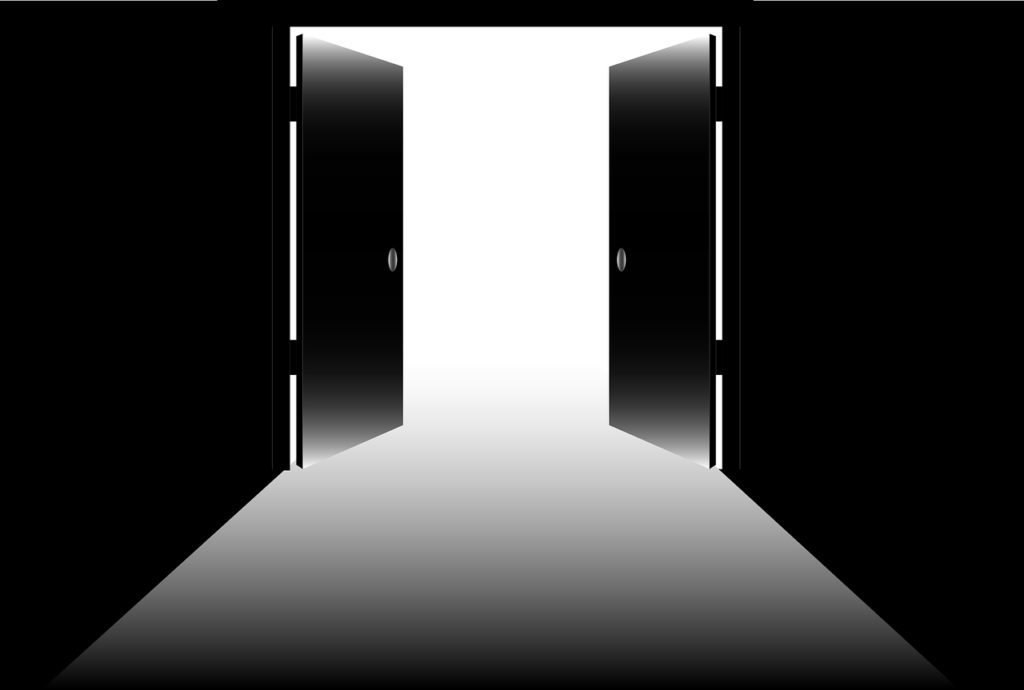教育環境の悪化と共同体の崩壊
教室の中の学力格差に潜む危険
子どもたちの対人関係能力低下の原因としては、家庭の問題を別にすると、いまの教育環境にも大きな問題がある。
文部省がゆとり教育を推進する中で、土日が休みになった。
かといって、学ぶ内容がそれほど減っているわけではないので、学校側は行事を減らしていく。
さすがに修学旅行までなくすことはないだろうが、遠足や球技大会など、さまざまな行事が減るということは、子ども同士が楽しく遊び、付き合える機会が減るということになる。
もともと大半の子どもたちにとって、学校に行く楽しみは、授業よりもむしろ友達との交流にある。
ところが、いまの学校では子どもたちが思い切って楽しく交流する機会が減ってしまっているのだ。
これでは、ゆとり教育といいながら、楽しいゆとりのイベント時間を奪い、ますます子どもたちの対人関係能力を低下させることになるのではないか。
最近、文部科学省にも、子どもたちの学力低下に歯止めをかけようという動きがあるが、ゆとり教育推進によってどうしても国語、数学(算数)、英語などの主要科目の時間数が減っている。
そうなると、受験に向けて、土日に塾に通う子どもがますます増えることが予想される。
当然、塾に通う子どもと学校だけの子どもとの学力差も開いてくることになろう。
ゆとり教育の狙いは、ひとつにはそれまでの詰め込み式のカリキュラムについていけない子どもたちを何とかしようということがあったはずである。
ところが現実には、公立の学校側は、子どもが私立へと流れていく風潮を食い止めたいので、授業時間をこれ以上減らさないために行事を減らす方向にいっている。
また、それでも私立に比べて学力低下を心配する親たちは、子どもを塾へと駆り立てている。
少しでも偏差値の高い学校に入学したいという子どもたちは、学校の勉強に加えて塾でも勉強する。
そうなると勉強嫌いな子どもたちと、さらに学力差が開くことにもなりかねない。
学力差が開いて、授業についていけない子どもたちは、いよいよ学校がいやになるだろう。
しかし、いまや塾なしに学力低下を防ぐことはできなくなっている。
つまり、いまの子どもたちをめぐる環境は、ますます不登校からひきこもりになる子どもたちが増える方向にあるように思わざるを得ないのだ。
ひきこもり激増の根本にある少子化問題
ひきこもりの原因として、教育環境、対人関係能力の低下、いじめがあるのだが、実はその根本には少子化現象の問題が横たわっている。
少子化の背景には、戦後の自由主義、個人主義の流れの中で個人尊重の生き方が当たり前になってきたことがある。
個人個人が自分の人生を大切にしたいと考えるので、結婚しても子どもをつくらない夫婦も増えている。
また、子どもをつくるにしても、母親が育児に時間を取られたくない、あるいは子どもに十分に手をかけたいと、計画出産で子どもを一人か二人しか産まないようになってきたという状況がある。
また、子どもに十分な教育を受けさせるために必要な教育費が大きくなってきたということもある。
高校、大学まで進学するのが当たり前という風潮、さらに受験競争が激しくなっている中で、親は子どもに少しでも偏差値の高い学校に進学してほしいと、塾などにも通わせる。
お金も手間もかけ、親の期待は一人か二人の子どもに集中する。
親の期待が大きいと、子どもに大きなプレッシャーを負わせることになる。
子どもが親の期待に応えることができている間はいいが、親の期待に応えることができず成績が落ちてくると、学校に行くのが苦痛になってくる。
しかも、一人っ子できょうだいもいない、また近所で一緒に遊ぶ子ども仲間もいないような環境では、対人関係を学ぶこともできない。
さらには、母親の愛情が一人なり二人の子どもに集中するので、どうしても過保護になる。
結果として子どもは家庭の中で王子様、王女様のように大事にされ、幼児的な全能感が修正されずに過大な自己愛を持ったまま、幼稚園に入り、小学校に入ることになる。
集団の場に入ったときに、他人と摩擦を起こしながらも対人関係を学んでいける子どもはいいのだが、うまく自己愛を修正できない子どもは仲間はずれにされていく。
人間関係がうまくできないと、居心地のいい母親に守ってもらえる家庭へと、ひきこもってしまうことにもなりかねない。
さらに情報化社会の進展で、テレビ、コンピューターゲーム、パソコンなどが普及して、家の中で一人で楽しめる、対人関係を必要としないような環境が整っている。
そのためにますます対人関係能力が低下していく。
もう一つ忘れてはいけないことは、日本社会にはもともと村八分のように、仲間でなければ排除するという性質があるという点だ。
いい意味では家庭的、しかし家族からはずれた人に対しては冷たい。
会社に対する帰属意識が強かったのも、同じ会社に属していることで、疑似家族のような結びつきをつくっていたからである。
しかし、いったんその仲間からはずされたら、いじめにあう。
徒党を組んで、仲間でない者は村八分にするといった日本人の意識は確実に残っている。
戦後の日本は個人主義が浸透したようでも、まだまだムラ意識が残った社会なのである。
個人が本当の意味で自立しないと、いじめという体質はなくならないといえるだろう。
甘え社会が自立できない若者を増やす
いまは、高校を卒業してもほとんどが専門学校、大学に進学するので、社会に出る年代はひと昔前よりも遅くなっている。
そういう意味では、かつてモラトリアムといわれていた社会に出るまでの時間がどんどん長くなっている。
しかも、社会に出ても家から離れずに自宅から仕事に通い、パラサイト・シングルとなって親から経済的にも精神的にも自立しない人も多い。
日本では二十歳で成人式があり、法律的にも成人となるが、いまの二十歳はたいていは学生で、経済的にも親に寄りかかっている。
さらに社会に出てからも、親にパラサイト(寄生)する。
そういう意味では、現代の日本で本当の意味で大人になるのは、平均して三十歳前後なのではないだろうか。
このような国は世界中見渡してもまずない。
日本で自立する年齢が遅いのは、親が過保護であるからといえる。
日本の親がこれほど過保護になっている背景には、もともと日本が甘えを許容する社会だということがある。
一人ひとりの自己責任というのが、日本ではあまり明確にならないのだ。
ことに家族関係となると、その甘え合い、もたれ合いが強くなる。
まだ、日本が貧乏な時代であれば、早く子どもたちに働いてもらわなくては困るという経済的な圧力が、子どもの自立を促していた。
しかし、現在は経済的に豊かになり、親に経済力があるので、子どもが三十歳になっても、子どもの生活の面倒を見ることが可能になっている。
子どもは、面倒を見てもらえるかぎりは面倒を見てもらったほうが楽だし、得である。
親の方も、いつまでも子どもを手元に引き止めておきたいと思っており、場合によっては結婚してからも、一緒にいてもらおうとする。
この長い期間の親子のもたれ合い、甘え合いによって、子どもに自立心が育ちにくくなる。
自立心がないから、いじめの問題も自分で何とか解決していく力がない。
そこから逃げてしまう。
ひきこもってしまうというようになりやすい。
そしてひきこもればひきこもったで、自分がこうなったのは親のせいだと、今度は親を責める。
しかし、十五歳くらいになれば、もう親の責任という話ではないはずである。
本来、どんなに親が過保護で過干渉であっても、自立心は生まれてくるものなのである。
ひきこもりになる子どもは自立心はなくとも、自尊心はかなり高いという共通項がある。
不登校レベルでは、多少自尊心が高いかなという程度だが、ひきこもりとなると自尊心はかなり高くなってくる。
自分が「優秀ではない」と言われたくない、批判されたくないという気持ちが非常に強いのだ。
かくて空想の世界で孤高の自尊心を守る。
そして、他人から批判されるくらいなら、家にいたほうがいいとなる。
このように自尊心が高くなってしまう原因は、自分を客観的にとらえる目を持たないことにある。
親の影響があったとしても、ふつう十代の半ばになれば、自分のことを客観的にとらえる目を持つようになる。
そこで自分の自尊心を少し修正していくことができればいいが、それができない。
つまり自分で考えるという能動的な思考や行動が乏しいのだ。
共同体の崩壊が「母子密着」を生んだ
ひきこもりは、本人の資質が問題となっている。
しかし、同時にその背景には家族の問題がある。
とくに母親と子どもの関係が重要である。
当然のことながら、母親と子どもの関係は、父親と母親の関係、つまり夫婦関係によっても大きく違ってくるし、父親と子どもの関係によっても違う。
しかし、現代の日本社会において共通していることは、子どもに対して決定的な影響力を与えるのは母親であるということだ。
不登校でひきこもっている中学生や高校生の中には、時に二十歳を過ぎてもお母さんの布団の中にもぐりこんで、お母さんと一緒に寝る子どもたちがかなり存在する。
これは男女を問わないのだ。
ひきこもりの子どもたちは、「お母さん、助けて」と、母親の布団の中に入るわけで、それは母親の子宮の中にもぐるようなものなのである。
異常に強い母子密着を表しているといえるだろう。
世界中で今日の日本社会ほど「母子密着」が強い社会はない。
教育熱の高い韓国や一人っ子政策の中国など子どもの教育に熱心な国はあるが、それでも日本のような母子密着という現象は聞かない。
なぜ、これほどに日本で母子密着が強くなったのだろうか。
社会的には、地域における共同体が失われてしまったことが大きな要因だと考えられる。
土居健郎や河合隼雄が指摘するように、日本は本来的に母性社会といえる。
しかし現代の日本社会には、かつてあったような村落共同体のような共同体はなく、かろうじて地域コミュニティ的なものがあるだけとなっている。
「共同体」とはごく簡単にいえば、そこで生活する人たちがお互いに話し合い、お互いに協力し合い、助け合っていく生活空間といったようなものである。
そこには協力や助け合いだけでなく、お互いの干渉や拘束、約束事といったものがある。
そう考えると、私たちが暮らしている今日の地域社会は、共同体としての機能をまったくといってよいほど失っていることになる。
そこで三つの問題点が生まれてくる。
- 地域社会の共同体による治安維持機能がなくなってきたということ。
- 地域社会を通じての子どもの社会化がなされないということ。
- 専業主婦の「孤立化」。
現代の日本社会で、共同体として機能しているものは会社と家族と学校くらいであろう。
しかし、その会社と学校すら最近の実態を見ればかなり不安定になっている。
となると、最後の砦となるのは家族しかないのである。
ところが、その家族にも問題がある。
父親はほとんどの時間を会社や仕事関係の付き合いで過ごし、時には家の中にまで仕事を持ち込む。
母親は、最近では専業主婦がどんどん少なくなっており、フルタイムではなくてもパートの仕事などで外に出ている。
子どもは塾通いで忙しいと、みんながバラバラに生活をしている。
とはいえ、仕事を持っていても、やはり育児を担うのは多くの場合母親となっている。
母親は子どものことはどうしても気がかりで、子どもとの接触はできるだけとろうとする。
そうなると、家の中で父親だけが家族から離れてしまう。
父親は会社という共同体に強く縛られ、地域共同体とは無縁で、家族という共同体との関係も希薄になりがちである。
専業主婦の母親の場合、その付き合いの範囲は子どもを通しての幼稚園や学校の母親同士だけで、地域の共同体との結びつきは希薄になっている。
働いている女性たちも、仕事を通じた付き合いが主となり、隣り近所との付き合いはあまりなくなる。
こうして日本では、母親は家族、ことに子どもとの関係だけが強くなる。
もっともその逆の虐待のケースも増えている。
つまり、過保護と虐待の二分法の世界である。
地域共同体が機能していないために、家族が閉鎖的になってしまっているのだ。
しかもその家族の中も、夫婦関係、父子関係が希薄で、母親と子どもの結びつきだけが強くなっている。
まして母親が専業主婦であれば、子どもへの関心はさらに大きくなり、その関係はさらに強くなる。
地域社会の人間関係の中で揉まれていない、社会性の育っていない子どもと、子どものことしか視野に入らない母親の関係。
ある意味できわめてグロテスクな関係が、現代の日本の家族のなかに多々見られるのである。
核家族化と少子化の流れの中で、こうした母子密着の傾向は確実に強くなっている。
■関連記事
ひきこもりに至る過程を解明
ひきこもりの本当の姿をとらえる
日本人のひきこもり
ひきこもりとは
母子密着と子ども中心家族の問題点
「いい子であり続けられない」子どもからのSOS
この日本のきわめて特殊な母子密着が引き起こす病理について考えてみたい。
子どもの第二次反抗期は、本来、子どもが自立していく過程、だいたい十二歳前後の時期を指すが、近年の日本ではほとんどそれが見られなくなっている。
というのも、いまの家族関係の中では、子どもにとって頼るべき人は母親以外にいないので、その母親に見離されまいとすると、母親には逆らえなくなっているからだ。
十二歳前後というのは、強い自己主義が出てくる時期なのに、言いたいことも言えず、母親の言う通りにする。
これを小学校の六年生くらいから大学生になるくらいまで繰り返すと、母親の意向に沿った人生しか送れないマザコン男性ができあがる。
こうしたマザコン男性には、高学歴で一流企業などに就職する人も多いが、何ごとにつけてもやる気があるのかないのかわからない無気力人間になりがちである。
そして、自分の結婚相手さえも母親に探してもらい、結婚してからも何かと母親に相談する。
だから、夫婦関係にも問題が起こりやすくなる。
ところが、このマザコン息子も母親にとってみれば、自分の意向どおりに期待に沿って人生を進んできてくれた、実に「いい子」となる。
四十歳になって、自分の子どもがいるにもかかわらず、自分の母親にとっての「いい子」、つまりペットを演じている大人を見るのも珍しくない。
しかしながら、すべての子どもたちが「いい子」のまま大人になるわけではない。
途中で「いい子」をドロップアウトする子どもたちも多いのである。
たとえば、有名中学一年生のG君のように、成績が下がり、母親が期待していたエリートコースに乗れなくなって、反旗を翻すケースなどが典型的だ。
また、勉強だけではなく、失恋や就職の失敗など、何らかの挫折がきっかけとなってドロップアウトするケースも珍しくない。
いずれにしても彼らは、もはや母親から愛してもらえないのではないかというある種の危機感を抱いて、生きるか死ぬかの瀬戸際に追い詰められたような気分になっている。
そうなると彼らは突然爆発し、これまでと打って変わって母親に対して激しく反発するようになるのである。
P君は、母親のひと言で爆発してひきこもり、家庭内暴力にいたってしまったケースである。
母親が高校受験に失敗したP君に向かって、「どうしてあの程度の学校に入れなかったの」と言った瞬間、「なんだ?てめぇ。お前の頭が悪いからだろう!おれを生んだお前が悪いんだ。
責任を取れ、一生面倒を見ろ」
と爆発してしまったのだ。
その後、この家庭は悲惨な状態になってしまった。
父母と妹が家を出て別居し、ようやく彼が立ち直ったとき、夫婦は離婚した。
こうしたちょっとしたことがきっかけで、子どもの家庭内暴力がはじまることも多い。
母親から見離されたと感じたとき、彼らは心理的に追いつめられ、爆発してしまう。
学校から就職、結婚まで母親の敷いたレールの上を「いい子」で歩くのも、途中でドロップアウトしてひきこもりから家庭内暴力にまでいたるのも、結局は母子密着が引き起こした病理といえるだろう。
世界に類のない「子ども中心家族」の奇妙さ
「親はなくても子は育つ」という諺があるが、今日の日本社会では、そうはいかなくなっている。
人間は何事も学ばなければ身につかない動物である。
学ぶとは、書物によって知識や教養を身につけるということだけではなく、経験を通して物事の本質を学ぶことでもある。
そして、学ぶことによって自分をコントロールし、社会の中で適応して生きていくことができるといえる。
「親はなくても子は育つ」とは、私たちの生活する地域社会が、共同体として機能していた頃の話である。
自分の家のおじいさんやおばあさんはもちろんのこと、隣近所のいじいさんやおばあさん、おじさん、おばさんまでもが教育に参加する。
つまり、挨拶もまともにできない子どもには平気で注意や説教をしてくれた頃の話なのだ。
共同体が崩壊し、核家族が一般的になった今日では、親の躾があってはじめて子どもは育つ。
現代の日本社会では、親の役割が非常に大きくなったと認識する必要がある。
ところがいまの日本の家庭は、おじいさん、おばあさんがいないどころか、「父親が不在」である。
そのため、子どもはエディプスコンプレックスを体験しない。
エディプスコンプレックスとはフロイトが唱えた説である。
幼児期に母をめぐって父親と対立した男の子が強い父親に敗れて、自らの母に対する欲望を抑圧することによって生じるコンプレックスである。
そこで子どもは、父親のように強い男になろうと思う。
このエディプスコンプレックスの挫折を乗り越えることによって成長していき、母以外の異性へと関心が移っていくことになる。
しかし、いまの日本では強い父親などはまず存在しない。
そこで、子どもは母親の愛情を独占したままエディプスコンプレックスを体験することなく幼児期を通過し、思春期、青年期を経て大人になっていく。
母子密着の強いいわゆるマザコンはこうしてできあがる。
ちなみに、女の子についても触れておくと、女の子の場合のエディプスコンプレックスはエレクトラコンプレックスと呼ばれている。
この場合は、父親の愛情をめぐって母親と対立する。
エレクトラコンプレックスを通過することで成長し、愛情の対象が父以外の異性に向けられるようになる。
いまの日本の家庭では、子どもが生まれると、子どものことはすべて母親まかせになるのがまだまだ一般的である。
たいていの父親は、「おれは外で稼いでくるのだから、家の中のことや子どものことはお前の担当だ」と言うし、言わないまでも、自分は子育てにタッチしようとはしない。
実際、日本の企業社会では、三十代~五十代の人たちの仕事の責任は大きく、どうしても仕事がすべての生活になりがちである。
父親にとって家庭とは、ただひたすら休息する場所になっている。
この年代の仕事などのストレスがどんなに強いかは、五十五歳前後の男性の自殺が突出して多いことからもわかる。
日本の家庭では、子どもが生まれたらその時から夫婦は分離され、男女というよりも、お父さん、お母さんになる。
そこで、母親の愛情と関心はすべて子どもに注ぎ込まれ、父親はその関係から自ら撤退する。
したがって今日の子どもたちは、家庭の中で父親との闘いや葛藤といったものを経験せず、家の中の「王子様」や「王女様」の地位を得てしまうのだ。
そうなると、子どもたちは、「自分は偉い、親は自分の言うことをきいてくれる」という意識を持つようになる。
ところが、子どもたちが思春期を迎える頃には、彼らの活動範囲や活動内容も幅広くなり、さまざまな局面で親との対立が生まれるようになる。
そこではじめて、自分の言うことをきいてくれるはずの親が、言うことをきいてくれないという事態に直面する。
そして親の愛情が自分に向いていない、親から見離されたと感じ、彼らは暴力を振るってでも親を支配しようとするのだ。
これは、夫婦が分離して「子ども中心の家族」をつくってしまった結果に他ならない。
こうした家族の構図が見られるようになったのは、高度経済成長を実現した七十年代頃からである。
その傾向はますます強くなり、そして世界に類を見ない子ども中心の家族が形づくられたのだ。
諸外国の場合、家庭内暴力というと夫が妻に対して暴力を振るうケースが主で、親子間の場合には親が子どもに暴力を振るうケースが多く、幼児虐待などが主となっている。
アメリカがその典型で、日本はまったく逆になっている。
ここに日本の家庭の特質が現われているといえる。
今日の日本の家庭内暴力の背景には、日本の家族の問題があることをしっかり認識すべきだろう。
生まれたときから自分中心で育てられ、父親とも、あるいは隣近所のお兄さんや学校のクラスメイトとも遊ぶことなく、「王子様」や「王女様」であり続けた子ども。
そのあり方自体がもはや病理といえるのだ。
母親が父親の役まで背負い込む危うさ
日本の家庭では、父親が子育てにほとんど参加せず、母子密着の状態で母親が一人で子育てをすることが多い。
しかし、母親だけで育児をした場合、子どもに問題が生じやすくなる。
その理由は何だろうか。
最近は死語になりつつあるかもしれないが、母親のことを「お袋」と呼ぶことがある。
文字通り、母親というものはわが子を無限抱擁する性質がある。
子どもがいくら悪いことをしても、「私の子どもだから、かわいいことに変わりはないです」と言う。
もちろん、子どもにとってこのように自分のすべてを受け入れてくれる存在は必要である。
しかし、無限に受け入れることと、事の良い悪いを教える、躾けることは、同様に大切なことであり、平行してなされることが必要なのだ。
母親が無限にかわいがる存在ならば、父親は事の良い悪いを教える、躾ける存在でなければならない。
両者があってはじめて子どもは健全に育つといえる。
子どもが悪いことをした時に、父親が厳しく叱ることができるのも、母親が後で子どもを抱擁してくれるからなのだ。
母親だけが育児をすると、どうしても良い・悪いの躾が甘くなってしまう。
そうすると、子どもの現実への適応能力が育ちにくくなってしまう。
つまり、父親は子どもが社会に適応していくために大切な役割を担わなければならないのだ。
子どもが悪いことをすれば、母親も叱る。
しかし、母親は子どもに対してどうしても細かいところばかりに目がいき、些細なことで叱る場合が多い。
また、父親が本来の役割を放棄しているような状況では、母親は自分が父親の役割まで果たそうとすることになる。
しかし、それには限界があり、きちんと叱りきれない面が出てしまうのだ。
母親には本気で叱ると、子どもが自分から離れてしまうのではないかという不安がどこかにある。
そのため叱りながらも、「私から離れないで」というサイン、子どもを自分の側に引き込もうとするシグナルを発信してしまう。
建前では「自立心と生活力のある子どもにしたい」と言いつつも、一方では、「私から離れないで」というサインを出していることが多い。
このように、矛盾したメッセージを子どもに同時に発することをダブルバインド(二重拘束)という。
アメリカの文化人類学者・精神医学者のベイトソンは、このような母子関係では、子どもに分裂病が発病しやすいと指摘している。
また、日本の家庭の母親たちは、「父親の不在」のため、その淋しさの慰めとして子どもを父親の代わりにする傾向がある。
それでは自立心のある子どもに育てるのではなく、子どもが自分から離れないように取り込んでしまうことになる。
子どもは母親のエゴイズムの支配下に置かれている状態といえるだろう。
子どもの自立は夫婦の絆が試される時
日本の離婚率はアメリカほど高くないが、近年、離婚の件数はまちがいなく増えている。
その理由のひとつには、未成熟婚が多くなっていることがある。
未成熟婚とは、十代の終わりから二十代のはじめといった若い年齢の結婚というだけではなく、精神的に未成熟なために、すぐに離婚してしまうというケースを含んでいる。
もうひとつ多いのが中年の離婚だ。
子どもが中学を卒業し、高校生以上の年代になったときに離婚するケースだ。
それまで子どもが存在していたために何とか保たれてきた夫婦関係が、子どもの自立によって崩壊し離婚に至るケースが多い。
ピークは四十代だ。
子どもが自立するまでの長い時間の中で、夫婦の溝が深くなっていき、人生観や生活スタイルまでがまったく違ってしまう。
そしてこの場合、別れを先に言い出すのは、妻のほうが圧倒的に多い。
夫は、仕事やそれに関する付き合いが忙しく、家庭のことを顧みず、子育ては妻に任せきり、自分の妻が日頃何を考え、何を感じているのかなどに思いも至らない。
しかし、子どもに手がかからなくなった時に妻は、「家事と子育てだけに追われていた私の人生は何だったのか」と、自分の人生を改めて考え、離婚を決意する。
そこで夫からすれば、突然のように妻から離婚を言い出され、ただ途方に暮れるというパターンになる。
そしてこの中年離婚と同様の理由で、ひきこもりの子どもを抱えた夫婦が離婚するケースが非常に多い。
ひきこもりの子どもを抱えている夫婦の場合は、子どものひきこもり状態が回復し、家庭が少し落ち着いたときに離婚している。
夫婦はあまりにも疲労していたのだ。
家庭の中にひきこもりの子どもを抱えたり、その子どもが暴力を振るったりしている時には、いかに分離している夫婦といえども、一緒になってこれに対処していく。
その期間は夫婦の間には、ある種の連帯感が生まれている。
しかし自立したとはいえないまでも、子どもが回復して安定してくると、なぜ自分たちの子どもが、家庭が、こんなことになってしまったのかをお互いに考え、自分たち夫婦のこれまでの姿に気づき、離婚を考えることになる。
ましてや子どもが自立して家を離れると、夫婦だけの家となり、そこには冷ややかな空気しかない。
やはりそこで「もう別れましょう」と言い出すのは妻が多い。
戦後、私たち日本人はがむしゃらに働いてきた。
とくに四十代後半以上の年代の男性たちは、食べるため、家族を養うために外に出て、家庭を顧みず必死で働いてきた世代である。
その結果、日本社会はたしかに豊かになった。
しかし一方で、私たちは大事なものを失ってしまったのかもしれない。
自己愛の強い若者たちの危機
これまで見てきたように、少子化や母子密着などによって、自己愛の強い若者たちが生み出されたといえる。
その背景には戦後の日本社会のあり方が大きく影響していると考えられる。
戦前と戦後では、日本人の価値観が大きく変わった。
戦前の日本では、建前として国家のために尽くすということがあった。
それは、自分のことよりもまず国家や社会を優先するという考えである。
そのためには当然のことながら、個人の生き方は後回しになる。
ところが戦後、アメリカから民主主義と個人主義が導入され、価値観は一変した。
個人の生き方や個人の幸せを求めること、考えることが、もっとも大事なことであるということになったのだ。
しかし、戦後の日本がすぐにそうなったというわけではない。
戦後の焼け跡から奇跡の復興を成し遂げる原動力として、国家に対する滅私奉公に代わる会社に対する滅私奉公が登場する。
猛烈サラリーマンという言葉に代表されるように、すべての勤労者がとにかく食べるために、少しでも豊かな生活をするために、懸命に働いてきた。
高度経済成長を遂げるまでの日本では、会社が豊かになること、会社に滅私奉公することが、個人の生活の豊かさに直結していた。
戦後の父親たちは、一生懸命に働いて家にお金を持ってくるという経済力によって、父親の権威を保っていたということができる。
父親が働いて稼いでくれたお金で、家の中にはテレビが入ったり、冷蔵庫が入ったりと、目に見えて生活が豊かになった。
そこでは家族は父親のありがたみを実感できた。
高度経済成長を成し遂げた日本はますます豊かになっていく。
1970年代に入ると、日本人のほとんどが、自分は中流であるという「一億総中流」意識を持つまでになった。
そうなると、もはやお金のありがたみも薄れ、父親がお金を家に入れてくれるのは当たり前となってきたのだ。
そこで、仕事一筋で家庭にいない父親よりも母親が家族の中で強くなってきたのは当然の結果であろう。
父親が外に出て稼いでくることができるのも、家庭で家事、育児を受けもっている母親がしっかりしているからだということになる。
「ニューファミリー」といった言葉が登場したのも70年代半ば頃である。
猛烈サラリーマンがはやらなくなり、父親も家庭を大切にしようという風潮になってきた。
つまり、自分の家族を中心にした幸福を求めようとする傾向がいっそう強くなりはじめた。
そうした傾向への傾斜の分岐点になったのは、団塊の世代の最後にあたる70年代全共闘世代が、会社に就職して会社人間に変身していった時点である。
もはやイデオロギーや理念といったものに向かうのではなく、自分の幸福、家族の幸福こそが大事なのだという方向に向かっていったのである。
戦後の日本社会は、基本的には一貫して、個人の幸福が最大のテーマであるという方向を歩み、70年前後を境にして、それがいっそう加速度を増し、自分以外に価値あるものがなくなってしまったといえる。
今日の若者は、そうした価値観にどっぷりとつかった世代といえる。
またその頃から少子化傾向がはじまり、いまでは一人の女性が生涯に産む子どもの数は1.4人を割るほどになっている。
その結果、母子密着が強くなり、家庭の中で子どもが王子様、王女様として大事に育てられ、幼児のときのような全能感が壊されることなく、成長していくようになった。
社会の変化が、家庭にも影響を及ぼし家族関係を変え、ひきこもりなどいまの子どもたちの問題に大きな影を投げ掛けているといえる。
家では母を中心として子どもが過保護になるにつれ、学校の教師自身も生徒に対して過保護になっていく。
学級崩壊、校内暴力、非行は、その傾向が広がっていることを示しているように思われる。
PTAは自分の子どもさえよければいいという利己主義に走る。
その意味では、社会にも学校制度にも大きな問題がある。
その影響を受けて、子どもや青少年に問題が生じることが多い。
しかしだからといって、健全な子どもが育たないわけではない。