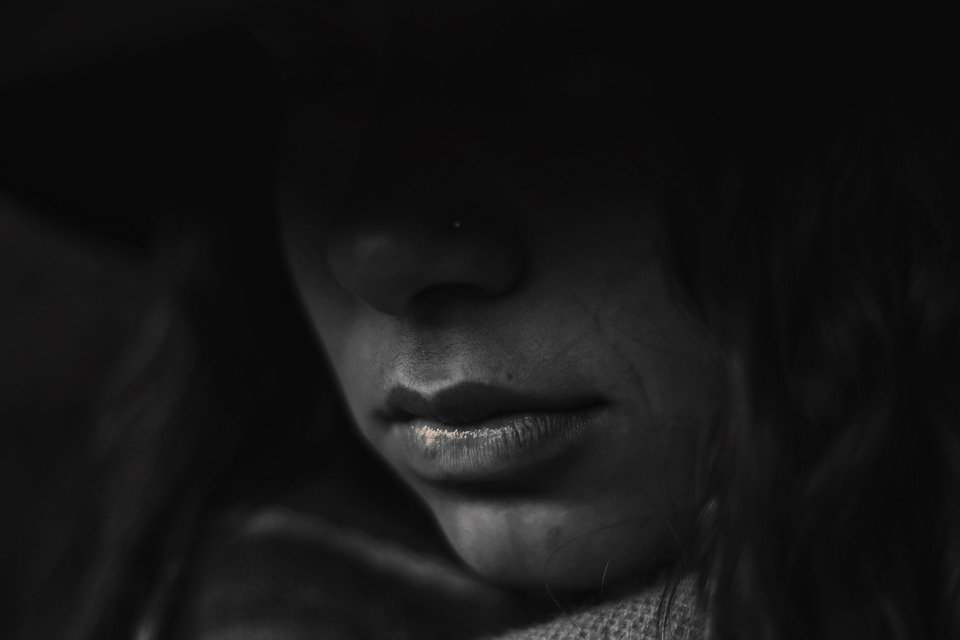ひきこもりに効果のある治療法
早めの対処がポイント
ひと口にひきこもりといっても、その実体は正常な人から分裂病まで幅広いものである。
分裂病を除外しようと思っても、会ってみなければ診断はできず、診察しても分裂病に近いが確定できないというケースも多い。
臨床の現場では、「分裂病を除外するものをひきこもりとする」と定義することも簡単ではない。
また、妄想性障害なのか、人格障害の妄想性人格障害なのか、十分に見分けられないことも多い。
さらに正常であっても、ひきこもることがあるのかという問題が残る。
25,6歳になって、なぜ社会に出て行かないのか、なぜ年齢相応の仕事ができないのかとなると、適応能力がその年齢相応でないわけである。
その場合は、精神障害といわざるを得ないケースとなる。
ただ家にいてパソコンをいじることが楽しみだ、あるいは絵を描くことが好きだ、あるいはピアノを弾くのが好きだという孤独な楽しみでひきこもっている場合は、それだけでは異常とはいえないのである。
実際に会ってみて、その人の生き方、考え方を検討しなければ診断はできないだろう。
創造性のためのひきこもりは、普通のひきこもりと同じとはいえないであろう。
ひきこもりという言葉は精神医学用語ではなく一般的な用語なので、それを一括して論じることは容易なことではない。
しかし、ひきこもりの若者を抱えた家庭は、25,6歳になっても家にひきこもって仕事をしていないとすると、彼らがとりたてて家で問題を起こすわけではなくても、親は大変深刻な事態に追い込まれる。
「この子はもう働かないだろう。もう結婚もしないだろう。そうなったら将来この子が生活するためのお金は、どうしたらいいのだろう?私たちが貯金しなければいけないのだろうか」
という事態になって、親の方がまず音を上げはじめる。
そしてそのときになって、はじめて本人に正面から説教をしたり、働くよう強要するのだ。
しかし、もはやその時点では、彼らは働く技術、働く能力を失っていることが多い。
無気力(アパシー)状態になっており、精神科医から診ても異常だと思うことが多い。
ある医師はこのような青年たちを診て、
「まず、最初にコンビニにでも勤めてみなさい」
とすすめる。
しかし、彼らがその気になってコンビニで働こうとしても、コンビニの面接で落とされてしまうことが多い。
その無表情な顔やいかにも機転の利かない、臨機応変さのない様子を見ると、「これは働けないな」とコンビニの店長らはすぐに察してしまうらしい。
まずは、「どんなに安い給料でもいいから働かせてください」「どんな仕事でもいいですから」
といった必死さを示せば、仕事に就くこともできるかもしれない。
しかし、彼らにはそのような臨機応変さも必死さもない。
そのため、「社会は厳しい。社会で生きる力はない」
と、また部屋に戻っていってしまうのだ。
彼らは、このようなことを繰り返す。
そうなると、ひきこもりの子を持つ母親はだんだんと精神的にまいりはじめ、うつ病になることが多いのだ。
そして精神科医に必死に助けを求める。
親のほうもいよいよ切羽詰まってしまうのである。
なかには、親が無関心な場合もあるが、それはよほど経済的に余裕のある家庭である。
たいていは経済的な面からも親は追い詰められていくことになる。
若い人同士が交流できる思春期・青年期病棟
25,6歳まで社会に出なかった場合、はっきりわかる特徴は対人関係の能力の低さである。
さらに人の表情や雰囲気を見て判断する能力や共感性の低下、体力の低下、また現実社会や会社での機転の利いた動き、思いつきといったものが欠落していることが多い。
そのため、何とかひきこもりを脱出したとしても、外の社会へ参加するのがむずかしい。
たとえ運良く就職してもすぐにクビをきられてしまう。
一日、二日行って辞めさせられた、一カ月で辞めさせられたというケースが、ひきこもりの人たちにはしばしば起こる。
したがって、すぐに就職するのではなく、ひきこもりから社会復帰への中間的な施設があることが望ましい。
自立支援組織が数多くつくられ、実際、そこからうまく立ち上がっていく人は多い。
しかし、自立支援組織にまで行ける力のある人はまだいいほうである。
そこにすら行けない人たちは、精神科の病院が単に治療というだけでなく、彼らが何とか外の世界に出て行くことができるところまで診てあげる必要がある。
しかし、そこまで面倒を見るような病院はなかなかないのが実状である。
ある精神科医はかつてある病院の一部を、思春期・青年期病棟のようにしたことがあった。
そして、そこをひきこもりの子どもたちに、
「病院というのではなく、あなたのような若い人たちがたくさん集まって巣立ちをする、そんな場所なんだ。
だから病院と名前はついているけれども、病院だとは思わないで、自分の対人関係の能力を高める場所だと考えてほしい。つまり学びの場なんだ。まあ、合宿と考えてくれ」と説明した。
そうすると、彼らの多くは母親の説得もあって心を動かし、入院してきたのだ。
入院してきたその日の彼らの行動は、実に奇妙である。
人とほとんど接したことがないので、病棟の自分のベッドのところに行くのにも恐怖感を持っているらしく、自分の手で目を隠し、腰を曲げて歩いて自分のベッドに行こうとしたりする。
自分を隠そうとしているのだが、その姿の方がよほど人目につき、周囲をびっくりさせることに気がついていないのである。
「人がどう見るのか」という感受性が歪んでしまい、妥当なバランスを失っているのだ。
最初はそんなふうだった当時ニ十六歳の青年は、自分と同じように対人関係がうまくない人をまず友達に選び、やがて二人は仲良くなり、ベッドの脇で子どものような拙い話をするようになっていた。
そして時にはふざけ合って、プロレスごっこのような遊びをしたりしていた。
このようなスキンシップは、この青年にとってははじめての体験であったのだろう。
このように同じレベルの若者との交流ができるようになることは、大きな心の励みになる。
やがて会話のレベルも上がっていき、病院では堂々と歩けるようになった。
生活も自分で歯を磨き、食事の時にはテーブルに座り、寝るときもちゃんと寝るという規則正しい生活ができるようになっていった。
彼はやがて自分で病院から外出することも余裕を持ってできるまでに回復した。
こうした段階を経て快方に向かっていく青年たちが多くいる。
それまでひきこもっていても、まずは状況が同じぐらいの仲間との交流が可能になることは、彼らにとって最大の喜びであり、最大の自信になるのだ。
その病院は一種の青年の合宿所と呼ばれていた。
合宿ということによって、病院のイメージを明るくしたかったのだ。
このような合宿から、多くの人が巣立っていった。
三カ月で人との接し方を身につけられる
その病院でどのような治療を行なっていたか紹介しよう。
まず、この青年たちの集まりでグループセラピーという集団療法を行なう。
それを雑談会と呼んでいた。
そこでは最初、彼らは何もしゃべることはできない。
その場合には「パス」といって、自分の話す番になったときの逃げ方を教えた。
やがて少しでもしゃべれるようになれば、その集団の一員という帰属感が生まれ、彼らも余裕が出てくる。
次に医師は、当直の夜に数人を集めてのロールプレー、つまり一対一の対人関係の練習を行なった。
たとえば、昔の友達に会ったときの対応の仕方、就職するときの面接の仕方など、さまざまな場面を想定してロールプレーを行ない、対人関係の能力をつけるようにした。
もちろん、個人療法で彼らの固有の問題もよく話し合った。
このような集団療法、ロールプレー、個人療法の三つのステップによって、彼らは深刻な病気でないかぎり、大体三カ月で人との接し方の基本を身につけていった。
また、その病院は開放病棟だけであったが、病院からアルバイトに行くことも許可した。
アルバイトで夜遅く帰ってきても、働くならばそれでいい、というように規則をつくったのである。
不登校の子どもも、そこから学校へ行きたいということであれば、積極的にすすめた。
彼らは学校に行くときに「行ってきます」と言えるようになり、病棟のもっと年上の青年たちが、「行ってらっしゃい」と言って送り出す。
そうして、いかにも嬉しそうに手を振って学校に行く。
帰って、「ただいま」と言えば、みんなが「お帰りなさい」と迎えてくれることも、彼らにとっては大きな励みになっていた。
これがもし、実際のお父さん、お母さんが言ったらほとんど意味はなく、むしろマイナスでしかなかったと思われる。
同じ年頃の若者との接触が、彼らにまさに必要なのだ。
彼らはやがて退院して、再び学校にいけるようになっていった。
■関連記事
ひきこもりの心の病理
現代日本社会のひきこもり
ひきこもりに至る過程を解明
ひきこもりの本当の姿をとらえる
日本人のひきこもり
ひきこもりとは
ひきこもりと向き合うことは日本社会の病理と向き合うこと
学校に戻れない二十代後半の問題
問題なのは、ひきこもり期間が長く、すでに学校に戻ることができない、二十代半ばを過ぎた人たちである。
病院で何とか人と交わることができるようになり、仲間との付き合いを学ぶことができても、そこから社会に出て適応していくことがなかなかむずかしいのである。
もちろん、運よく仕事を見つけることができる人もいる。
まずはコンビニということが多いが、そのほか倉庫の仕事、あるいは警備の仕事といったような、一人でできる仕事からはじめるケースがほとんどである。
やがて、もっと人と接することができるようになると、普通の会社に勤めることができるようになる。
しかし、普通の会社では、27,8歳になってしまうとなかなか採用してくれないのが現実だ。
二十回も面接を申し込んでも、すべて断られていた青年もいた。
その青年に「これからどうするんだい?」と聞くと、「先生、どうすればよいのでしょうか」と聞き返してくる。
「残念だけれど、お父さん、お母さんに自分が一生暮らせるようなお金の準備ができないだろうか、と相談してごらん。あるいは、お父さん、お母さんがアパートでも経営して、そこの管理人になるのもいいかもしれないね」
などと話した。
実際、親がアパートを建て、そこの管理人になって生活している34歳の男性もいる。
せっかく何とか社会に出て行くことができるようになっても、年齢によっては、アルバイトなら何とかなっても、定職に就くとなると社会の壁にぶつかることが多い。
しかし、まずは人との付き合い方を学び、学校に戻る、あるいはアルバイトであれ仕事をすることで、何とか社会に出ていくことができるようにする。
そこから定職に就き、経済的な面も含めて、本当に自立するには、かなりの時間が必要である。
日本を離れて自立する
日本の母親の過保護は、子どもが自己主張する力を低下させ、自分で人生を切り開いていく力をそぎ落している。
この深刻さをぜひ母親は知ってほしい。
本当にかわいがるということは、その子が自立して、自分で自分の生活が維持できるようになる力を持てるような独立心や、人生の計画性を立てられる人間にしていくことであるはずだ。
幼いときにこそ子ども同士で遊び、対人関係の基礎的な力がつかなければ、その上のより高度な対人関係の力は持てるはずはない。
幼い時から「勉強、勉強」と強要する親は、後に子どもが人と接することができなくなったときに、勉強どころか人の中にすら入っていけなくなることを知るべきだろう。
まずは対人関係、それが重要なのだ。
また、病院に入院して退院後、母親の元に戻れば家庭内暴力が起こる可能性のある子どもには、時に外国に行くことをすすめることがある。
ひきこもりの青少年を海外で生活させるという自立支援組織もいくつかある。
勉強嫌いな子どもが海外で生活することによって、自分で食事を作り洗濯をして、友達と遊ぶようになる。
やがて現地の言葉を勉強したり、あるいは一人で静かに勉強をはじめ、現地の高等学校に入っていく。
しかも、その高等学校から現地の大学へも行きたいと希望を待つまでにいたる。
日本であれほど勉強することを嫌い、中学校も不登校でまったく行かなかった子どもが、外国では自主的に高校から大学まで行こうとする。
このことは、日本においては、いかに親の過保護と過塾社会というものが子どもをスポイルしているかを示すものではないだろうか。
X子さんは家庭内暴力で21歳のときに病院に入ってきた。
退院するときに「君、お母さんと一緒に住まない方がいいよ。自立したまえ」と言うと、彼女は「じゃあ私はしばらく海外旅行に行きます」と言い、インド、チベット、フランス、ドイツと転々として、最後にイギリスに行き、そのままイギリスに6年も住んでいる。
彼女はイギリスで地元の建築の専門学校に入り、見事、建築士の資格を取った。
そしてイギリスの住居権も得て建築士として働きはじめた。
すでに、彼女は昔のようなひよわで、ときには荒れる女の子ではなくなっている。
立派な成人として、イギリスで楽しく暮らしている。
日本の過保護社会から離れ、彼女はもはや母親の元には戻ろうとしない。
親と離れて自立する方法
すでに紹介したが、青少年たちを集めた合宿形式の入院が、多くの人を助けたと思っている。
彼らがだいたい三カ月で、どうにか社会に出られるレベルになるということに、驚きである。
病院側には、このようなひきこもりの若者たち専用の病棟をつくってもらいたいと思う。
それを病院といわず、「合宿所」のようなものにすれば、彼らはもっと気軽に入ることもできるだろう。
同じようなひきこもりの人たちとの合宿こそが彼らを力づけ、仲間意識、共感意識を持たせ、彼らが社会に出るエネルギーを一緒に築き上げていくことができるのだ。
かつてはどこの民族にも、「若者宿」というものがあった。
いまでも、ニューギニアなどでは見られるのではないだろうか。
若者宿は、「子どもを大人にするためには、母親から子どもを離さなければならない」という知恵からはじまった慣習で、子どもが12,3歳になると子どもを母親から離して、子ども同士で生活させるものである。
期間はさまざまであるが、そこで彼らは老いたリーダーによって指導を受け、その村の言い伝えや規則などを教えられる。
また、そこではもちろん彼ら自身が自活して生活しなければならない。
こうした生活の中で、彼らは真の大人になる訓練を受けることになる。
そして彼らが若者宿から出る頃には、親がびっくりするほど大人に成長している。
昔からこうした若者宿があったということは、かつての人類の大きな知恵なのだろう。
しかし、いまやそれがなくなり、個人と共同体も分断されている。
自立支援組織の人たちが行なおうとしているのも、思春期・青年期病棟も、そうした若者宿のようなものだといえる。
子どもは親から離れ、そしてその親を断念しなければ自立できないのだ。
ところが、社会が裕福になり、母親の時間の余裕ができればできるほど、母親と子どもの接触が長くなり、母親と子どもがきょうだいか友達のようになってしまい、「母と子」という年齢の差、世代の差を感じさせないようになっている。
これは実はきわめて危険なことだ。
ライオンなどの動物はある一定の年齢になると、母親の方から子離れする。
子どもが悲しそうに、母親にいかにくっついていこうとしても、母親が噛み付いたりして突き放す。
自分で生きるしかないという厳しい試練を与えるのだ。
そうやって、子どもは自立していく。
動物でも、親がこのように厳しく対処しなければ、子どもはそのままでは自立できないのである。
私たち人間も、子どもを自立させるための、母と子の厳しい対立は必要ではないだろうか。
こうした厳しさこそ本当の愛情であり、それが親の冷たさでないことを、子どもはやがてわかるようになるはずなのだ。
大人になることが容易ではないことは、いまの日本の青少年のひきこもり現象をみればあきらかである。
ひきこもりを防ぐためには、場合によっては昔の若者宿のような、ある時期、親ときちんと離れることができる社会的な受け皿が必要なのではないか。
たとえば、ひきこもりから立ち直った若者たちが自らの手で自立支援組織をつくることができないだろうか。
ひきこもりの青年たちは、同じひきこもりの仲間に大変な興味を持っている。
インターネットのサイトを見ても、その実状がよくわかる。
彼らもまた、仲間を求めているのである。
彼らにとっては、社会に出て元気で働いている青年はあまりに距離が遠く、共感性を抱けないのである。
彼らは人間への興味を持とうとしても、一挙にその高いレベルにまでには上れないのだ。
したがって、まず同じひきこもりの仲間に共感を寄せることから出発すべきだろう。
このような人たちの中から、ひきこもりから脱する人が生まれるにちがいない。
そしてそのような人たちがひきこもりの青少年に働きかけ、自立支援組織をつくるということになれば、ひきこもりの改善に大いに役立つのではないかと思っている。
「類は友を呼ぶ」ように、似た者同士が寄り添いお互いに協力していくことで、自立へと進んでいくものであると考えられる。
ひきこもりを生み出さないために
ひきこもりの青少年を生み出さないようにするためには、まず、子どもたちの対人関係の能力を上げることだ。
対人関係の能力を上げるためには、子ども同士が集まるような集団を確実に確保しなければならない。
いまは、子どもたちが集まれる場所は学校しかない状況である。
したがって学校での仲間づくりに、学校の先生方はもう少し力を入れてほしい。
学校は勉強だけを教える場ではない。
それ以前に対人関係を学ぶ場でもある。
対人関係を学べば、感情のコントロールも、人との共感性も学ぶことができ、それは子どもの大人への成熟を促すもっとも大切な訓練なのだ。
また、何でも望みをかなえてくれるこの消費社会は、子どもの欲望のコントロールをいっそうむずかしいものにしている。
何でも思うままになることが、わがまま、自己中心性を強め、それがまた対人関係の能力を低下させ、最終的には孤立化を招くことにもなる。
そして母親としか接することができない、ひきこもりの状態をつくってしまう。
自分の子どもさえよければいいという利己的な母親は、母性本能でしか子どもに接していない。
妥当な理性ある母性というものを失いがちな社会、それがいまの母性社会である。
そして母親自身も共同体から切り離されているためにバランス感覚を失い、エゴイスティックな母性となって、かえって子どもに害を与える結果となっている。
学歴社会はつねに格差をつくり、勉強だけが突出して重要なものとしてみなされ、勉強以外のものがいかに有能でも評価されないという社会を生み出している。
これは、お互いがお互いを敵とする、つまりホッブスの「人間は人間の敵である」というのとほぼ近い社会である。
それは、日本人のいかにも偏狭な社会観を表わしている。
さらに、そこに日本的ないじめの構造が絡み、日本的なねたみ、そねみの世界をつくり出しているとさえいえる。
ひきこもりというのは、すでに述べてきたように日本独特の社会病理とみなされるものである。
●母性社会の病理
母子分離がうまくできない病理、母親の過保護の病理、父親の家からの逃避の病理
●学校教育の病理
偏差値教育の病理、学校教育の画一化の病理
●社会的な病理
豊かであるが故にひきこもってもこまらないという病理、少子化の病理、いじめの病理、その他組織が硬直化したことからくる病理
こう考えてみると、ひきこもりは日本社会そのものの病理が青少年に現われているといえる。
たしかに彼らがひきこもっていても、家族が困らないほどに日本は豊かになった。
また、豊かさゆえに母親と子どもの接触がいっそう多くなり、母子が密着するようになった。
そのために、子どもを強くし、自立を促すというしつけを忘れてしまってきた日本の病理なのでもある。
ひきこもりを解決しようとするとき直面するのは、いままで一途に繁栄を望み、先進国になろうとしてきた日本が、置き去りにしてきた世界である。
ひきこもりに現われているのは、日本のすすみゆく文化の矛盾でもある。
つまり西洋文化を取り入れ、産業発展を目指し、一途に進歩と繁栄を目指したことに対するアンチテーゼでもある。
私たちは何のためモノをたくさんつくり、消費社会を進めてきたのであろうか。
それは私たち自身の幸福のためでなければならないはずである。
ところが、いまやそれが人間を置き去りにし、人間疎外を生み出している。
人間同士のつながりや心を大切にすることを忘れ、モノの豊かさだけを追求してきたことに対する反撃を、私たちはひきこもりという形で突きつけられているのかもしれない。
このように、私たちのいまの社会にこそ問題があるとして、ひきこもる青年たちを庇うとしたら、いささか行き過ぎかもしれない。
彼ら自身が自ら立ち直る力を持たなければ本当の解決にはつながらない。
まず彼ら自身が自らにも問題があることを勇気を持って直視してほしい。
ひきこもりの人の多くは、本音としてはひきこもりたくはないと思っている。
したがって、彼らに援助の手を差し伸べる組織を十分に備えたいものである。
どんなに家庭に問題があろうとも、どんなに社会に問題があろうとも、どんなに学校に問題があろうとも、子どもたち、若者たちには、それを突き抜ける強さを身につけてほしいものである。
流れ流れて、気がついたらひきこもりになってしまったり、努力しても実らないならば、ひきこもるしかないなどということは、人間の弱さを露呈するばかりである。
ひきもりつつ、その高い自尊心を誇示しているという自分の現実の姿を見つめ、正直に自分の弱さを認め、その弱さから出発することを、彼らに期待したい。
そうでなければ、彼らはひきこもることによって、たとえいまの社会に対して異議を唱えていたとしても、自己満足でしかないのではないか。
問題のない社会はない。
ならば問題を乗り越えようとするその勢いが、社会を活性化させ、平和な社会実現へのエネルギーとなり、さらに自分たちの自由をより広げていくのに役に立つ喜びを、彼らに知ってほしいものである。
どんな条件であっても、それを乗り越えていく、創造的な力こそ彼らに望まれる。
そして、もしそれが成功するならば、彼らは大変な人生の喜びを手にすることだろう。