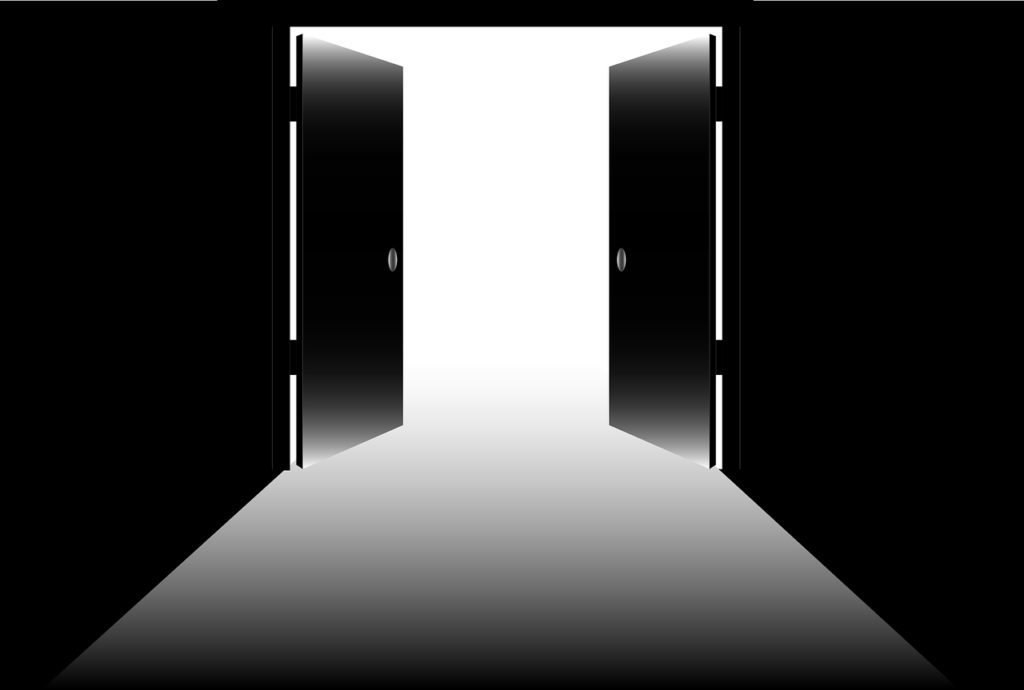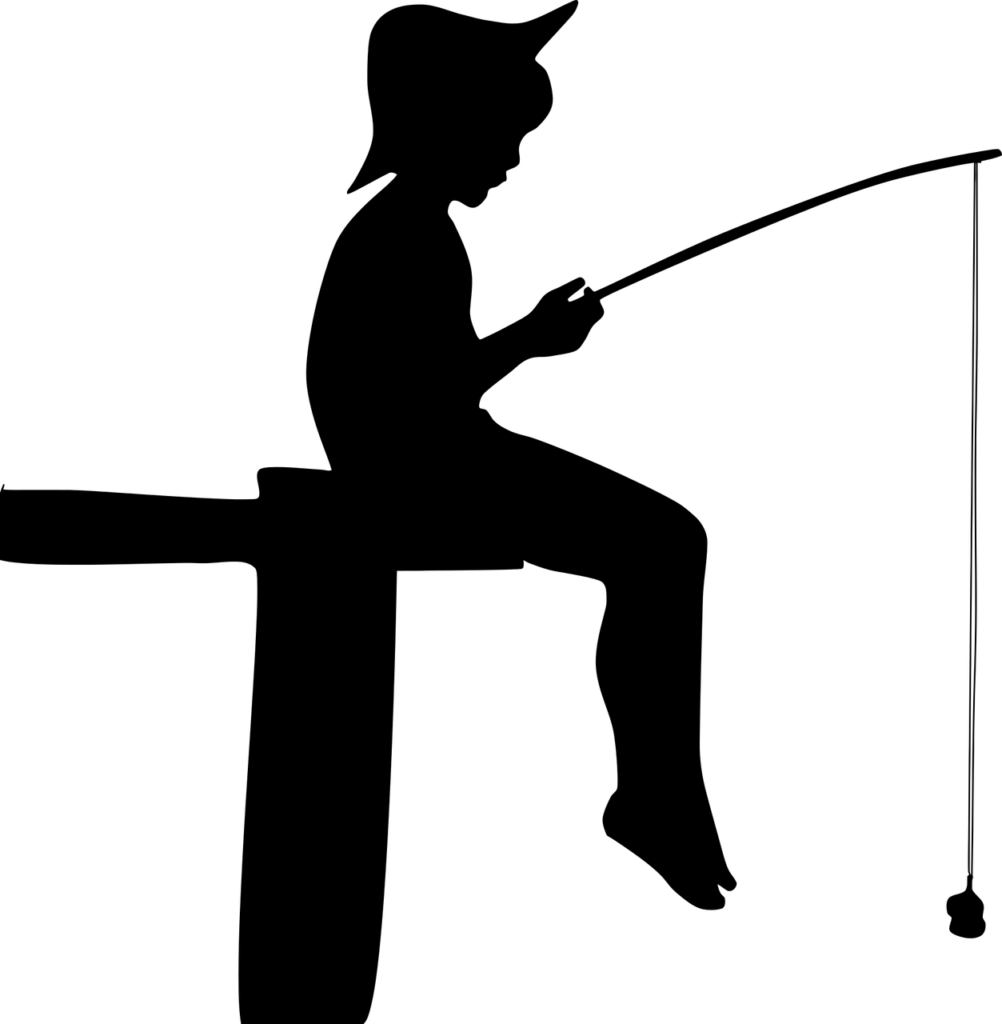彼らはつねに単独で行動する
1975年3月5日。カリフォルニア州メンロパーク、冷たい霧雨が降る夜。
無愛想なエンジニアたちが、ゴードン・フレンチの自宅ガレージに集まった。
<ホームブリュー・コンピュータ・クラブ>と名づけられた集まりの第一回目の会合だった。
彼らの目的は、一般向けのコンピュータをつくること。
大学や企業で使われる大型のものしかなかった当時、それは画期的な大仕事だった。
ガレージには隙間風が吹き込んでくるうえに、出入りする人々のために、湿った夜の外気に向かってドアが開け放たれていた。
そのなかに、<ヒューレット・パッカード>で電卓設計の仕事をしている24歳の若者がいた。
生真面目な性格で、眼鏡をかけ、髪を肩まで伸ばして、茶色のヒゲをたくわえていた。
彼は椅子に座って、仲間たちが『ポピュラーエレクトロニクス』誌に紹介されたばかりのコンピュータキット<アルテア8800>の登場に驚き、熱心に語り合っているのにじっと耳を傾けていた。
アルテアはまだ本物の個人向けコンピュータではなかった。
操作が難しく、興味を持つのは、雨の水曜日の夜にこのガレージに集まってマイクロチップの話をするようなタイプの人間だけだった。
だが、パソコン開発の重要な第一歩だったのだ。
若者の名前はスティーブ・ウォズニアック。
彼はアルテアの話を聞いてわくわくしていた。
ウォズニアックは三歳のときからずっと、エレクトロニクスに興味を持っていた。
そして、11歳のときに、アメリカで開発された最初期のコンピュータであるENIAC(電子式数値積分計算機)についての記事に出会って以来、自宅に置けるような小型で使いやすいコンピュータをつくることを夢見るようになった。
そして今、このガレージで、その夢が実現されるかもしれないと知ったのだ。
当時の経緯を語った自伝『アップルを創った怪物』で、ウォズニアックは同じ志を持った人々が周りにいたことが大きな刺激になったと語っている。
ホームブリュー・コンピュータ・クラブの面々にとってコンピュータは人類に貢献するための道具であり、彼もまた同じ考えだった。
最初の会合で彼はそれを口にはしなかった―あまりにも内気だったからだ。
だが、その晩自宅に帰ってから、さっそく彼はキーボードとスクリーンがついた現在使われているような形のパソコンの設計にとりかかった。
三カ月後、最初のプロト機ができあがった。
そして、その10カ月後、彼はスティーブ・ジョブズと一緒に<アップル・コンピュータ>を設立した。
今日、ウォズニアックはシリコンバレーで崇拝される存在だ-カリフォルニア州サンノゼには彼の名前にちなんだ通りがある―そして、彼はアップルのおどけ者と呼ばれることもある。
彼は公の場で話をしたりうちとけたふるまいをしたりするすべを身につけ、BBCのリアリティ番組『ダンシング・ウィズ・ザ・スターズ』に出演したこともある。
私は彼がニューヨークシティの書店で講演しているのをみたことがある。
立ち見だけの会場は混み合って、詰めかけた人々はウォズニアックの業績に敬意を表して、1970年代のアップルのマニュアルを持ってきていた。
だが、名声はウォズニアックだけのものではない。
ホームブリュー・コンピュータ・クラブの最初の会合はコンピュータ革命のはじまりであり、自分の人生でもっとも重要な夜だったと、ウォズニアックは言う。
したがって、志を同じくする人々が集まっていたホームブリューへの参加が、ウォズニアックの成功をもたらした重要な条件だったと指摘できるかもしれない。
ウォズニアックの偉業は創造性に対する共同アプローチの輝かしい一例だと、あなたは思うかもしれない。
革新的でありたいと思う人々はたがいに交流しながら働くべきだと結論づけるかもしれない。
だが、それは間違いかもしれない。
メンロパークでの会合のあと、ウォズニアックがどんな行動をとったかを考えてみよう。
彼はクラブの仲間たちと一緒にコンピュータの設計に取り組んだだろうか。
答えはノーだ(ただし、水曜日の集会には欠かさず参加したが)。では、意見を交換し合う広い開放的なオフィスを求めただろうか。
これも答えはノーだ。
自伝に書かれたパソコン開発の経緯を読んで、もっとも驚かされるのは、彼がつねに単独で行動していたことだ。
ウォズニアックは作業の大半をヒューレット・パッカードの狭い自分のオフィスで行った。
毎朝6時30分頃に出社し、そんな早朝からひとりで専門誌やチップのマニュアルを読み、パソコンの設計に試行錯誤した。
仕事が終わると、いったん自宅へ戻って簡単な食事をしてから、車でオフィスへ取って返し、夜遅くまで作業した。
パソコンの設計に明け暮れたこの孤独な日々を、彼は「それまでの生涯で一番ハイだった」と表現している。
1975年6月29日の夜10時頃、地道な努力がついに成果を実らせ、プロト機第一号が完成した。
彼がキーボードを打つと、目の前のスクリーンに文字が現れた。
それこそ、かぎられた人間しか味わえないブレークスルーの瞬間だ。
その瞬間も、彼はひとりだった。
彼は故意にそうしたのだ。自伝のなかで、彼は偉大な創造に憧れる子どもたちにこんな助言をしている。
これまで会った発明家やエンジニアの大半は僕と似ている―内気で自分の世界で生きている。
彼らはアーティストに近い。
実際、彼らの中でも特に優れた人たちはアーティストそのものだ。
そして、アーティストは単独で働くのが一番いい。
ひとりならば、マーケティング委員会だのなんだのに意見を差し挟まれることなく、自分の発明器の設計をコントロールできる。
本当に革新的なものが委員会によって発明されるなんて、僕は信じていない。
もしきみが、発明家とアーティストの要素を持ったたぐい稀なエンジニアならば、僕はきみに実行するのが難しい助言をしよう―ひとりで働け。
努力で作業してこそ、革新的な品物を生み出すことができる。
委員会もチームも関係なく。
■参考記事
内向型と外向型はどこが違う?
内向型人間の心理
生まれつきの内向型
パートナーの内向型、外向型組み合わせ特徴
内向型の子育て
創造性に富むのは内向型
1956年から1962年にかけて、カリフォルニア州立大学バークレー校の<インスティテュート・オブ・パーソナリティ・アセスメント・アンド・リサーチ>が、創造性に関する一連の研究をした。
研究者たちは素晴らしい創造性に富んだ人々を対象にして、いったいどんな要因が彼らを一般人と一線を画する存在にしているのかをあきらかにしようとした。
研究者らはまず、建築家や数学者、科学者、エンジニア、作家など各分野で大きく貢献した人々のリストを作成し、その人々を招いて性格検査や問題解決実験を実施し、特定の質問をした。
つぎに、研究者たちは各分野でそれほど革新的な業績をあげていない人々を招いて、同じ検査や実験や質問をした。
研究の結果得られたもっとも興味深い発見のひとつは、すばらしい創造性に富んだ人々は落ち着いた内向型だという点で、のちの研究でも同じ結果が得られた。
彼らは人間関係を維持するのが上手だが、「特別に社交的だったり、積極的に人間関係を築こうとしたりする性格ではなかった」。
彼らは自分自身について、自立していて個人主義だと表現していた。
そして、多くの人が10代の頃には内気で孤独だったという。
これらの発見は内向型が外向型よりもつねに創造力が豊かだという意味ではないが、特別な創造力を発揮する人々のなかには内向型の人間が多くいるということを示唆している。
これはいったいなぜだろう?
静かな性格は創造力を育てる力があるのだろうか。
内向型が創造力に勝っていることを説明する理由はいろいろあり、その理由からは誰もが学ぶところがある。
たとえば、内向型は単独作業を好み、孤独は革新の触媒となりうる、ということだ。
著名な心理学者のハンス・アイゼンクによれば、内向型は「当面の課題に意識を集中させ、仕事と関係ない人間関係や性的な問題にエネルギーを浪費することを避ける」のだ。
つまり、人々がパティオで楽しく乾杯しているときに、裏庭でリンゴの木の下に座っていれば、あなたの頭にリンゴが落ちてくるが高いということだ(ニュートンは偉大なる内向型のひとりだった。そして、ウィリアム・ワーズワースは自分自身を「永遠なる心、思考という奇妙な海を孤独に旅する」と表現した)。
■参考記事
内向型人間の楽になる人付き合い
内向型の人の仕事が楽になる方法
内向型の自分で楽に生きる方法
生まれ持った内向性を大事に育む
内向型の人が楽に生きる方法
「新集団思考」が創造性を壊す
もし本当に孤独が創造性の重要な鍵ならば、私たちはみな孤独を愛そうとするだろう。
ひとりで勉強しなさいと子どもに教えるだろう。
企業は従業員にプライバシーと自主性を与えるだろう。
けれど、実際には、現代の社会では逆のことをしている。
自分たちは創造的な個人主義を重要視する時代に生きているのだと、私たちは信じたがる。
そして、バークレー校で創造性の研究が開始された1950年代を振り返って、優越感を覚える。
1950年代当時の体制に順応していた人々とは違うのだと考え、舌を突き出して因習に囚われないぞと主張しているアインシュタインのポスターを壁に貼る。
インディーズの音楽を聴き、映画を観て、独自のオンラインコンテンツをつくる。
私たちは「発想を変える」(たとえ、それがアップル・コンピュータの有名な広告スローガンに発想を得たものであっても)。
だが、たとえば学校や職場など、世の中の重要な組織がどんな状況かを見れば、話は違ってくる。
そうした現状を「新集団思考」と呼んでいる。
この現象は職場で生産性を閉塞させ、競争が激化する社会ですばらしい成果を得るために必要になるスキルを、学校へ通う子どもたちから奪ってしまう。
新集団思考は、なによりもチームワークを優先する。
創造性や知的業績は社交的な場からもたらされると主張する。
多数の人々がこれを強力に提唱している。
「革新(知識を基盤とした経済の心臓部)はそもそも社会的なものだ」と著名なジャーナリストのマルコム・グラッドウェルは書いている。
組織コンサルタントのウォーレン・ベニスは著書『「天才組織」をつくるグレート・グループを創造する15の原則』で、「私たちは誰ひとりとして、私たち全員よりも賢くない」と書いた。
この本の第一章は、「グレート・グループ」の隆盛と「グレート・マンの終焉」を告知している。
クレイ・キャシーは『みんな集まれ!ネットワークが世界を動かす』のなかで「ひとりの人間によるものと考えられている仕事の多くは、じつは集団を必要としている」と言っている。
「大天才ミケランジェロでさえ、システィーナ礼拝堂の天井画を書くときにアシスタントたちを使った」というのだ(アシスタントは交換可能だが、ミケランジェロはそうではないことは考慮されていない)。
新集団思考は多くの企業に採用され、しだいに労働力をチームに組織化した。
これは1990年代はじめのことだ。
経営学教授フレデリック・モーゲソンによれば、2000年までには全米企業の半数が、現在ではほぼすべてが、チーム制を採用している。
最近の調査で、上位管理職の91%が、チームは成功の鍵だと信じているとわかった。
コンサルタントのスティーブン・ハーヴィルは、2010年に彼が関わった、<J・C・ペニー><ウェルズファーゴ><デル><プルデンシャル>など大企業30社のうち、チーム制でないところはなかったと語った。
たがいに離れた場所で働く仮想チームの場合もあるが、それ以外の場合には、チームをつくり維持するために、オンラインで各人の日程を管理してミーティングの期日を決める必要があり、物理的なオフィス空間にはプライバシーはほとんどない。
最近のオフィスはオープンなつくりになっており、自室を持っている者はいないし、壁や仕切りのない広い部屋で重役が中央に陣取って各部に指示を出す形になっている。
じつのところ、雇用者の70%がそうしたオープンオフィスで働いている。
たとえば、<P&G><アーンスト・アンド・ヤング><グラクソ・スミスクライン><アルコア><ハインツ>などがこの形式をとっている。
不動産管理・投資会社<ジョーンズ・ラング・ラサール>の重役ピーター・ミスコヴィッチによれば、従業員ひとりあたりのオフィス空間は、1970年代には500平方フィートだったが、2010年には200平方フィートにまで縮小した。
オフィス家具メーカーである<スティールケース>のCEOジェイムズ・ハケットは、2005年にビジネス誌『ファスト・カンパニー』で、「職場は『私』から『私たち』へシフトしている。
かつて従業員たちは『私』を基盤に働いていた。
だが、現在では、チームやグループで働くことが高く評価される」と述べた。
ライバル企業である<ハーマン・ミラー>は、「職場での共同作業やチーム編成」に適した新しいオフィス家具を開発しただけでなく、自社の役員たちも個室からオープンなオフィスへ移動した。
2006年、ミシガン大学ロス・ビジネススクールは、大グループに対応できない教室を取り壊した。
さらに新集団思考は、「協同学習」や「小グループ学習」と呼ばれる、しだいに人気を集めている手法を通して、職場や大学以外の学校教育の場でも実践されている。
多くの小学校で、従来は一律に教壇に向かって置かれていた児童机が、多くなったグループ活動に便利なように四個ほどずつまとめて配置されるようになった。
算数や作文などの科目でさえ、グループ単位で授業が進められるのだ。
四年生の教室では、「グループワークのためのルール」が壁に貼りだされてあり、そのなかには、グループの全員が同じ疑問を持ったときでなければ先生に助けを求めてはならないというルールがあった。
2002年に4年生と八年生の教師1200人以上を対象に実施された全国規模の調査によれば、四年生の教師の55%が共同学習を好み、教師が主導する授業を好むのはわずか26%だった。
授業時間の半分以上を従来のやり方で指導する教師は、四年生で35%、八年生では29%で、それに対して、四年生の42%、八年生の41%の教師が、少なくとも授業時間の四分の一をグループ学習にあてていた。
若い教師のあいだでは小グループ学習の人気がさらに高く、今後もこの傾向が続くだろうと推測できる。
協同アプローチの根底には政治がらみの進歩的な考えがある―生徒がおたがいに学び合えば、自主的な学習ができるという理論だ。
だが、ニューヨーク州やミシガン州やジョージア州の公立や私立の小学校で教師たちから話を聞いたところ、グループ学習は大企業に牛耳られるアメリカ社会のチーム文化のなかで自己主張するための練習の場にもなっているのだと語ってくれた。
「協同学習はビジネス社会の状況を反映しています。ビジネス社会では独創性や洞察力ではなく言語能力が評価の基盤になっています。
上手にしゃべれて、注目を集められる人間でなくてはならないのです。
真価以外のなかにもとづいたエリート主義ですね」マンハッタンの公立学校で五年生を教える教師が語った。
「最近ではビジネスの世界がグループ単位で動いているので、子どもたちも学校でそれに慣れなければならないのです」とは、ジョージア州ディケイタ―の三年生の教師の説明だ。
「協同学習はチームで働く際のスキルを身につけさせる―職場では欠かせないスキルだ」と、教育コンサルタントのブルース・ウィリアムズは書いている。
ウィリアムズはまた、リーダーシップを身につけることが協同学習の最大の利益であると考えている。
実際に、教師たちは生徒たちのマネジメントスキルに大いに注目していた。
アトランタ州のダウンタウンのある公立学校では、三年生を受け持っている教師が「単独作業が好きな」物静かな生徒について、「でも、朝の安全パトロールを任せたので、彼もリーダーになる機会を得たのです」と請け合った。
この教師は親切な善意の人だが、生徒がみんな従来の意味でのリーダーになりたいと願っているとはかぎらないと認めてあげたほうが、その子にとってはよかったのではないだろうか―集団にうまく調和したいと願う人間と、ひとりでいたいと願う人間がいるのだ。
ずば抜けて創造的な人間は、後者に含まれていることがよくある。
ジャネット・ファラールとレオニー・クロンボーグは『才能と能力のある人々のためのリーダーシップ構築』でつぎのように書いている。
外向型が社会でのリーダーシップをとる傾向があるのに対して、内向型は思索や芸術の分野でリーダーシップをとる傾向がある。
チャールズ・ダーウィン、マリー・キュリー、パトリック・ホワイト、アーサー・ボイドといった、思想の新分野を築いたり、既存の知識に新しい光をあてたりした傑出した内向型のリーダーは、人生の大部分を孤独に過ごした。
したがって、リーダーシップとは社会的な状況でのみ発揮されるのではなく、芸術の分野で新手法を生み出す、新しい哲学を築く、重要な書物を執筆する、科学の分野で新発見をするといった、孤独な状況でも発揮されるものである。
新集団思考はあるとき突然に登場したのではない。
協同学習、チームワーク、そしてオープンオフィスの設計は、それぞれ違った時点で違った理由から生まれたものだ。
だが、これらの傾向をひとつにまとめたのはワールドワイドウェブ(WWW)の誕生だった。
WWWはコラボレーションという考えをクールで魅力的なものにしたのだ。
インターネット上には、人々がすぐれた知能を分かち合うことを通じて驚くべき創造物が生み出された。
たとえば、フリーソフトウェアとして公開されたOSである<リナックス>、オンライン百科事典の<ウィキペディア>、インターネットで活躍する草の根政治団体の<ムーブオン・ドットオルグ>などだ。
これらの急激に発展した共同作業の産物はまさに畏怖を感じさせるものだったため、私たちは集合精神や集団の知恵やクラウドソーシングの奇跡を尊敬するようになった。
「コラボレーション」は、成功を増幅させる鍵として、不可侵の概念となった。
だが、つぎに私たちは求められた以上に一歩前進した。
透明性を尊重し、オンライン上だけではなく人と人との関係においても、壁を打ち抜いたのだ。
送信側と受信側がタイミングを気にせずにやりとりする「非同期」は、インターネット上のやりとりの特徴のひとつである。
だが、オープンオフィスという、さまざまな人間関係がからみ、さまざまな騒音が満ちているかぎられた空間内では、それがうまく機能しないかもしれないと私たちは認識してはいなかった。
オンラインのやりとりと人間どうしのやりとりを区別せずに、前者で学んだことを後者にあてはめたのだ。
だから、オープンオフィス設計など新集団思考の側面について語るとき、インターネットに頼りがちになるのだ。
「働く人々はフェイスブックやツイッターなどに自分の生活をなんでもかんでもアップしている。
それなのに、個室の壁のなかに隠れている理由はない」とソーシャルマーケティング会社<ミスター・ユース>のCFOであるダン・ラフォンテインがナショナル・パブリック・ラジオで語った。
別のマネジメントコンサルタントも同じようなことを言った。
「オフィスの壁はまさに『壁』なんです。
思考方法が新鮮なひとほど、壁など必要ないと感じますよ。
オープンオフィス設計を取り入れている企業は、WWWと同じく、まだティーンエイジャーみたいな新しい企業です」
初期のウェブが内向的な個人主義者たちのつながりを可能にした媒体だったことからして、人間どうしの集団思考を促進するうえでインターネットが果たしている役割はとりわけ皮肉に感じられる。
ファラールやクロンボーグが言及したような人々が、ウェブ上で協力して通常の問題解決方法をくつがえし、それを越えるものを生み出したのだ。
1982年から1984年までにアメリカ、英国、オーストラリアで働くコンピュータ専門家1229人に関する研究によれば、初期のコンピュータに夢中になった人々の大多数は内向型だった。
「内向型がオープンソースに惹かれるのは当然だ」-シリコンバレーでコンサルタントやソフトウェア開発をしているデイヴ・W・スミスは、オープンソースとはソフトウェアの設計図にあたるソースコードをインターネットなどを通じて無償で公開し、誰でもそのソフトウェアの改良や再配布ができることだからと説明した。
そうした人々の多くは世の中に貢献したいと願い、自らの業績を社会で認められたいと願って行動したのだった。
だが、最初期のオープンソース・クリエイターたちは、共有のオフィス空間で働いてはいなかった。
そもそも、同じ国にいないことさえあった。
彼らのコラボレーションはおもに想像空間で行われたのだ。
これはささいな要素ではない。
もし、リナックスをつくった人々を広い会議室に集めて一年間で新しいOSをつくってほしいと頼んだとしても、画期的な成果が出るとは考えにくい。
■参考記事
内向型と外向型、対照的な二つの性質
外向型はどのようにして文化的理想になったか
内向型、外向型のリーダーシップ
内向型は生まれつきなのか
孤独のほうが集中的実践ができるようになる
心理学者のアンダース・エリクソンは15歳でチェスをはじめた。
腕前はたちまち上達して、昼休みにクラスメイトと対局してつぎつぎに破った。
ところが、チェスがすごく下手だったひとりの少年が、ある日突然、連戦連勝しはじめた。
いったいなにが起きたのかとエリクソンは不思議に思った。
「理由を一生懸命考えた。あんなに簡単にやっつけていた少年に、これほど簡単に負けるようになったのはなぜなのか。
彼がチェスクラブに入って勉強しているのは知っていたが、本当のところ、いったいなにが起きたのだろうか」と彼は『ザ・タレント・コード』の著者ダニエル・コイルとの対談で語った。
この問いかけがエリクソンのキャリアを方向づけた。
偉大な業績をあげる人は、いったいどのようにしてそれをなし遂げるのか。
エリクソンはチェスやテニスやクラシック・ピアノなど広範囲な領域でこの問いの答えを模索した。
エリクソンが同僚らとともに実施した有名な実験がある。
まずベルリン音楽アカデミーの教授の協力を得て、バイオリン専攻の学生を三つのグループに分けた。
第一のグループは、将来世界的なソリストになれるほどの実力を持つ学生たち。
第二のグループは、「すぐれている」という評価にとどまる学生たち。
第三のグループは、演奏者にはなれず、バイオリン教師をめざす学生たち。
そして、全員に時間の使い方について同じ質問をした。
その結果、グループごとに驚くべき違いがあることが判明した。
三つのグループが音楽関連の活動にかける時間は同じで、週に50時間以上だった。
課題の練習にかける時間もほぼ同じだった。
だが、上位の二つのグループは音楽関連の時間の大半を個人練習にあてていた。
具体的には一週間に24.3時間、一日あたり3.5時間。
それに対して第三のグループが個人練習にあてる時間は、一週間に9.3時間、一日あたり1.3時間だけだった。
第一のグループの学生たちは、個人練習をもっとも重要な活動と評価していた。
すぐれた音楽家たちは―たとえ集団で演奏する者であっても―個人練習が本当の練習であり、集団でのセッションは「楽しみ」だと表現する。
エリクソンらは他の分野についても、ひとりで練習したり学習したりすることが同じような結果をもたらすと発見した。
たとえば、チェスの世界でも「ひとりで真剣に学ぶこと」がプロのチェスプレーヤーになるスキルを得るかどうかの指針になる。
グランドマスターは一般に、修業時代の10年間に5000時間という途方もない時間をひとりで指し手の研究をするために費やす―中級レベルのプレーヤーの約5倍にものぼる時間だ。
ひとりで勉強する学生は、グループで勉強する学生よりも、長年のうちに多くを身につける。
チームスポーツのエリート選手もまた、驚くほど多くの時間を個人練習にあてている。
いったいなぜ、孤独はこれほど魔法のような働きをするのだろうか。
ひとりでいるときにだけ集中的実践が可能になり、それこそが多くの分野において驚異的な成果をもたらす鍵なのだと、エリクソンは語った。
なにかに集中して練習しているときには、より高い知識を身につけたり、パフォーマンスを向上させたり、自分の進捗状況を検討して軌道修正したりすることが可能になる。
こうした水準に達しない練習は無益なだけでなく、逆効果を招きかねない。
向上をもたらすどころか、現状の認知メカニズムを強化してしまうのだ。
集中的実践がひとりでやってこそ効果があるのには、いくつか理由がある。
極度の集中を必要とするので、他人の存在は気を散らすもとになりうる。
心の底から自然に湧いてくるような強い意欲も必要だ。
だが、もっとも重要なのは、あなた個人にとって非常にやりがいを感じさせる事柄に取り組まなければならない、という点だ。
ひとりでいるときにだけ、あなたは「自分にとってやりがいのある事柄に、まともに向き合える。
自分の技術や能力を向上させたければ、自発的でなければならない。
グループ学習を考えて下さい―あなたは集団のなかのひとりでしかありません」とエリクソンは語った。
「集中的実践」の具体例を見るには、スティーブ・ウォズニアックの話がうってつけだろう。
ホームブリュー・コンピュータ・クラブの会合は、彼にとって最初のパソコンをつくるための触媒の働きをしたが、それを可能にした知識や労働習慣はずべて他の場所で得たものだった。
ウォズニアックは子どもの頃からずっと自分の意思でエンジニアリングを学んでいた(エリクソンによれば、真の専門家になるにはおよそ一万時間の集中的実践が必要だそうなので、子ども時代からスタートすることが役に立つ)。
ウォズニアックは『アップルを創った怪物』のなかで、子ども時代に抱いたエレクトロニクスに対する情熱について語っており、そこには図らずもエリクソンが強調する集中的実践のすべての要素が含まれている。
第一に、彼には動機づけがあった。
<ロッキード>のエンジニアだった彼の父親は、エンジニアは人々の生活を変えることができる「世界にとって重要な人間だ」と教えた。
第二に、彼は一歩一歩努力して専門技術を身につけた。
小学生の頃から数々のサイエンス・フェアに出品していたおかげで得たものについて、彼はこう書いている。
「僕は自分のキャリア全般を助けてくれる大切な能力を獲得した。
それは忍耐力だ。ジョークじゃない。
忍耐力は一般にひどく過小評価されている。
僕は小三から中二までのあいだずっと、出品する作品をつくるために、どうやったら電子部品を組み立てられるか、たいして本に頼らずに学んだ・・・結果はあまり気にせずに、目の前の作業だけに集中して、それをできるだけ完璧に仕上げようとすることが大事だと学んだ。」
第三に、ウォズニアックはしばしばひとりで作業に取り組んだ。
これは必ずしも意図的にそうしたわけではなかった。
理科系にのめり込んだ子どもにはよくあることだが、中学生になった彼は、それ以前とはうって変わって仲間からの人気を失った。
それまでは友達が理科や算数の能力を褒めてくれていたのに、誰からも認められなくなったのだ。
彼は無駄話が嫌いだったし、興味の対象が同級生たちとはズレていた。
当時の白黒の写真に写っているウォズニアックは、わざとしかめ面をしてサイエンス・フェアで優勝した自分の作品を指差している。
だが、この頃の苦しい日々にも、夢を追うのはやめなかった。
それどころか、その夢をさらに育てたようだ。
もし、自分が家にこもるほど内気でなかったら、コンピュータについてあれほど学ばなかっただろうと、ウォズニアックは今になって振り返っている。
自ら選んで苦しい思春期を送ろうとする人はいないだろうが、ウォズニアックが10代の頃孤独で、そのあいだに生涯の情熱を傾けるべき対象に熱心に取り組んだという事実は、並外れて創造的な人にとって典型的な話である。
1990年から1995年にかけて、芸術、科学、ビジネス、政治の分野で並外れて創造的な人物91人を研究した、心理学者のミハイ・チクセントミハイによれば、対象者の多くは孤独な思春期を過ごし、その理由のひとつは「同級生たちには奇妙に思えることに強い関心を持っていた」ことだという。
「音楽や数学の勉強には孤独が必要なので」、10代の子どもが社交的すぎてひとりでいる時間がないと、才能を育てるのに失敗することがよくある。
『五次元世界のぼうけん』をはじめ60冊以上もの作品があるヤングアダルト小説の名手マデレイン・レングルは、もし読書と空想に明け暮れる孤独な子ども時代がなかったら、奔放な発想は育たなかっただろうと語った。
少年時代のチャールズ・ダーウィンは友人には不自由しなかったが、自然のなかを長時間ひとりで散歩するほうが好きだった。
大人になっても、それは変わらなかった。
あるとき、著名な数学者からディナーパーティーへの招待を受けたダーウィンは、「親愛なるバベッジ様へ。パーティーへご招待下さいまして、まことにありがたく存じますが、残念ながらお受けできかねます。
なぜなら、天国の聖人諸氏に誓って私は外出いたしませんと言った相手に、パーティで顔を合わせる恐れがあるからです」と書き送った。
だが、並外れた成果は、集中的実践によって基礎となるものを築くだけではなく、適切な労働条件もまた必要とする。
そして、現代の職場では、それを手に入れるのは難しい。
■参考記事
内向型の人間がスピーチをするには
なぜクールが過大評価されるのか
内向型と外向型の考え方の違い
なぜ外向型優位社会なのか
性格特性はあるのか
内向型と外向型の上手な付き合い方
内向型をとことん活かす方法
オープンオフィスは生産性を阻害してしまうのか?
コンサルタントをしていると、多種多様な職場環境をよく知ることができるという会得がある。
コンサルティング会社である<アトランティック・システムズ・ギルド>を率いるトム・デマルコはかなりの数のオフィスに出入りし、特別に人口密度が高いオフィスがあることに気付いた。
そして、それが会社の業績にどんな影響をもたらすかに関心を持った。
デマルコはティモシー・リスターと一緒に<コーディング・ウォー・ゲーム>と名づけた研究をした。
目的は最高と最低のプログラマーの性格を明確にすることだった。
92社の600人以上の開発者が研究に参加した。
各人がプログラムを設計し、コードを書き、テストした。
参加者はそれぞれ、同じ会社からパートナーを割りあてられた。
パートナーどうしは別々に作業するが、情報を交換し合わなくても、出来上がったプログラムはよく似ていた。
ゲームの結果、パフォーマンスに大きな差があるのがわかった。
最高と最低では十対一の割合だった。
最上位のプログラマーは中位のプログラマーの約2.5倍の成果を出した。
これほど驚くべき差が生じた理由は何なのか、デマルコとリスターが調べたところ、経験年数や給与額や仕事に要した時間といった通常考えられる要因はすべて、結果とはほとんど関連がなかった。
経験10年のプログラマーは2年のプログラマーよりも点数が悪かった。
中央値以上を記録した半数のプログラマーの給料は、中央値以下の半数の給料と比較して、10%以下の違いしかなかった―能力の差はほぼ2倍だというのに。
「不良ゼロ」のプログラマーは、そうでないプログラマーと比較して所要時間はわずかに短かった。
この結果は謎だったが、ひとつ興味深い手がかりがあった。
同じ会社のプログラマーは、一緒に作業しなかったにもかかわらず結果はほぼ同レベルだった。
そして、最上位のプログラマーたちは、従業員にプライバシーや個人的スペースを十分に与え、物理的環境の管理を自由にさせ、邪魔されない状況に置いている会社で働いている率が圧倒的に高かった。
労働スペースで十分にプライバシーが保たれていると答えたプログラマーは、最上位グループでは62%だったのに対して、最下位グループではわずか19%だった。
仕事中に必要もないのに邪魔されると答えたのは、最上位グループでは38%、最下位グループでは76%だった。
コーディング・ウォー・ゲームはテクノロジーの世界ではよく知られているが、デマルコとリスターの発見はコンピュータ・プログラムの世界にとどまらない。
多種多様な産業界でのオープンオフィスに関するやまのようなデータが、ゲームの結果の確証となっている。
オープンオフィスは生産性を減少させ、記憶力を損なうことがわかっている。
また、スタッフの離職率も高める。
働く人の気分を悪くさせ、敵対的にし、意欲を奪い、不安を抱かせる。
オープンオフィスで働く人は血圧が高くなり、ストレスレベルが上昇し、インフルエンザにかかりやすい。
同僚と対立しやすくなる。
同僚に電話を盗み聞きされたり、パソコン画面を盗み見られたりするのではないかと心配する。
同僚との個人的で親密な会話が少なくなる。
自分ではコントロールできない騒音にさらされることが多く、それが心拍数を増加させたり、体内で闘争―逃走反応をもたらす「ストレス」ホルモンと呼ばれるコルチゾールを分泌させたりする。
そして人々を、孤立した、怒りっぽく攻撃的な、他人に手を差し伸べない人間にしてしまうのだ。
それどころか、過度の刺激は学習を阻害するようだ。
最近の研究によれば、森の中を静かに散歩した人は、騒音が溢れる街中を歩いた人よりも学習効果が高いと判明した。
多種多様な分野の三万八千人の知識労働者を対象にした別の研究では、邪魔が入るという単純なことが、生産性を阻害する最大の要因のひとつだとわかった。
一度に複数の仕事をこなすことは、現代の会社員にとって賞賛される偉業だが、これもまた神話だとわかった。
人間の脳は一度に二つのことに注意を払えない、と科学者たちは知っている。
一度に二つのことをこなしているように見えても、じつは二つの作業のあいだを行き来しているだけで、生産性を低下させ、ミスを最大で50%も増加させる。
多くの内向型が、このことを本能的に知っていて、ひとつの部屋に大勢で閉じ込められるのを嫌う。
カリフォルニア州オークランドのゲーム制作会社<バックボーン・エンターテイメント>では、当初オープンオフィス・プランを採用していたが、内向型が多いゲーム制作者たちから居心地が悪いという声が聞こえてきた。
「なんだか大きな倉庫にテーブルが置いてあるみたいで、壁もないし、おたがいに丸見えだった」とクリエイティブ・ディレクターだったマイク・マイカは回想する。
「そこで、部屋に仕切りをしたのだが、クリエイティブな部門でそれがうまくいくかどうか心配だった。
ところが、結局のところ、誰もがみんな人目につかないで隠れられる場所を必要としていたとわかった」
2000年に<リーボック・インターナショナル>がマサチューセッツ州カントンの本社で1250人の社員を整理統合したときにも、同じようなことが起きた。
デザイナーたちにはブレインストーミングできるようなたがいにアクセスしやすいオフィスが必要だろうと、上層部が考えた(おそらくMBA時代の体験からそう考えたのだろう)。
だが幸運にも、彼らはまずデザイナーたち当人から意見を聞いたので、本当に必要なのは意識を集中するための静けさと平安だとわかった。
この話は、ソフトウェア企業<37シグナルズ>の共同設立者ジェイソン・フリードにとっては驚きではなかった。
2000年以降10年にわたって、フリードは数百人の人々(おもにデザイナーやプログラムーやライター)に対して、なにかをなし遂げなくてはならないとき、どこで作業したいか尋ねた。
すると、彼らはオフィス以外のさまざまな場所を口にした。
オフィスはうるさすぎて、しょっちゅう邪魔が入るからだ。
そんなわけで、現在フリードのもとで働く16人のうち本社があるシカゴに住んでいるのは8人だけで、会議のために招集されることさえない。
会議は「有害」だとさえ、フリードは考えている。
彼は共同作業に反対しているわけではない。
37シグナルズのホームページは、自社製品が共同作業を生産的かつ快適なものにすると売り込んでいる。
だが、フリードはメールやインスタントメッセージやオンラインでのチャットツールといった受け身の共同作業を好んでいる。
世の中の経営者たちに彼はどんな助言をするだろう?
「つぎの会議をキャンセルしなさい。そして、二度と予定に入れないで、記憶から消し去るのです」と彼は助言する。
さらに、「おしゃべりなしの木曜日」を推奨する。
一週間に一度、従業員どうしが会話してはいけない日をつくるのだ。
フリードの質問に答えた人々は、クリエイティブな人たちがすでに知っていることをあらためて口にしたのだ。
たとえば、カフカは執筆中には愛する婚約者でさえ近づけたがらなかったそうだ。
「僕が書いているそばで座っていたいと、きみは言ったことがある。
けれど聴いてくれ、そうすると僕はなにも書けなくなってしまうんだ。
なぜなら、書くというのは、自分をなにもかもさらけだすことだから。
そうした極限の状態に身を任せているその場に他人が入ってきたら、正常な人間ならば誰だって身がすくんでしまうはずだ・・・だからこそ、書くときにはいくら孤独でも孤独すぎることはないし、いくら静かでも静かすぎることもないし、夜の闇がいくら深くても深すぎることはない。」
世界で愛される絵本作家シオドア・ガイゼル(ドクター・スースという名前でよく知られている)はカフカよりは陽気だろうが、カリフォルニア州ラホヤ郊外の、壁にスケッチや絵をずらりと並べた鐘楼のような仕事場にこもって作業をしていた。
リズム感に溢れた文章とは対照的に、ガイゼルは物静かな人物だった。
絵本読者の子どもたちはきっと『キャット・イン・ザ・ハット』に出てくるような陽気でよくしゃべる人物だと思っているだろうから、そうした期待を壊してはいけないと、ガイゼルはめったに読者たちの前に姿を見せなかった。
「私が出て行くと、たいていの場合、子どもたちは怖がった」とガイゼルは認めた。
内向型のブレインストーミング
個人的な空間が創造力にとって欠かせないものだとしたら、「同僚たちの圧力」から自由になることもまた、そうだと言える。
伝説的な広告マンのアレックス・オズボーンのこんな話を考えてみてほしい。
今でこそオズボーンの名前を知る人は少なくなったけれど、20世紀前半には彼は画期的な発想で同時代の人々を魅了した英雄的存在だった。
オズボーンは広告代理店<バットン・バートン・ダスティン・オズボーン>(BBDO)の共同設立者だが、作家として有名になった。
そのきっかけは1938年、ある雑誌編集者が彼をランチに招待して、趣味はなにかと問いかけたことだった。
「イマジネーションです」オズボーンは答えた。
「オズボーンさん、それをテーマに本を書くべきです。
そういう本がずっと待ち望まれてきました。
最高に重要なテーマです。
時間とエネルギーをそそぐだけの価値があります」と編集者が言った。
そこで、オズボーンは本を書いた。
1940年代から50年代にかけて数冊を執筆したが、いずれもBBDOのトップとしての彼を悩ませていた原因がテーマだった。
すなわち、社員が十分にクリエイティブでない、といったことだ。
彼らはすぐれたアイデアを持っているのに、同僚たちからの評価を恐れてそれを発表しようとしない、とオズボーンは信じていた。
オズボーンの解決策は社員たちをひとりで働かせるのではなく、集団思考による批判の脅威を取り除くことだった。
彼はブレインストーミングの概念を発案した。
集団でたがいに批判せず自由にアイデアを発表し合うのだ。
ブレインストーミングには四つのルールがある。
- 判断や批判をしない
- 自由に考える。アイデアは自由奔放であるほどいい。
- 質より量。アイデアは多いほどいい。
- たがいのアイデアを結合し、発展させる。
批判や評価されることがなくなれば、集団は個人よりも、よりすぐれたアイデアをより多くもたらすに違いないとオズボーンは信じ、ブレインストーミングを強力に喧伝した。
「集団によるブレインストーミングの量的な成果は疑問の余地がない。
あるグループは電気製品の宣伝に45件、募金キャンペーンに56件、毛布の販売促進には124件ものアイデアを生み出した。
また、ある問題について15のグループでブレインストーミングを実施したところ、800件ものアイデアが出た」と彼は書いた。
オズボーンの理論は大きな衝撃をもたらし、企業のリーダーたちはこぞってブレインストーミングを採用した。
今日にいたるまで、アメリカの大企業にいたことのある人ならば誰でもみな、ホワイトボードやマーカーがたくさん置かれた部屋に同僚と一緒に閉じ込められて、いかにも精力的な進行役に、さあ意見を出しなさいと言われた経験があるはずだ。
オズボーンの画期的なアイデアには、ひとつだけ問題があった。
集団のブレインストーミングは実際には機能しないのだ。
それを最初に立証した研究は1963年に行われた。
ミネソタ大学の心理学教授マーヴィン・デュネットは、<ミネソタ・マイニング・アンド・マニュファクチュアリング>(3Mという社名で知られている、ポストイットをつくった企業)で働く科学系研究職の男性48人と広告分野の管理職の男性48人を集めて、単独作業と集団でのブレインストーミングをさせた。
当初デュネットは、管理職の人々は集団作業からより大きな成果を得るだろうと考えていた。
そして、内向型である可能性が高いと思われる研究職の人々については、その可能性は比較的低いだろうと考えていた。
各48人の被験者は、4人ずつ12のグループに分けられ、6本指で生まれてくることの利益と不利益はなにかといったような問題についてブレインストーミングをするよう指示された。
また、各人は同じような問題についてひとりで考えるようにとも指示された。
そして、デュネットらの研究チームは、集団から生まれたアイデアと個人が考えたアイデアの数を比較した。
さらに、アイデアの質を評価して、「実現性」について0点から4点の点数をつけた。
結果は非常に明快だった。
24組のうち23組の人々がグループよりも個人で考えたほうがたくさんのアイデアを生み出した。
また、質の点では、個人作業で生まれたアイデアは、集団作業で生まれたアイデアと同等あるいはそれ以上だった。
そして、広告分野の管理職のほうが科学系研究職よりも集団作業を得意としているという結果は出なかった。
これ以後40年以上にもわたってさまざまな研究が続けられたが、結果はつねに同じだった。
集団が大きくなるほどパフォーマンスは悪くなることが、研究から立証されているのだ。
4人のグループよりも6人のグループのほうがアイデアは質・量ともに低下し、九人のグループではさらに低下する。
「科学的な証拠からすると、集団でのブレインストーミングを採用するのは正気とは思えない。
能力とやる気がある人々には、創造性と効率が最優先で求められる場合には単独作業をするよう勧めるべきだ」と、組織心理学者のエイドリアン・ファーンハムは書いている。
例外は、オンライン上のブレインストーミングである。
電子機器を使った集団のブレインストーミングは、きちんと管理されていれば単独作業よりもよい結果をもたらす。
そして、集団が大きいほどパフォーマンスも向上する。
これは学問的研究の分野にもあてはまる―教授たちが離れた場所から電子機器を使って共同作業をすると、単独作業や対面での共同作業をした場合よりも有力な研究成果を得られる。
これは驚くような結果ではない。
すでに述べたように、新集団思考に貢献した電子機器を通じた共同作業の興味深いパワーなのだ。
もし電子機器上の大掛かりなブレインストーミングがなかったら、リナックスやウィキペディアは存在しただろうか。
けれど、私たちはそうしたオンライン上のコラボレーションのパワーに驚嘆するあまり、あらゆる集団作業を過大評価して、個人による思考を軽視しているのではないだろうか。
オンライン上で集団作業している人々はみな、それぞれに単独作業をしているのだという事実を、私たちは見逃してしまっている。
それどころか、オンライン上の集団作業の成功が、対面の世界でも可能だと思い込んでいるのだ。
実際に、長年の研究から従来の集団ブレインストーミングの参加者たちはその成果を過大評価しており、この手法が人気を得ているのには重要な理由がある―集団でのブレインストーミングには結びつきが感じられるのだ。
だが、目的が社会的な結びつきであるとするならば価値があるけれど、創造性の点からは目的に反している。
集団の中にいることのプレッシャー
心理学者たちはブレインストーミングが失敗する理由を、通常三つあげている。
第一は、社会的手抜き。
つまり、集団で作業すると、他人任せで自分は努力しない人が出てくる傾向がある。
第二は、生産妨害。
つまり、発言したりアイデアを掲示したりするのは一度にひとりなので、その他の人たちは黙って座っているだけだ。
第三に、評価懸念。
つまり、他者の前では自分が評価されるのではないかと不安になる。
オズボーンのブレインストーミングの「ルール」は、この不安を消すためのものだが、恥をかくことに対する恐れは非常に強力なものだと、さまざまな研究が示している。
たとえば、1988年から1989年のバスケットボールのシーズン中、麻疹の流行で大学が休校になって、NCAAの2チームが観客なしで11ゲームを戦った。
敵のファンも味方のファンもいないなかで、両チームともいつもよりも好成績(たとえばフリースローの成功率など)を残した。
行動経済学者のダン・アリエリーはこれと同じような現象に気付いた。
アリエリーは39人の被験者に、自分の机でひとりで、あるいは他人が見ている前で、文字を並べかえて別の単語にするパズルを解いてもらった。
見ている人がいればやる気がそそられて、ひとりでやるよりもよい結果が出るのではないかと、アリエリーは予測した。
ところが、結果は逆だった。
観客の存在は、やる気を生むと同時に、ストレスをかけたのだ。
評価懸念に対する対応が難しいのは、私たちができることはほとんどないというところだ。
意志力や訓練やアレックス・オズボーンが定めた集団のルールによって克服できると、あなたは思うだろう。
だが、最近の神経科学の研究によれば、評価されることに対する恐れは非常に根深く、想像以上に広範囲な影響をもたらしているのだ。
オズボーンがブレインストーミングを推奨していたちょうど同じ時期、1951年から1956年にかけて、ソロモン・アッシュという心理学者が集団心理の危険性に関する、現在ではよく知られた一連の研究をした。
アッシュは学生の被験者を募って、視覚テストをした。
まず学生たちをいくつかのグループに分けて、長さが違う三本の直線が描かれた図Aを見せ、どれが一番長いかと尋ねた。
つぎに、図Bに一本だけ描かれた直線と同じ長さなのはどれかを答えさせた。
そんな具合に質問を続けた。
質問はどれも単純で、95%の学生が全問正解した。
ところが、アッシュがグループのなかにサクラを複数仕込んで、同一の間違った答えを声高に主張させると、全問正解者の割合は25%にまで低下した。
すなわち、75%もの学生が少なくともひとつの問題で、サクラにひっぱられて間違った答えを出したのだ。
アッシュの実験は「同調」のパワーの強さを立証し、オズボーンはその鎖から私たちを解き放とうとしたのだ。
だが、私たちがなぜ周囲に同調しやすいのかについては、二人とも語っていない。
長いものに巻かれてしまう人々の心のなかでは、いったいなにが起きているのだろう?
他人のプレッシャーに負けて直線の長さが違って見えてしまうのか、それとも仲間外れになるのが怖くて、間違いだとわかっている答えを選んでしまうのか。
何十年ものあいだ、心理学者たちはこの問いに頭を悩ませてきた。
現在では、脳の働きを画像で見るfMRI(機能的磁気共鳴画像法)の助けを借りて、私たちはその答えに近づいているようだ。
2005年、エモリ―大学の神経科学者グレゴリー・バーンズは、アッシュの実験の最新版を実行することにした。
バーンズらの研究チームは19歳から41歳の男女32人を被験者とした。
被験者たちはコンピュータ画面で二つの異なる三次元の物体を見せられ、最初に見た物体を回転させると二番目に見たものと同じになるかと訊かれる。
そして、そのときの被験者の脳がどのように働いているかが、fMRIで観察された。
結果は長年の疑問を解明するとともに、不安をも感じさせるものだった。
第一に、それはアッシュの発見を確認した。
被験者がひとりで判断して答えた場合、誤答率は13.8%だった。
だが、集団で自分以外の全員がもれなく間違った答えを選んだ場合、41%が集団にひっぱられて誤答を選んだ。
だが、バーンズの実験は、なぜ私たちが周囲に同調してしまうかにも焦点をあてていた。
被験者の脳内を観察すると、被験者が単独で答えたときには、脳の視空間認知を司る後頭皮質と意識的な意思決定を司る前頭皮質の部分で、神経細胞のネットワークが活性化していた。
だが、他人の誤答に同調したときには、脳の働きがはっきり違っていた。
思い返してみれば、アッシュが知りたかったのは、被験者が集団の意見は間違っていると知っていながら同調したのか、それとも集団によって認知が変化させられたのか、ということだった。
もし、前者が正しければ、意思決定を司る前頭皮質で活動が活発化するはずだと、バーンズらは推論した。
逆に、視空間認知を司る部分の働きが活発化していれば、集団がなんらかの形で個人の認知を変化させたのだということになる。
結果はまさに後者だった。
集団に同調して誤答した人の脳内では、意思決定に関わる部分ではなく、視空間認知に関わる部分が活性化していたのだ。
要するに、集団によるプレッシャーは不快なだけでなく、あなたが問題をどうみるかを実際に変化させるのだ。
これらの初期の発見は、集団がまるで幻覚誘発物質のように作用することを示唆している。
集団が答えはAだと考えれば、あなたはAが正答だと信じてしまう傾向が強い。
「よくわからないけれど、みんながAだと言っているから、そうしておこう」と意識的に考えるのではなく、「みんなに好かれたいから、答えはAにしておこう」というのでもない。
もっとずっと思いがけないことが、そして危険なことが起こっているのだ。
バーンズの実験で集団に同調した被験者の大半は、「思いがけない偶然で意見が一致した」から自分も同意見だったと報告した。
つまり、彼らは集団からどれほど強く影響されているか、まったく意識していない。
これのどこが社会的な恐れと関連しているのだろう?
アッシュの実験でもバーンズの実験でも、被験者全員がつねに同調したわけではないのを思い出してみよう。
一部の人々は周囲からの影響に負けず正解したのだ。
そして、バーンズらの研究チームは、それについて非常に興味深い発見をした。
正解した被験者の脳内では、拒絶されることに対する恐れなどの感情を司る扁桃体が活性化していたのだ。
バーンズが「自立の痛み」と呼んだこの現象は、深刻な意味を持っている。
選挙や陪審裁判から多数決原理にいたるまで、重要な市民制度の多くは意見の相違があることによって成立している。
だが、もし集団が私たち一人ひとりの認知を文字通り変化させることができるのならば、そうした制度の健全性は一般に考えられている以上に脆弱なのかもしれない。
多様化された職場空間がおこす恩恵
ここまで私は対面の共同作業を単純化して反証してきた。
だが、つまるところ、スティーブ・ウォズニアックはスティーブ・ジョブズと共同作業をした。
二人の結びつきがなかったら、現在のアップルはなかっただろう。
母親と父親、両親と子どもそれぞれの結びつきは、創造的な共同作業の実践だ。
実際、対面のやりとりはオンラインのやりとりでは生み出せない信頼感をもたらしうる。
また、人口密度の高さが革新的な発見と相関しているとする研究もある。
静かな森の中での散歩は利益をもたらすものの、混雑した街に住む人々は、都会生活が提供する相互作用の網の目から恩恵を受けているのだ。
内向型の人たちが進むべき道は、対面での共同作業をやめるのではなく、そのやり方を改良することだろう。
一つには、個々人の強さや気質に応じてリーダーシップや他の職務が分けられるような、内向型と外向型との共生関係を積極的に追求すべきである。
もっとも達成度の高いチームは内向型と外向型が適切に混在していると数々の研究が示しているし、リーダーシップの構造についても同じことが言える。
また、万華鏡のように変化する人間どうしの相互作用のなかで自由に動きながらも、集中したり孤独が必要になったりすれば自分だけのワークスペースに隠れることができる、そんな環境を設定する必要もある。
学校は子どもたちに他人と一緒に働くスキルを教えるべきだが―十分に実践され時代に即した形であれば、協同学習は効果的になりうる―意図的にひとりで学習する時間や訓練もまた必要なのだ。
さらには、多くの人々が―スティーブ・ウォズニアックのような内向型はとくに―最大限の成果を生みだすために普通以上の静けさやプライバシーが必要だという認識も欠かせない。
一部の企業は静けさや孤独の価値を理解しはじめたらしく、単独の作業スペースに、静粛ゾーン、カジュアルなミーティングエリア、カフェ、読書室、コンピュータ・ハブ、そして、他人の仕事を邪魔せずに社員どうしが気軽に会話できるように”ストリート”までも提供する、”フレキシブル”なオフィスプランを提案している。
<ピクサー・アニメーション・スタジオ>のオフィスは、16エーカーの広大な敷地に立ち、中央にはメールボックスやカフェテリアやバスルームまで備えたフットボール場サイズのアトリウムがある。
偶然の出会いをできるかぎり促進する、というのが設計のアイデアだ。
さらに、社員たちは小さく仕切られた部屋に机を置いた個人のオフィスを持ち、その内部を好きなように飾ることができる。
同じように、<マイクロソフト>の社員たちも個人用のオフィスを持っている。
しかも、各オフィスはスライドドアや可動式の壁などで仕切られていて、共同作業が必要かそれともひとりで考えるためにプライバシーが必要か、用途に応じて使用できるようになっている。
システムデザイン研究者のマット・デイヴィスによれば、こうした多様化された職場空間は、従来のオープンオフィスよりもこもる場所が多いので、内向型にも外向型にも恩恵をもたらすという。
きっとウォズニアックもこうした新しいオフィス空間設計を肯定するだろう。
アップルを創設する以前、ウォズニアックはヒューレット・パッカードで計算機の設計をしていた。
彼がその仕事を気に入っていた理由のひとつは、会社が同僚どうし雑談しやすい環境だったことだ。
毎日午前10時と午後3時にコーヒーとドーナッツが出て、社員たちは気軽にアイデアを交換し合った。
そのやりとりが特別だったのは、社員たちが落ち着いたリラックスした状態だったことだ。
自伝のなかでウォズニアックはヒューレット・パッカードについて、外見にこだわらない、
社会的な駆け引きに重きを置かない能力主義で、愛するエンジニアリングの仕事から彼を引き離してマネジメントをさせようとはしなかったと記した。
それこそが、ウォズニアックにとって意味のある共同作業なのだ。
気取らない恰好をした、批判とは縁遠いのんびりした同僚たちと、ドーナッツやひらめきを分かち合い、彼が仕事に真剣に取り組むために仕切りのなかに隠れても、誰も少しも気にしない、そんな環境が大切だったのだ。